| |
||||||
3��25���i���j    �@�i�����߂łƂ��������܂��@�@  �@�@�|���쏬�w�Z�͈�l�ЂƂ�Ő��藧���Ă���| �@���Ɛ��݂̂�Ȃ͗��h�ɗ������Ă����܂����B���Ǝ��͒g���ȓ��ƂȂ�A�V��ɂ��b�܂�C�����ς��̊���������������Ǝ��ɂȂ�܂����B���Ɛ��́u�ʂ�̂��Ƃv���ϗ͋������C���́u�������̓��Ɂv�������ɉ̂��グ�Ă���܂����B�܂��C�T�N���݂̂Ȃ���̂��Ԃ��̂��ƂƉ̂������Ƃ�Ǝv��������������ς��炵�����̂ł����B���炵���������v���[���g���Ă��ꂽ���Ɛ��ƐV�U�N���Ɋ��ӂ��܂��B �@��N��U��Ԃ�Ɩ{���ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ�����܂����B��l�ЂƂ�̎q�ǂ������̂��̎����̏u�Ԃ̋P���Ă����p���v�������т܂��B�g�C���̃X���b�p����l�ł��ꂢ�ɕ��ׂĂ�����w�N�̒j�̎q�A�n��̋Ǝ҂̕������t��������������w�N�p�T�b�J�[�{�[���ɁA���X�ɏo��������̋C������`���Ă��ꂽ�q�ǂ������A�o�Z�ǂŏW���ꏊ�ɗ��Ȃ��q��S�z���Ă����Ƒ҂��Ă��Ă��ꂽ�ǒ�����ȂǁA�q�ǂ������͒N�Ɍ����邱�Ƃ��Ȃ������̔��f�Ői��ŕ����Ɏ��g�ގp�𐏏��Ō��܂����B�܂��A�^����A�q�ǂ��܂�A�C�w���s�A���R�����A�Z�N���𑗂��Ȃǂ�ʂ��āA�W�c�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�C�ƌ̂������C���K�̐ςݏグ�̐��ʁC�S�ƐS���ʂ��������p�������̊�����^���Ă���܂����B�������C���̏W�c���x���Ă���̂́C��͂��l�ЂƂ�̑��݂Ȃ̂ł��B��l�ЂƂ�̎v���Ƃ�����荇����������^���Ă����W�c�����肾���̂ł��B���̈�N��U��Ԃ�C��l�ЂƂ�g���S���{���ɑ傫�����������Ǝv���܂��B�݂Ȃ���̗��N�x�̔��Ɋ��҂��܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ �@ �@ �@ �@ �@  �@�����{��k�ЂɎv�������@�@ �@�����{��k�ЂɎv�������@�@�@�����Q�T�N�R��11���ŁA���̑�k�Ђ���2�N�ڂ��}���܂����B���̓��Ɋe�w���ł́A�u�Ђ܂��̂����v�Ƃ����G�{��ǂ�A���b��������Ɗw�N�ɉ������l���鎞�Ԃ������܂����B �@�T�N�Q�g�̊w���ʐM��ǂ݁A���БS�Z�����݂̂Ȃ���ƂƂ��ɍl���Ă݂����Ǝv���A�����ɂ��鎙���̕��͂��Љ���Ă��������܂��B�i�T�|�Q�w���ʐM���f�ځj ��������Q�N�O�A���k�̑����m���ő�k�Ђ�����܂����B �Q�F�S�U�̂��Ƃł����B���͉��Z���ŁA�L�k����ƂĂ��͂Ȃ�Ă���O�d�ł��A���̂��������܂����B�ӂ��ɂ��Ă��Ă��킩��܂����B�Ԃɏ���Ă���悤�Ȃ��`�Ƃ������ł����B���͂��̂܂܋A��܂����B���ꂳ�e���r�����āA���낤�낵�Ă��܂����B���̎����́u�����������v�Ǝv���܂����B ���̒ʂ�A���k�̕����A�{��A���̒���ԁA�����A�c��ڂ��������̂��������Ă����܂����B���́A�v�킸�ACG�������̉f�悾�Ǝv���܂����B���ꂳ���������܂����B �u�Ôg����B�����݂������ˁB�v �Ƃ����܂����B���̂��ƁA��l�́A�e���r�̑O�Ń{�[�ƍ����Ă��܂����B���̎�����A�V����e���r�Łu�Ôg�v�A�u�Ôg�v�ƕ����悤�ɂȂ�A���̓e���r�̑O�ł����ƍl���܂����B�u�E�\���B�����M���������ǁA����͖{���̂��ƁB�v ���ꂩ�疈���A�e���r�ɂ͖S���Ȃ����l�̐l�����̂�悤�ɂȂ�܂����B�ǂ�ǂ������Ă����܂����B�S���Ȃ����l�̉Ƒ��̘b���e���r�ŕ����܂����B�{���{���ŕς��ʂĂ��Ƒ��̎p�A�����Ȃ��炻�̘b�����Ă��܂����B�u�ڂ̑O�ŗF�����������ꂽ�B�v�u��������Ă��ꂽ���������������ł����̂�ڂ̑O�Ō����B�v�ȂǁA���킢�����Șb����ŁA���������āA�܂��~�܂�܂���ł����B ���̂�������͌x�@���ł��B�Ȃ̂ŁA�V���̏I���ɓ��k�ɍs���܂����B�Z�ɂɃo�X�����������Ă���Ƃ���A��������������čL�X�Ƃ��Ă��܂����y�n�B��������́A����̖{����Ă��܂����B���ɑD���オ���Ă���ʐ^�A�Z�ɂ��{���{���ɂȂ��Ă���ʐ^�A���Z�����Ɠ�l�ł��܂��Ă݂Ă����̂��o���Ă��܂��B ���̂��ƁA����Șb���e���r�ŕ����܂����B�Ō�̍Ō�܂Ŏq�ǂ�������Ă����l�A���������đ����̐l�������悤�ƁA�݂̂��܂��Ō�܂ŕ����𑱂����l�A�����݈��̏�ł���Ɗ݂ɂ����l�A���낢��Ȑl�����܂����B ���͂����l���܂����B�����邱�Ƃ͍K�����Ǝv���܂����B���������Ă��������Ȃ��l�������ς��������Ƃ�Y��Ȃ��ł������Ǝv���܂����B �@�����āA����ɒ����V���̃R�����̐蔲�����͂�A���̒��ɏ�����Ă����{��̏��R�̏��̎q�̃G�s�\�[�h�i���̓��̒��A��e�ƃP���J���Ďӂ�Ȃ��܂܊w�Z�ɏo�������B�A��r���n�k���N����A���̎q�͊w�Z�ɖ߂��Ė������������A��e�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�n�k�̂������̂����j���������̂ŁA���j���̂Q�F�S�U�Ƀx����炵�A��e�Ɂu�S�����l�v�𑗂��Ă���B�j�ɂ��Ă��R�����g�������Ă���Ă��܂��B �u���͍Ō�́u�S�����l�������Ă���B�v�̂Ƃ��낪�ƂĂ����킢�����ɂƎv���܂����B�ӂ�Ȃ������q�͐S�c�肾�Ǝv���܂����B�ƂĂ����킢�������Ǝv���܂����B �S���Ȃ����l�͖߂��Ă��Ȃ�����ǁA���C�͖߂��Ǝv���܂��B�Ȃ̂ŁA���k�̐l�����ɑ������C�ɂȂ��Ă��炢�����Ǝv���܂��B�v �@ |
||||||
�R��11���i���j    �Z�N���̂������������������u���ӂ̂ǂ��v�@  �@�R���U���i���j�́C���H���͂���łU�N����Ấu���ӂ̂ǂ��v���s���܂����B���̂ǂ��͑̈�قłU�N���Ɖ��쏬�w�Z�̋��E���ƂłQ���Ԃقǂ̊y�������Ԃ��߂����܂����B �@11��50���ɂU�N�����E�����܂ł������}���ɂ��āC����̑̈�قւƈē����Ă���܂����B�̈�ق͎������ƒ����ō��ꂽ�e�[�u����15�قǂ���C�o�}���̔���̂Ȃ���ʂ�Ȃɒ����܂����B�͂��߂̂������̂��ƁC��W���[�X�Ŋ��t�����܂����B���̌�͗�������蕪���܂����B�u�������ł����I�����W�ł����v�u�f�U�[�g�͂ǂꂪ�����ł����v�ƒ��J�ɐq�ˁC�����ĂȂ��̋C�����������Đڂ��Ă���܂����B�y������H��i�߂�Ȃ��ŁC���w�Z�œ��肽���N���u������Z��o���̂��ƂȂǂ��낢��Ɗy�����b���ł��܂����B��ϊy�������Ԃ��߂��܂����B  �@ �@ �@ �@ �@���悢��U�N���e�N���X����̏o�����ł����B  �@�Q�g��EXILE�̃s�A�m�̐����t�ɏ悹�āC�����̓��Z�����낢���I���Ă���܂����B�Ȃ�ƂсC�o�N�e���C�s���~�b�h�ƌ�������������܂����B�Q�Ȗڂ́u���X�����āv�̉̂ɏ��C�x��͌��C�����ς��ŃN���X����ۂƂȂ��Ă���l�q���悭�킩��܂����B�r���ł̂S�i�s���~�b�h�͂ƂĂ������ł����B �@�Q�g��EXILE�̃s�A�m�̐����t�ɏ悹�āC�����̓��Z�����낢���I���Ă���܂����B�Ȃ�ƂсC�o�N�e���C�s���~�b�h�ƌ�������������܂����B�Q�Ȗڂ́u���X�����āv�̉̂ɏ��C�x��͌��C�����ς��ŃN���X����ۂƂȂ��Ă���l�q���悭�킩��܂����B�r���ł̂S�i�s���~�b�h�͂ƂĂ������ł����B �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@�P�g��AKB48�u�L���K���`�F�b�N�v�̋Ȃɏ��C�O��̏��̎q����������T�V���c�p�ŁC���Ă��ȃ_���X���I���܂����B����Ɠ����i�s�ŁC���ꂼ��̓��Z�̔�I������܂����B�u���肪�Ƃ��v�̏K���p�t�H�[�}���X�C�T�b�J�[�̃��t�e�B���O�C�_���X�̃\���C�o�h�~���g���C�̑��C�������ȂǂƑ�ϊy�����V���[�̂悤�ł����B�㔼�ɂ͑O��̃_���X�ɒj�q�������C��l�ЂƂ�̂Ȃ���������܂����B �@�P�g��AKB48�u�L���K���`�F�b�N�v�̋Ȃɏ��C�O��̏��̎q����������T�V���c�p�ŁC���Ă��ȃ_���X���I���܂����B����Ɠ����i�s�ŁC���ꂼ��̓��Z�̔�I������܂����B�u���肪�Ƃ��v�̏K���p�t�H�[�}���X�C�T�b�J�[�̃��t�e�B���O�C�_���X�̃\���C�o�h�~���g���C�̑��C�������ȂǂƑ�ϊy�����V���[�̂悤�ł����B�㔼�ɂ͑O��̃_���X�ɒj�q�������C��l�ЂƂ�̂Ȃ���������܂����B �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�U�N���̎����݂̂Ȃ���́C��l�ЂƂ肷�Ă��ȗ͂������Ă���Ɖ��߂Ċ����܂����B���̈�l�ЂƂ�̂悳�����܂��������C�傫�Ȃ��̂�n��グ�Ă���܂����B�v���Ǝv�����d�Ȃ荇���C�Ȃ��肪���邩�炱���C���҂��ꂽ�����������������邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B���ꂩ�炻�ꂼ��̒��w�Z�ɐi��ł����킯�ł����C���������Ă��ꂽ�悤�ɁC�����̂悳���o���C�����̖��͂��X�ɖ����āC�V���Ȏ�����n��グ�Ă����Ă��������B�u���ӂ̂ǂ��v�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�{���Ɋy�����C���C�������ς����������܂����B�����̐S�z��Ɋ��ӂ��܂��B  �@ �@ �@ �@  �@���쏬�w�Z�u�w�Z�n���L�O���v �@���쏬�w�Z�u�w�Z�n���L�O���v�@�R���P���͉��쏬�w�Z�̊w�Z�n���L�O���ł��B�Z�����ɂ́w�L�т扺��@  ���쏬�w�Z�S���N�L�O���x�i���a51�N�i1976�j�R���P�����s�j���c����Ă��܂��B����44�y�[�W�u��C���쏬�w�Z�S�N�̕��݁v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B ���쏬�w�Z�S���N�L�O���x�i���a51�N�i1976�j�R���P�����s�j���c����Ă��܂��B����44�y�[�W�u��C���쏬�w�Z�S�N�̕��݁v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�@���쏬�w�Z�̃V���{���C�Z�R�C�A�i�ʂ܂����j���C�Z��ɐA����ꂽ�̂��C���a�ܔN�i1930�j�̂��Ƃł��B���ꂩ�獡���܂Ŏl�\�ܔN�̔N��������܂����B�c�ł��������̂��O�K���Ă̍Z�ɂ�荂���Ȃ�C�ЂƂ�ł͂Ƃ��Ă��肪�܂�肫��Ȃ��������Ȃ��Ă��܂��B�l�\�ܔN�Ƃ����N���͂���قǂȂ������̂Ȃ̂ł��B�������̉��쏬�w�Z�����܂�܂����̂�������N�i1876�j�C�{�N�̎O������ł��傤�ǕS�N�ɂȂ�܂��B�Z�R�C�A�̕c������Ȃɑ傫���Ȃ����N���̓�{�ȏ�̗��j�����������쏬�w�Z�͕���ł����킯�ł��B  �@ �@ �@ �@ �@����25�N�R���P���i2013�j��137��ڂ̊w�Z�n���L�O�����}���܂����B�{�N�x�̑��Ɛ��͉��쏬�w�Z137�����ƂȂ�킯�ł��B137�N�̗��j���������C���h�ɑ��Ƃ��C�n��������C�n��ɍv�����Ă����Ăق����Ƃ������܂��B ���쏬�w�Z�̕��݂̈ꕔ�����Ă݂����Ǝv���܂��B �s�w�Z�̂͂��܂�t �� �����ܔN�i1872�j�Ɋw���͎��{����܂������C����n��ɂ͂����Ɋw�Z�͐��܂�܂���ł����B������N�i1876�j�R���P���C�u�J���w�Z�v�Ƃ������ŏ��߂Đ����̊w�Z�Ƃ��đn������܂����B �� ���̊w�Z�͒������i���̒������j�C��������C��������i���̑�����j�ƒ����C�������i���̔����n��̈ꕔ�j�̌܂������������Ă���܂����B �� �����\�O�N�i1880�j�ꌎ������C������C�����C�D��C�k�R�C�R��̘Z�����ŁC�ꏊ�����掛�ƌ��߁C���߂āu����w�Z�v�Ɩ����܂����B �s���a�̑傫�ȕω����t �� ���a��\��N�i1954�j��������������āC�l���s�s�����쏬�w�Z�Ɖ��̂���V�������݂��n�߂܂����B�i�O�d�S�ɑ����Ă������쑺�͎l���s�s�֍������܂����B�j �� ���a�O�\��N�i1964�j����l�\��N�i1966�j�ɂ����āC���������u�c�n�C������c�n�̓������n�܂�C�������������n�߂��B���a�l�\�N�i1965�j�̎�������237���V�w���C���a�\�N�i1975�j�̎�������857��21�w���ƂȂ�C10�N�Ԃ�500�l�ȏ�����������ƂɂȂ�܂��B �� ���a�l�\�Z�N�i1971�j�ɂ͍Z�̂����낤�Ƃ����@�^�������܂�C������̌���������\�O�搶����삵�Ăł�������܂����B��Ȃ͉��{�q���搶�ł��B �� ���a�l�\��i1974�j�N����\��N�i1976�j�ɂ����āC�k�Z�ɂƓ�Z�ɂ��V�������z����C�قڌ��݂̌`�ƂȂ�܂����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@100�N�̗��j�����Ă݂�ƁC���߂Ċw�Z���ǂ̂悤�ɂ����Ă��������悭�킩��܂��B����n��Ŋw�сC�n��Ŋ���Ă���ꂽ���X�̂��Ƃɑ������߁C�`�����鉺�쏬�w�Z�̈�l�Ƃ��āC���悢�w�Z��n��グ��w�͂��݂�Ȃł��Ă����܂��傤�B |
||||||
| �R���T���i�j �@�@  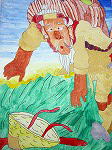   ���ӂ̎v���������ς����u�Z�N���𑗂��v�@  �R���P���i���j�Q�E�R���ڂɁu�Z�N���𑗂��v���Â���܂����B���̂Q���Ԃ͑�ω��₩�ł������Ƃ������Ԃ����ꂽ�悤�Ɋ����܂����B�P�N������T�N���܂ł��C���܂œo���Z��w�K�C�����C�V�сC���H�C�|���Ȃǂ��ׂĂ̋��犈���ł����b�ɂȂ������Ƃ����t��́C���t�C�_���X�Ȃǂŕ\�����܂����B �@�u���肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ������t���d�Ȃ荇���C�C�������d�Ȃ荇���ƁC�^�Ɍ��t�̂��u�����������v�Ƃ�����x����u�v���v�����̂悤�ȉ��₩�ł������Ƃ������Ԃ��������o���̂��Ɗ����܂����B���̉�����E�i�s�߂Ă��ꂽ�T�N���ɂ܂����ӂ��q�ׂ����Ǝv���܂��B 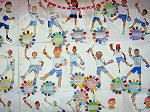 �@ �@ �@ �@ �s�U�N������t �@�D���Ȍ��t�C���ӂȃX�|�[�c�C�D���ȐH�ו��C�D���Ȃ��ƂȂǁC��l�ЂƂ�̏Љ�s����Ȃ��C�U�N���͓��ꂵ�܂����B�D���Ȍ��t�ł́u������߂Ȃ��v�u�p���͗͂Ȃ�v�u�ǂ�����H�v�u���v�u������v�Ȃǂ��Љ��܂����B���ꂼ��̎v����M���������܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�S�N���@�u�G�C�T�[�v�ق��t �@�P�ԃo�b�^�[������Ȃ̂��C���ْ��C���̃X�^�[�g�ł������C���芴�C���͂Ƃ��ɂ��炵���C�S�N���̒�͂������܂����B�G�C�T�[�͉^����ɔ�I�������̂ł����C�ȑO���葫���L�т₩�ŁC�`�����܂��Ă��āC�y����ŗx���Ă��銴�����܂����B���ꂩ�炪�y���݂Ȋw�N���Ɗ����܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�R�N���@�u�Ԋ}�v�ق��t �@�^����̂Ƃ��ɔ�I���Ă��ꂽ�Ԋ}��������x�����Ă���܂����B�x�荞��������C�Ԋ}�≺���g�̓����͈��芴�ƃL��������܂����B�u�o�[�h�E�H�b�`���O�v�̉̂ƃ��R�[�_�[���t�͂R�N���̑f���ł܂��߂ȋC�������ƂĂ��悭�`���܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�Q�N���@�u�̂ƃ_���X�v�t �@�u���̐���̂悤�Ɂv��͋������Ŗ{���ɂ���₩�ɉ̂��܂����B�_���X�͑̂������ς��g���Ă݂̂�Ȃ��y�����Ȃ�_���X�ŁC�ꏏ�ɗx���Ă݂����Ȃ�܂����B�Q�N���̕\���͌���l�������K���ɂ��Ă���܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�P�N���@�u���ނ��т�����i�Q�ǂƉ́j�v�t �@�P�N���݂̂Ȃ���ɂ͖{���ɋ�������܂����B�Q�ǂ͖{���ɂ悭���K����Ă��āC�����Ă��Ă��X�g�[���[�̂������낳���`����Ă��܂����B�܂��C�͂�����Ƃ������t�Ŋ��ӂ̌��t���C���C�Ȑ��Łu���肪�Ƃ��̉́v�̉̂��v���[���g���Ă���܂����B�U�N���ƈ�ԂȂ���̂������P�N���̋C�����������ς������܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�T�N���@�u�̂Ɗ�y���t�v�t �@�T�N���͍���̊��E�^�c�����C�o�����̗��K�����Ă��܂����B��������Ƃ����i��Ƒ�\�������ȂǁC�悭������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�̂͂��ꂢ�ȃn�[���j�[��t�ŁC��y���t�u�L���}���W�����v�ŃA�R�[�f�B�I����؋ՂȂǂ��낢��Ȋy��ƃ��R�[�_�[�̂܂Ƃ܂�̂��鉉�t�ŁC�T�N���̗͂�]�����ƂȂ��������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B����̑����ł́C���N�̍ō��w�N�ւ̈ӋC���݂������܂����B�{���ɂ���J�l�ł����B  �@ �@ �@ �@ �s�P�N������̃v���[���g�t �@�P�N�����������ς�������f�G�ȃ��b�Z�[�W���肵������U�N����l�ЂƂ�̎�ɂ����āC���ӂ̌��t��Y���܂����B  �@ �@ �@ �@ �s���Ɛ����t �@�U�N�������Ǝ��ɉ̂��������Q�ȃv���[���g���Ă���܂����B�u�������̓��Ɂv�̍����͗͋����̂Ȃ��ɂ������ʂ�̂��т����������܂����B�U�N����l�ЂƂ�̎v�����ɂ��Ȃ���C���Ǝ��܂ŗL�Ӌ`�ȓ��X���d�˂Ăق����Ǝv���܂��B  �@ �@ �@ �@ �s�S�Z�����t �@�S���Łu�p�[���p�[���v���̂����̂ł����C�R�Ԃ���̓T�v���C�Y�ŁC�U�N���ւ̊��ӂ̎v�������߂��ւ��̂ŁC�U�N���͉������N�������̂��ŏ��͂���낫��낵�Ă��܂������C�������̎v������������Ǝ~�߂Ă���\��ł����B  �@ �@ �@ �@     �s��2���@�a���ۉ��t�ƃ��[�N�V���b�v�t �s��2���@�a���ۉ��t�ƃ��[�N�V���b�v�t�@�����̑�Q���Ƃ��āC���N�́u�a���ہv���t����悵�܂����B�a���ۑt�҂̕������V����͍��Z���ォ��a���ۂ��n�߁C1995�N����u�a���ۈ�H�i���JDO��H�j�v�̃����o�[�Ƃ��ă��[���b�p�c�A�[�ȂǂɎQ�����C���E�e�n200��ȏ���̌�������������Ă�����ł��B���͒Îs���ݏZ���C�a���ۑt�҂Ƃ��Ċ���Ă��܂��B �U�N�����͂��߁C�S�Z�����ɘa���ۂ̋����Ɠ��{�̓`���̉��y�ƃ��Y���̐����t�ɐG��Ă��炤���Ƃ�ړI�Ɋ�悵�܂����B����͊w�Z����̑��Ƃ����U�N���ƂP�N�Ԃ悭�撣�����S�Z�����݂̂Ȃ���ւ̃v���[���g�ł��B�a���ۂ̗͋��������Ɩ������ɐS����������܂����B�r���̃��[�N�V���b�v�ł͂U�N���𒆐S�ɑ��ۂɒ��킵�悤�̃R�[�i�[������܂����B�����Ƌ��������Ƌ����������悤�Ɍ����C��ɋ������c��悤�ɂȂ�܂ł������܂����B�T�N���ȉ��̎q�ǂ��������̌����C���ۂ̖ʔ������������Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̂��Ƃ��C�a���ۂ̉��y��y�퉉�t�̊y�����̂��������ɂȂ��Ă����Α�ς��ꂵ������ł��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �l�N�����u�E�T�M�̎���v���n�߂܂� �@���N�x�Ɍ����Ă��낢��Ə�����i�߂Ă��܂����C���܂ŃE�T�M�̎��������ψ�����Ă��܂������C����25�N�x����͂S�N���S���Ŋw�N���������悤�ɕύX���������Ǝv���܂��B�w�N��������邱�Ƃɂ��C�U�N�ԂőS��������̌o�������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B �@���N�x�̃E�T�M�̎���Ɍ����ĂR�N���́C�Q��26���i�j�ɕ��R�����a�@�̏b�コ����}���ăE�T�M�̏K���C�����C������@�Ȃǂɂ��đ�Ϗڂ����w�K�����܂����B���̓��e�������Љ�����Ǝv���܂��B  �s�s�����^�̂��Ɓt �s�s�����^�̂��Ɓt�@�I�X�C�J�C�E�T�M�ނɑ�������{���F��   �s�J�C�E�T�M�̐����t �s�J�C�E�T�M�̐����t�E �����@�� �E ��s���i�H�ׂ�̂́C���C�[���C�钆�j �E �ЂƂ�ŕ��C �E �I�X�ǂ����͂������� �E �������ł���i�������Ƃ�����₳����������C������邱�ƂɂȂꂳ���Ă����Ƃ悢�j  �s�����t �s�����t�E �����L�ё�����̂ŁC��ɏ�Ɖ��̎��������Ă���B�����������ł���B�������Ă���̂͂��̓���ł���B �E �����キ�Đ܂�₷�� �E �畆���������Ĕj��₷���i������܂���܂Ȃ��j �E ���������͓����ł͂Ȃ��i����������C�����I�����W�C�Ԓ��F�ŐH�ו��ŐF���ς��j �E �����Ƃ���C���邳���Ƃ���C���߂��߂����Ƃ��낪���� �E �ւ�H�ׂ邱�Ƃ�����i�ւɉh�{������̂ŁC�h�{�⋋�ɖ钆�ɐH�ׂ邱�Ƃ�����j   �s�H�ו��̗^�����t �s�H�ו��̗^�����t�E �����������Ԃɗ^���� �E �c�����a�͎̂Ă� �E �e��͂��ꂢ�ɐC�a������ �E �V�������C�����i���Ə����ɂ悢�j �E ���̓��r�b�g�t�[�h�C�[���̓j���W���C�L���x�c�Ȃ� �E �������̂�p���Ȃǂ͑����Ă��T�ɂP����x�i�^���Ȃ��Ă��ǂ��j �@���̑��ɂ�������̐��b������Ƃ��ɂǂ�Ȃ��ƂɋC�����Ȃ�������Ȃ����C�����̃E�T�M�̊ώ@�̃|�C���g����������Ƌ����Ă��������܂����B���Ɋώ@�ł́u���̎��肪����Ă��Ȃ����v�u�ڂ��ɂ�������C�ڂ�ɂ��o���肵�Ă��Ȃ����v�u�����͂��Ă��Ȃ����v�ȂǁC�C�����Ă������ƂȂǂ��m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B�E�T�M�̎����ʂ��āC�q�ǂ������͖{���ɂ�������̂��Ƃ��w��ł���邱�Ƃł��傤�B����������Ă邱�Ƃ͂ƂĂ�������C���C�̂���d���ł��B�����̌��Ȃ��Ƃ́C�E�T�M�����Ȃ̂ł��B��ɑ���̗���𗝉����C�炿�������Ƃ�����̒l�ł��ł͂Ȃ��ł��傤���B    �@ �@ |
||||||
2��26���i�j    ��R���u�w�Z�Â��苦�͎҉�c�v���J���܂����@  �@�Q��21���i�j�ɖ{�N�x�ŏI�̑�R��w�Z�Â��苦�͎҉�c���s���܂����B�{�N�x�̂V���̑S�ψ��̏o�Ȃ̂��ƁC�{�Z�̋��犈���⎙���̗l�q�Ȃ�  �̂��ӌ��◈�N�x�Ɍ����Ă̂������������@��������܂����B�����Ƃ���11���Ɏ��{����������ی�҂݂̂Ȃ���̋��犈���Ɋւ���A���P�[�g���Q�l�ɂ��Ȃ���M�d�Ȃ��ӌ������������܂����B �̂��ӌ��◈�N�x�Ɍ����Ă̂������������@��������܂����B�����Ƃ���11���Ɏ��{����������ی�҂݂̂Ȃ���̋��犈���Ɋւ���A���P�[�g���Q�l�ɂ��Ȃ���M�d�Ȃ��ӌ������������܂����B�s�ψ��݂̂Ȃ���̂��ӌ��Ȃǁt �����Ɋw�K�̍���Ȏ����ɑ��Ă̕�K���܂߂��o�b�N�A�b�v�̐������肢�������B�Œ���̓ǂ݁E�����E�v�Z��g�ɂ�����g�݂̏[����]�݂܂��B �� �w�Z����Ɋւ���A���P�[�g�i�ی�ҁE�����j�̔N�x���Ƃ̐��l�̔�r�����C�ۑ�𖾂炩�ɂ��Ăق����B�w�N�ɂ�����������̂ŁC�w�N�ɍ��킹�����g�݂�i�߂Ă����Ă͂ǂ����B �� �u�w�Z���y�����Ȃ��v�̐��l�����C�ɂȂ�̂ŁC���N�x�̂Ȃ��܂Â���̎��g�݂���H�v�������̂ɂ��Ă����Ă��炢�����B���Ɂu�l�̒ɂ݂��킩��v�����̈琬��}���Ă��炢�����B �� �F�������ɂ��Ē��ǂ��߂����Ă���悤�ň��S�����B�������C������肪�N�����Ƃ��ɁC���k������v����ӌ����o���������肷��u�b�������v�ꂪ���Ȃ��悤�Ɏv���B�X�N�[���J�E���Z���[�̊��p���܂߁C�����������@��𑝂₵�Ăق����B �� �n����̍H�ꌩ�w�C�n��̕��������Ă̊w�K�ȂǁC���܂��܂Ȏ��g�݂����H���Ă��炢�C���肪�����B �� �u�悤������y�v�̎��g�݂̂悤�ɁC�������Ƃ̑���C�����ɂȂ��邱�ƁC�ڕW����������w���𑱂��Ă����Ăق����B �� �R�~���j�P�[�V�����\�͂̈琬��}��ƂƂ��ɁC�X�L���̏K�����玩�M�ɂȂ���w��������w�i�߂Ăق����B �� �}���{�����e�B�A�Ƃ��č�����Ǐ����L���銈���̎菕�������Ă��������B �� ���͋���������鎞��ł����āC�q�[���[�����Ȃ��B���ꂼ��̓��ӂȂƂ��낪�����ł���悤�ɂ��Ă����Ă͂ǂ����B���ꂪ���M�ւƂȂ���C���肪�������������܂��B �� �������������Ƃł���悤�ɂ��Ă����Ăق����B���̌�ʈ��S�w�������Ă��ē��Ɋ�����B �� ���]�ԃw�����b�g�̒��p�������Ɛi�߂��ق����ǂ��B�w�Z�����Ō[���𑣂��Ă��邪�C�ƒ�ւ̎w�������肢�������B �@�{�N�x�̋��犈���Ɋւ���M�d�Ȃ��ӌ��₲�����������܂����̂ŁC���������Ȃ���C���N�x�̋��犈���Ɋ������悤�ɍH�v�Ɖ��P�������Ă��������ƍl���܂��B�ڂ������e�ɂ��܂��ẮCPTA����Ɉ��������Ắu�w�Z�Â���r�W������������v�ŕ���25�N�x�̕��j������������Ă��������\��ł��܂��B����Ƃ��{�Z�̋���ɂ������E�����͂����܂��܂��悤��낵�����肢�������܂��B  �@ �@ �@ �@ �@ �@�R�N���u�����Â���Ɛ̂̂��炵�v�@�@�@  �@�R�N���͑����I�Ȋw�K�̎��Ԃ𒆐S�ɁC�P�w���́u�w�����ł̑哤����Ă悤�v�C�Q�w���́u�}�������ׂ悤�v�u�哤�̎��n�v�C�R�w���́u���������낤�v�u�ΉP�ł��Ȃ������낤�v�Ɗw�K��i�߂Ă��܂����B����Ȃł��Q�w���͐������u��������������哤�v�̊w�K�����Ă��܂����B���̂悤�ɂP�N�Ԃ������č͔|�E���n����H�i�Â���܂Ŏq�ǂ������͂�������̑̌��Ɗw�K����ł��܂����B�����āC���̊w�K��ꎓ������JA�݂��̐E���݂̂Ȃ���̂��w���������č��グ�邱�Ƃ��ł��܂����Bꎓ�����́u�ɂ���v���g���ĊQ������哤����邱�ƂȂǂ������܂����B�哤�𑋌��ɂ��낢��Ȋw�K�ւƓW�J���C�����Ǝq�ǂ������͔_�Ƃ���H�i�����܂ł̎d����Y�҂̋�J��v���C���i�H�ׂĂ���H�ו����ǂ̂悤�ɍ���Ă���̂��ȂǁC���낢��ƍl���C�[�����ɍ��ނ��Ƃ��ł����ł��傤�B �@�Q���T���i�j�́CJA�݂��̖x����ɗ��Ă��������C�Ƃ��ӂÂ���ɒ��킵�܂����B�e�ǂɂ͕ی�҂̕����P��������Ă��������C�Ƃ��ӂÂ���̕⏕�����肢���܂����B�~�L�T�[�ɑ哤�Ɛ�������C�P���Ԃ���������C�����Ԃ���œ��������ڂ�����C�{���Ɏ葁���y��������Ă��܂����B��ԋ�J�����̂́C���ڂ����������ɂ����C20����������肩�������Ȃ��牷�߁C���~�߂Ă���75���ɂȂ�����ɂ�������Ă���������Ƃ���ł��B �@���āC�ǂ̂悤�ɓ������ł����������̂ł��傤���B�q�ǂ������̊��z���Љ�����Ǝv���܂��B  �@ �@ �@ �@ ���킽���́C�����łƂ��ӂ������Ȃ�Ēm��܂���ł����B �Ƃ��ɂイ���ɂ߂Ă��鎞�C�}�X�N���͂����āC���ɂ����������ł���ƁC�ɂ������킩���Ă��܂����B �������ɂ�������C�Ƃ��ӂ̂ɂ����ɂȂ��āC�H�ׂ��Ƃ��ɂ͂��܂������ł��B �����ڂ肶��̂����E�������������āC�Ƃł��������ɗ���������Ă�����āC�������������ł��B ���Ƃ��ӂ͂��܂������ł��B �ł��C������Ƃ����ɂ��݂�����܂����B �ł��C�ɂ��݂�����������C�������������ł��B �Ƃ��ӂ��Ƃō���Ă݂����ł��B  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �s�̂̂��炵�ƃ|�X�^�[�Z�b�V�����t �@ �@�R�N���͂P���ɓ����Ďl���s�s�������قɍs���āC�̂̂��炵��m�邽�߂ɂނ����̓���Ȃǂ����ۂɌ��āC���ׂĂ������̂��܂Ƃ߂Ă��܂����B �@����͂��̂܂Ƃ߂����̂��|�X�^�[�Z�b�V�����`���Ŕ��\����@��������܂����B�|�X�^�[�Z�b�V�����Ƃ́C���\����l�������ɕ����C���\����l�����ƕ����l��������シ��̂������ł��B���\���������蕷�����Ƃ��ł��C�܂��C�����l���������Ȃ��l���ł��邱�Ƃ������̂Ŕ��\���₷�����̂ł��B �@�����̎l���ɂS�l�̔��\�҂����āC���̃u�[�X�ɂS�O���[�v�ɕ����ꂽ���̎q��������シ��`���Ő̂̂��炵�ɂ��Ē��������w�K�����܂����B��l�̎q�����\������C�U�l���炢�̐l���玿�����`�Ŋw�K��i�߂܂����B���\�҂͂P���ԂɂS��b���@�����C������͂S�l�̔��\���ڂ����m��C�܂��\���Ɉӌ��������ł���̂ł��B���߂Ă̌o���Ȃ̂ł��܂��͂����Ȃ��Ƃ��������܂������C���\���͂��������q�ł������̎v����`���邱�Ƃ��������ł����悤�ł��B�Ō�ɕtⳂł��ꂼ�ꂩ�烁�b�Z�[�W���������̂ł����C���\�҂̎��M�ɂȂ���R�����g����������C��ϗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂������悤�ł��B  �@ �@ �@ �@ ��26��O�����E���w�Z���ʎx���w���w�K���\�� �@�Q��22���i���j�Ɏl���s�s������ّ�Q�z�[���œ��ʎx���w��  �̎q�ǂ������̊w�K���\��s���܂����B�w�K���\��Ƃ����̂́C�O���n��̏����w�Z�̓��ʎx���w���̎������k�������C�����̊w�K�����̐��ʂ�5���Ԃ̃X�e�[�W���\��W�����Ŕ��\��������ł���C���N�C���̎����ɍs���Ă��܂��B�X�e�[�W���\�ł́C���R�[�_�[���̉��t�C���є��E�Ȃ�Ƃѓ����e�Z����I���Ă��܂����B �̎q�ǂ������̊w�K���\��s���܂����B�w�K���\��Ƃ����̂́C�O���n��̏����w�Z�̓��ʎx���w���̎������k�������C�����̊w�K�����̐��ʂ�5���Ԃ̃X�e�[�W���\��W�����Ŕ��\��������ł���C���N�C���̎����ɍs���Ă��܂��B�X�e�[�W���\�ł́C���R�[�_�[���̉��t�C���є��E�Ȃ�Ƃѓ����e�Z����I���Ă��܂����B�@���쏬�w�Z�̂Ȃ��悵�w���́C�����C���Ƃ̏��߂Ɏ�����Ă���_���X���I���Ă��܂����B�������D���Ȃ����[�ς݂�ς݂�̉��y�ɍ��킹�āC�y�����̂������Ƃ��ł��܂����B�\����L���ŁC�{���Ɋy�������Ō��Ă���ق������ꂵ���Ȃ��Ă��܂����B��ꂩ��傫�Ȏ蔏�q�����炢�C�傫�ȒB�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B �@          |
||||||
2��8��(���j  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@���U�N�����@�@�u�R�K���璭�߂����i�v�@                     �@��5�N�����@�@�u�z���C�g�{�[�h�v�@�@   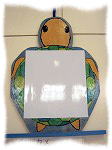      �@�@ �@�@           �@���S�N�����@�u�ʼn�|�����ȕ\����݂Ă��������v�@  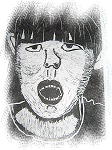 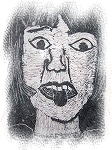 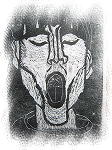 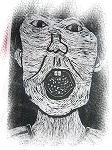  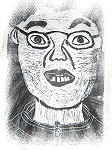   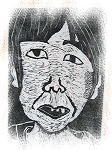 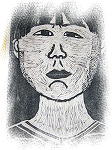  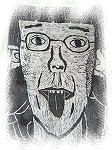 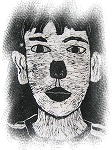 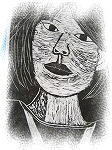 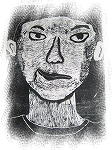 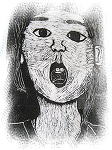  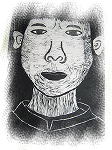 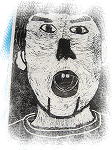  �@���R�N�����@�@�u�Ԋ}�����v�@  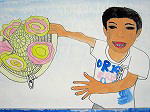 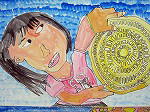       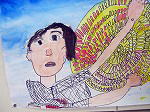 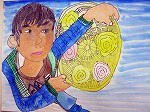    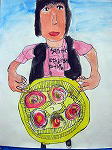  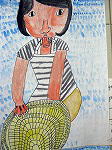 �@��2�N�����@�@�u�~�����l�v�@                       �@���P�N�����@�@�u�ӂ����Ȃ����ȁv�@                 �@           |
||||||
| �Q���S���i���j    �@�l�ƒn��Ƃ̏o��@�u�悤������y�v�@  �@�U�N���́C�P��22���i�j�ߌ�ɒn��o�g�̂R���̐�y�����Əo��@��������܂����B�n��Љ�Ŋ���{�Z�̑��Ɛ�����̕��������s���C�������ƁC���������Ƃ̑���𗝉�����ƂƂ��ɁC���I�ȋZ�p�E�Z�\�Ɋւ��鋻���E�S�����߁C�����Ɍ����Ď����̐������₠������l���邫�������Ƃ���w�K�����{���܂����B �@���b�����������R���̕��́C���삳��i��Y����_�C�J�X�g�H�Ɗ�����Ёj��C����i��C�H�i������Ёj�C�ߓ�����i�������������E�O�d�n��S���v���f���[�T�[�j�ł��B�����͂R�O���[�v�ɕʂ�C���ꂼ��̕��̂��b�����ԂɈړ����Ȃ��璮���Ă������@�Ŏ��{���܂����B�����āC�S�C�̐搶���͑��Ƃ��ԋ߂ɍT�����U�N���̎q�ǂ������Ɏ��̂悤�Ȏv���������āC���̊w�K�ɗՂ܂�܂����B �@�u���w�Z�i�w���T�����q�ǂ������͍��C�����v���Ă��邾�낤�B���R�Ƃ����`�ł��ꎩ���̏������v���`���Ă���q������C��̂��ƂȂǂ܂��l�����Ȃ��Ƃ����q�����邾�낤�B�S�z��s��������Ă���q�����邩������Ȃ��B���ʂ������Ƃ����̂́C���͑�l�ł��Ȃ��Ȃ�����B �@���C�n��Љ�Ŋ��Ă����l�������C���͊F�C���������������������͂��ł���B�����āC��̌��ʂ����͂�����Ƃ͎��ĂȂ��Ă��C���̎��X�̏o����ɂ��C��肪����������C�ڕW�������đO�����ɐi��ł����͂��ł���B�����ƌ��������Ȃ���P���P���i��ł������Ƃ̑�����C�g�߂Ȑl���̃��f���ƂȂ�u�t�̕��X�̎p���犴����点�����B �@�u�t�̕��X�́C�U�N���̍��ǂ�Ȏq�ǂ����������C���̎d���i�����j�Ƃǂ�Ȃӂ��ɏo��C�ǂ�Ȃ�肪���������Ď��g��ł������B���������Ƃ₤�܂������Ȃ����Ƃ��C�ǂ�ȕ��ɏ��z���Ă������B���͂ǂ�ȖڕW��v���������Ă��邩�c�B����Ȃ��b�����Ă����������ƂŁC�q�ǂ��������������g�̐�������݂�����l�����邫�������ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B�v  �@�s���삳��̂��b��q�ǂ������̎��₩��t �@�s���삳��̂��b��q�ǂ������̎��₩��t�E ���w�������C�^����̐���̕��ɓy�U�������āC���o�����Ă����v���o������B �E �Ⴂ�l�͑傫�ȉ�Ђɍs��������X�������邪�C������Ƃł���ό��C�Ŗ��͓I�ȉ�Ђ���������B �E �����n�߂���Ђ��w���ƌ�����p�����B���͑�莩���ԉ�Ђ̌y�����Ԃƒn��������Ƃ̘A�g�ŁC��蔖�����i�Â�����s���C�����Ă����i����ڎw���Ă���B �E �o�C�N�̃G���W���J�o�[���P����2,000�䐶�Y���Ă���B �E ���n�u���W���l�͎�̓����o�[�ŁC�i���Ǘ��ȂǏd�v�Ȗ��������Ă�����Ă���B�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł���B �E �l���ɂ͊�H�����邪�C���낢��ȍ������������蕥���C�����̏����̎p���v���`���Ăق����B �E �����̖���ڕW���B���ł���Ǝv���C������߂��ɂ���Ă����������ō��������Ǝv���Ă���B�w�͂𑱂��Đi��ł����Ăق����B  �@�s��C����̂��b��q�ǂ������̎��₩��t �@�s��C����̂��b��q�ǂ������̎��₩��t�E ���w�Z�U�N������25�܂ŋ������C�I��Ƃ��č��̂ɂ��o�ꂷ�邱�Ƃ��ł����B������߂����������Ă��ėǂ������B�ڕW�������ĕ����ɂ�����C�v�`�������d�˂Ă����Ăق����B �E ����̑�l��e����������T�|�[�g���Ă��ꂽ�������ŁC������߂��ɑ����邱�Ƃ��ł����B �E ���C�����������Ŏd�������Ă��邪�C�N���N�n�ɐ��_�{�̂��͂炢�����ł��������_���Ă����B�x�e������Ԃ��Ȃ������Ƃ��Ă������C�d���͂��q����ɂ�낱��ł��炤���߂ɁC�Љ�v���ł���悤�ɂ���̂ŁC�������ւ��Ă����v�ł����B �E �Ⴂ�]�ƈ������邪�C���炢�Ƃ����ɂ�����߂悤�Ƃ���B�������Ƃ�����h����������C������{���Ăق����B �E ������������1�{����R�N�ԂłT�`�U�L���̂������������n�ł���B �E ���������͔|���n�߂�O�͍L���㗝�X�T�N�Ԃɋ߂Ă������C�����̂����̂Ŗ߂��Ă��ĉƋƂ��p�����ƂɂȂ����B�݂Ȃ���������ς��̌o����ς�ł��������B �E �炢���Ƃ́C�ƋƂ��p�������Ȃ��Ȃ��H�ׂĂ������C�o�C�g�����Ȃ��炵�������͔|�𑱂��Ă����B���Ɍ��Ă���Ƃ����v���ł���Ă����B �E ���ꂵ���������Ƃ́C���q������������H�ׂĂ���āC�������������Ƃ����Ă��ꂽ���ƁB���́C�݂�ȁi�S�l�j�Ŏd�����ł���̂����ꂵ���B �E ����̐l�����������Ă����̂́C�����̂��Ƃ��������Ă���Ă��邩�炾����C�����Ă��ꂽ���Ƃ����肪�Ƃ��Ƃ����C�����Ŏ~�߂Ăق����B  �@�s�ߓ�����̂��b��q�ǂ������̎��₩��t �@�s�ߓ�����̂��b��q�ǂ������̎��₩��t�E �l����낱�Ԃ��ƁC�l�Ɛl���Ȃ����Â�����s���Ă���BI�@love �n��.�i�n������D���j�����b�g�[�ɁC���ݏE���C�����ł̉Ԍ��ȂǁC�݂�Ȃ��y���߂�ꏊ�Â���ɂ�����Ă���B �E �ߏ��̐l�Ƙb����Ƃ��āC���̃��W�I�̑����n�߂��B���N�Ԃ͈�l�ł���Ă������C���X�ɋߏ��̂������������Ă����悤�ɂȂ��āC��N1000����}�����B �E �l���s�����N���u�i�u�T�y�j���j���V������Q���ԍs���Ă���i�_���{�[�����ׂ�C�₫�����Â���Ȃǁj �E �O���[���o�[�h�Ƃ��āC�݂�Ȃł��|���i��R���j���C�ɍ�_���E�X�������j���s���Ă���B �E �������������E�O�d�Ƃ��āC���悭�������v���ŁC���������̐l�̉�����Ȃ������s���Ă���B �E ��w���ƌ�͉c�Ƃ����Ă������C�R�N�O�ɂ�߁C���Â���̎d�����n�߂��B�����̂��߂Ɏd��������Ă���B�l����낱�Ԏp���݂āC���������ꂵ���Ȃ��āC�����̐��܂ꂽ�����݂āC���n�߂��B �E �e�[�}�́u���邳�ƏΊ�v�B�����̍D���Ȃ��Ƃ͂��Ƃ��炭�Ă�������B�݂�Ȃ����ꂵ���Ȃ�邱�Ƃ���ł������Ă��������ȁB �E �ŏ��͏��Ȃ��Ă��C�Q�������l���F�����i�Ƒ��C��Ђ̐l�j���Ă�ł��Ă����B�l�̗ւ��L����Ƃ����Ƃ����Ɗy�����Ȃ�B �R���̕��̂��b�͖{���ɋ����[���������C�U�N���̎q�ǂ������ɍ��܂ł̐l����w�ю�������Ƃ���̃��b�Z�[�W���ꐶ�����ɓ`���Ă��������܂����B�U�N���݂̂Ȃ���̂��̊w�K�͂܂��܂������܂����C�o�����w��C�������肵�����Ƃ��݂�Ȃňӌ��������Ȃ���C�����̂��ꂩ��̏����ɂȂ��Ă��������B  �@�ܔN���u�O�������t�ƃ��[�N�V���b�v�v �@�ܔN���u�O�������t�ƃ��[�N�V���b�v�v�ߔN�A���y�̎��Ƃɂ����ē��{�̓`�����y��a�y��ɐe���ނ��Ƃ��d������Ă��Ă��܂��B�����ŁC�V�������g�݂Ƃ��ĂP��24���i�j��25���i���j�ɍ��N����n��̘a�y��̖��l�������āC�T�N�����u�a�y��̉��t�Ɛe���ރ��[�N�V���b�v�v���s���܂����B�������������͎O�����̍�F������ł��B �@�͂��߂ɎO�d���Ƃ䂩��̂���ɐ������C���h�߂�Ȃ��݂̂���Y�B�߂Ȃǂ����t���Ă��������܂����B�O�����͎q�ǂ������ɂ͂Ȃ��݂̂Ȃ��a�y��ł����C��ς킩��₷���O�����̓�����������Ă���܂����B�e�����ɂ́u�͂˂�v�u�X���[�v�u�����w�ł͂˂�v�Ȃǂ����邱�Ƃ����Ă�������C�Ȃ̃C���[�W�̂�������������邱�Ƃ��ł��܂����B���̔�͔L�⌢��C��͎O�����̂����Ƃ��厖�ȂƂ���Ō��̉����ɓ`����������ʂ����Ă��邱�ƁC�p���𐳂����ۂ��̂ƎO�����̓��̊Ԃ��Ēe�����ƂȂǂǂ�������ÁX�ł����B �@�㔼�ł́C�O�������t�ōZ�́C���C�~�i�F�C�ƂȂ�̃g�g���Ȃǂ��݂�ȂŊy���݂Ȃ���̂��܂����B�����čŌ�ɂ́C��l�ЂƂ肪���ۂɒe���Ă݂�Ƃ����̌����s���܂����B��ς������F���o���Ă���q�������肵�āC���Ԃ�����Ȃ��قǂł����B�Q�g�ɂ͒Ìy�����O�������K���Ă��鎙�������āC���̎q�ɂ�����e���Ă��炢�C�y���݂܂����B���܂�̎w�E�o�`�����ɋ����C�Ȃ̋���݂̂��Ƃ��ɔ��芅�тł����B �@���w�������������܂����₳��ɂ����\���グ�܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���N�x�ւƂȂ��Ă��������Ǝv���܂��B  �@ �@ �@ �@ �@          |
||||||
�P��24���i�j    �c�t���E�ۈ牀�̔N���������}���Ă̌𗬉� �@�P��18���i���j�C����c�t���̉���25���Ɖ��쒆���ۈ牀�̉���19�����}���āC�P�N���Ƃ̌𗬉������܂����B�v��ł͉���ۈ牀�̎q���������҂��ĎO���Ƃ̌𗬂�����\�肾�����̂ł����C����ۈ牀�ŃC���t���G���U�����s���Ă��āC���x�݂����Ă���q�������Ƃ������ƂœƂ̌𗬂ƂȂ�܂����B �@�P�g�ƂQ�g�ɂ��ꂼ�ꕪ����Č𗬉�X�^�[�g�B�܂��̓y�b�g�{�g���L���b�v�Â���ł��B�y�b�g�{�g���̂ӂ��Ɏ��S�y�Ƃǂ�Ȃǂ��g���ď���t�������Ă����܂��B�P�N���͎����̕������炩���ߍ���Ă���̂ŁC�����͉����݂̂�Ȃւ̐搶���ł��B�u��������Ă��������B�v�u�ǂ���̍ޗ����g���H�v�Ƙb�������Ȃ���C��i�������[�h���Ă����܂��B15���قnjo�Ƒf�G�ȃy�b�g�{�g���L���b�v���o���オ��܂����B�r���C�g�C���ɍs�������q���ē�������C��Еt���₻��������ۂ悭������ƁC���h�Ȃ��Z����C���o����Ԃ�ł��B10�����O�C���w��������̍��͈�ЂƂw��������Ȃ��ƍs���ł��Ȃ��q���������܂������C��N���炸�̂����ɂ���Ȃɐ��������Ȃ��ƁC���Ă��Ă��ꂵ���Ȃ�܂����B �@�����ẮC����̃J���^���g���ẴJ���^�Ƃ�ł��B�����ł��P�N���͓ǂݎD�S���ł��B��l�������ɎD����������Ȃǂ́C�u����ȁB�v�Ɛ��������Ă��܂����B �@�X�ɁC���ɕ�����āC�܂莆�̎藠���𓊂��ă|�C���g�������u����肯��Q�[���v�ƁC���p�b�N�ɓ��ꂽ�ǂ��U���ē_�����o���u�ǂ�p�b�N�Q�[���v�����Ċy����C�u���肪�Ƃ��������܂����B�v�u�ǂ��������܂��āB�܂����Ă��������B�v�Ƃ����������킵�Č𗬉�͏I���܂����B�����R�ł����Ƃ����Ԃ̂P���Ԃł����B�P�N���Ɋ��z�����Ƃ���u��ꂽ�[�B�v�Ƃ̐�������܂������C�������Ȋ�Łu�v���Ă������y���������B�v�u�����Ɖ��̎q�����ɋ����Ă������Ă悩�����B�v�Ƙb���Ă����q���������܂����B �@���͂Q��19���i�j�ɍĂюO���݂̂Ȃ���ɗ��Ă��������C�̌����w�Ƃ��Ċw�Z�̊w�K����̗l�q���݂Ă��������܂��B �u���H�L�O���v���Ēm���Ă��܂��� �@����22�N(1889�N)�ɎR�`���߉����i���߉��s�j�̎����������w�Z�ɂ����āC���ٓ��������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��q�ǂ������̂��߂ɁC���ɂ���ƏĂ����C�Е��Ƃ������������̒��H���o�����̂��C�w�Z���H�̎n�܂�Ƃ���Ă��܂��B �푈�i����E���j�̂��߂ɐH�ƕs���ƂȂ苋�H�͒��~����܂����i���a18�N���j�B �@���a20�N�C�푈���I���������̓��{�ɂ͈炿����̎q�ǂ������ɏ\���H�ׂ����邾���̐H�ו�������܂���ł����B�����ŁC���{�̎q�ǂ������������悤�ƃ����E�A�W�A�~���A���i���Q�Ɓj���~�������������C���a21�N12��24���Ɋw�Z���H���Ăюn�܂�܂����B���̓����w�Z���H���ӂ̓��ƒ�߂܂������C��������~�x�݂ƂȂ邽�߁C1�������1��24�������H�L�O���Ƃ��܂����B���̋L�O���̂���1�T�Ԃ��u�w�Z���H�L�O�T�ԁv�Ƃ��đS���I�ɗl�X�Ȏ��g�݂��s���Ă��܂��B �@�l���s�s�ł́u���H�L�O���i1���Q�S���j�v�̂���1��24���`�R�O�����u���H�T�ԃ��j���[�v�Ƃ��āC���{�S���́s���y�����t��s�����n���j���[�t��������Ă܂��B �y���z���������Ƃ́C����(LARA�GLicensed Agencies for Relief in Asia�F�A�W�A�~�����F�c��)�̒��Ă������{�����̉��������̂��ƁB�����̓A�����J���O���~�ϓ����ψ��1946�N6���ɐݒu��F�������n�č��l�̓��{���������c�́B �@  �@���H���o���オ��܂� �@���H���o���オ��܂��@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�`�����������1�����Љ�܂��` �l���s�s�ł́u���S�C���S�C��Â���v��厖�ɂ��āC���w�Z�̎q�ǂ������ɂ����������H����Ă��܂��B�H�ނ͏{�̂��̂�������C�ł������n���Y�̂��̂ŁC���_���Ȃǂ��g���Ă��܂��B�����͎肬��C��2��̒n����Ԃ��s���C�Ă͎l���s�Y�u�݂��̂��݁v���g�p���Ă��܂��B���̂悤�ɏ�Ɏq�ǂ������̔���ɂƂ��čł��ǂ���Ԃŋ��H������Ă��܂��B ����ł́C���������̋��H���ǂ̂悤�ɍ���邩���Љ�܂��B���쏬�w�Z�ł́C��450�H���Q�l�̒���������ƂR�l�̒����⏕���̂T���̕�������Ă���Ă��܂��B �s1��16���i���j�̋��H��ȃ��j���[�F�J���[���C�X�C�C�����T���_�t �s��ƑO�̏����t�@���O�Ȏ�B���̉��f�Z�x�C�Ⓚ�E�①�̉��x�C�������̉��x�E���x�̊m�F�B���̎����̃A���R�[�����ŁB 7�F55�@�������͂��B�i�����C�n���C�`�[�Y�C�O���[���s�[�X�C�R�[���C���_�Ёj�����E�n���͗e��ɓ���C��ؗp�①�ɂցB�`�[�Y�E���_�Ђ́C�r�j�[���܂����f�Ő@���C�ۗ�ɂցB���ޗ��T���v���̗Ⓚ��2�T�ԕۑ��B 8�F00�@��͑O�������i1��ρj�B���̖�i���܂˂��C�L���x�c�C�j���W���C�W���K�C���j��n�߂�B����������1��C��������2�������B 8�F45�@���N�`�F�b�N�B���ɐ������ڂ��Ȃ��悤 �@�ɋC�����C����n�߂�B �@�@�@�@���S�������f�Ő@���B 9�F00�@�Ĕт��͂��B�G�v������t�ւ��C�ۉ��ɂ̊O�����f�Ő@���B��Ƃ��ƂɎ���s���B 10�F00�@��ؐ��C��Ƒł����킹�i��Ǝ菇�i���x�m�F�C�A�����M�[�m�F�C�q���ʎ����ǂݏグ�m�F�j�B�����m�F�B 10�F15�@�������͂��B���E���ԁE���x�C�ܖ��������m�F�����B���̌�C�r�j�[���P�[�X�̊O�C�o�������f�ň���@���B�N���X���Ƃɕ����C�ۗ�ɂցB 10�F30�@���S���Z�b�g�i�H��̐��m�F�B�p��̃Z�b�g�B�j �@�@�@�@�n���������i75���P���ԁj�B���̌�C��܂��B 11�F00�@�L���x�c����ł�B���i���f�Z�x�C�����m�F�C�L�^�j��������܂��B���̌��ł��ڂ�B���l�ɃR�[������ł�B�C�����~�b�N�X�𐅂ł��ǂ��B �@�@�@�@�劘�ŋ������u�߁C�j���W���E���܂˂����u�߁C�������ς�B 11�F30�@�W���K�C�������C�ς�����C�������E�J���[���[������B�d�グ���̉��x�m�F�B���_�ЊJ���C�z�H�B �@�@�@�@�ۑ��H���Ƃ�C�Ⓚ�ɂłQ�T�ԕۑ��B 11�F50�@�z�H�i�N���X���ƂɐH�ʂɁj�B�C�����T���_��������B�d�グ�̉��x���m�F���C�L�^��C�z�H�B 12�F10�@���S�����e�K�ɔz���i2�l�j�B��̎҂� ���̂�����B�������E�z�V���̑|�� �Ȃǂ̑|���B 12�F45�@�ߑO�̍�ƏI���B 13�F30�@���S������B�H��C�H�ʁC�c�Ȃǂ̕Ђ� �@�@�@�@���Ɛ��B 13�F50�@��؎��i���E��ނ��m�F�C�L�^�j�C1������C�U���ɓ���C�①�ɂցB �@�@�@�@���S����@���i�T2����j�B�ӂ���E�X�|���W�Ȃǂ̐��Ə��ŁB �@��́C���ނ̋L���Ɩ����̑ł����킹���s���C1�����I���܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@���̂悤�ɂ��āC�o���オ�������H���e�����ɓ͂����܂��B��ƍH�������Ă�������̂悤�ɁC��ɉ��x�𑪂�C�}���ۗ���s���C�G�v��������Ƃ��Ƃɑւ��C�אS�̉q���Ǘ����Ȃ���Ă��܂��B�ƂĂ������������H������Ă��������Ă��钲�����̊F����ɉ��߂Ă�����q�ׂ����Ǝv���܂��B �@           |
||||||
12��10���i���j    �݂�Ȃŗ����S�����킹�����R���� 11��27���i�j�C28���i���j��2���Ԃɂ킽��C5�N���͎l���s�s���N���R�̉ƂŎ��R�������s���܂����B1���ڂ͓V��Ɍb�܂ꂸ�C���J���~������~��̓V��ŗ\���ύX���Ȃ�����{���܂����B 8�F30�ɏo�������s���C�o�X�ŏo�����܂����B���R�̉Ƃ�9�F30�ɂ͓������C�ӂꂠ���̍L��œ��������s���܂����B�Z�̂��̂��Ȃ���C�f�g��̃|�[���ɍZ����g���C���R�̉Ƃ̐E���̕�����u���[�������C���R���\���Ɋ��\���Ă��������v�Ƃ������t�����������C���R�������X�^�[�g���܂����B �s�Ă����̌��t �@�ߌ�̗\��ł������C�V��̓s���ŁC�ߑO�ɍs���܂����B�����o�[�i�[�ŏĂ�������o�[�i�[�̈����������R�̉Ƃ̐E���̕��Ɏw�����āC�q�ǂ������͎����̏Ă����ɂ�������āC���ɏĂ��グ�Ă��܂����B������Ő����C�Ƃ��玝���Ă����̎��⏼�ڂ�����C���ジ���܁C�������Ȃǂ��z�b�g�{���h�ł��āC���������܂����B�͍삼�낢�ł�����i���ł�������܂����B    �s�I���G���e�[�����O�t �@�J���~�ނ̂�҂��āC�ߌ�2������X�^�[�g���܂����B�Ǎs���ł̂ӂꂠ���̐X�̃|�C���g�����߂Ă̒T���ł������C���͂��Ȃ���C�ǂ��������ł��Ă����悤�Ɋ����܂����B �s�H���ł̗[�H�t �H���W�肪�搶�̎w�����āC�Ă��ς��Ɛ���t�������Ă��ꂽ�������ŁC�����������ς݁C�H�����݂�Ȃł��̂����H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�c���q���قƂ�ǂ����C�����납��̎w���ƈ�l�ЂƂ�̈ӎ��Â��肪�ł��Ă���悤�Ɋ����܂����B    �s�L�����h���T�[�r�X�Ɛ����̂��b�t �@�V��̊W�ő̈�قł̃L�����h���T�[�r�X�ɐ�ւ��܂����B�傫�ȃt�@�C���[���͂�ł̂��Ƃ͂ł��܂���ł������C�����������̂ŁC�������h���C��ϐ���オ�������Ԃ��������܂����B�u����܂���v�u������ԁv�Ȃǂ��Q�[���W��̎i��̂��ƍs���C�Q�[���̍Ō�ɂ͗ѐ搶�̃��[�h�Łu�ҏb���v���s���܂����B�݂�Ȗ{���Ɋy���݁C�傫�Ȑ��ƊJ�����ꂽ���͋C���Y���Ă��܂����B���̌�_���X���s���C�Z�����j�[�t�@�C���[�Ɉڂ�܂����B�����ł͈�l�ЂƂ�̃L�����h���ɉ��C5�N���̑�\����̊��ӂ̌��t���q�ׁC�����݂�Ȃ���ɂȂ�C�Ȃ��肠�����ЂƎ��̖�����܂����B �@��2���Ƃ��āC�����w�K�Z���^�[�̐��J����ɂ�鐯���̘b���s���܂����B�܂肵��11��28����23�������炢�ɂ͔��e���H���n�܂�Ƃ����̂ŁC�̈�ق���_�̐�Ԃ��猩���B�ꂵ���������Ȃ���C�u���̊w�K�v���s���܂����B���͂ǂ̂悤�ɂł����̂��C���͖��N�n������ǂ̂��炢����Ă����Ă��邩�C�����n�����痣���Ƃǂ��Ȃ邩�ȂǁC���낢��l���Ȃ���C�n���ƌ��̊W��m��ǂ��@����Ă܂����B    �s2���ځ|���̏o�n�C�L���O�t �@2���ڂ͍ō��̓��ƂȂ�܂����B5�F50���ɋN�����C6�F20���ɂ͓W�]���ڎw���܂����B�܂��Â����̏o���ł������C���X�ɂ������邭�Ȃ��Ă��āC6�F38�����炢�̓��̏o��҂��܂����B���F�ɐ��܂�_�C�l���s�`�ƃR���r�i�[�g�̉��˂Ɖ��C�l���s�̒����݂��ቺ�Ɍ����낵�Ȃ���C�������Ƃ������ԂƂȂ��܂Ɖ߂�����Ԃ��y���݂܂����B���ݐ�����C�̒��̓��̏o�͍ō��ɂ��炵�������ł��B    �s�J���[�Â���Ɣт���������t �@���O�̌��̘r�������Ԃ�����Ƃ���Ă��܂����B���܂njW��C�J���[�W��C���ьW��ɕ�����Ă��ꂼ�ꂪ�Ă��ς��ƍs���܂����B���������̂ɋ�J������C���т��������Ȃ������v���낤���C���M���ĂȂׂ��Ȃ��Ȃ������������Ȃ��ȂǁC���ꂼ��ɋ�J���Ă��܂������C�Ō�ɂ͂��������J���[���C�X�ɘb���e��ł��܂����B��������d���Ă����������ō�������͍̂ō��ɂ��܂����̂ł��B    �@�ޏ������I���C�w�Z�Ɍ������܂����B����2���Ԃ�U��Ԃ�C���ꂼ��̂��q����͂������ʼn���`����ꂽ�ł��傤���B5�N���̎q�ǂ�������5���O�s���C�����̖������ʂ������ƁC��������i��ł�邱�ƂȂǁC�{���ɂ悭��������Ǝv���܂��B�Ȃɂ�肤�ꂵ���v�����̂́C�Lj��̂��Ƃ�ꏏ�ɂ��������Ƃ�厖�ɂ��Ȃ���C���₩�ł���₩�ȋC�����ƂȂ�����悭�����邱�Ƃ��ł��܂����B�����ȉۑ�͂���܂����C3���܂ł�5�N���̐搶�����ƈꏏ�ɏ��z���Ă������Ƃ��肢�܂��B5�N����l�ЂƂ肪�{���ɂ悭����������Ƃɑ傫�Ȕ���肽���Ǝv���܂��B  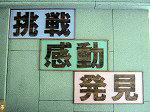   �����̋����ɂ�鍇�����Ƃ��s���܂��� �����̋����ɂ�鍇�����Ƃ��s���܂����w�Z�����w�Z�R�C�A�̎��x18���ł����m�点���܂������C�w�т̈�̉��̎��g�݂̈�Ƃ��āC11��30���i���j��1�E2���C���������w�Z�̐��W�搶�ɁC�U�N���̒S�C�Ƃ̂s�D�s�ŗ��Ȃ̎��Ƃ��s���Ă��������܂����B ���e�́w���̌������̈Ⴂ�x�B�U�N���̎q�ǂ��B�ɂƂ��Ă��C����w�K���I��������̒P���ł��邱�Ƃ���L���ɂ��V�����C���Ҋ����\��ɕ\��Ă��܂��B��������̌��̉摜���v���W�F�N�^�[�Ō����Ȃ���C�u�E�T�M�̖݂��v�u���̐l�̉���v�u�{��ǂޏ��̐l�v�Ȃnj��̌������̘b������Ƃ͎n�܂�܂����B�����Č��ʂ̒n���̘b���o�Č��̖��������ւƘb�͕ς��C11��14���ɃI�[�X�g�����A�ŎB�e���ꂽ�F�����H�̎ʐ^�����Ȃ���b�́u�Ȃ����̌������͕ς���Ă����̂��v�ցB�d���z�C�싅�̃{�[�������Ɍ����āC�n���V���g���Ă��ꂼ��̈ʒu�W��������Ă����܂��B���搶�͈ȑO�l���s�s�������قŋΖ����C��啪�삪�V���Ƃ������ƂŐ������I�m�ŁC�q�ǂ��B�������ÁX�ł����B�^�Ɍ����J�����{�[�h��p�ӂ��C����������r�f�I�J������`�����ĉ��Ɍ�����s���|���ʂ̌��̌`���m�F������C���搶���g���B�e�������ʂ̃N���[�^�[�̉摜��������ƁC���o�ɑi���Ȃ���̎��Ƃ͍Ō�܂Ŏq�ǂ��B��O�������܂���ł����B ���ƌ�̎q�ǂ��B����́u���w�Z�̗��Ȃ̐搶����������C���̌������Ȃǂ킩��₷���������Ă��炦�Ă悩�����B�v�u�{�[�h��f���ȂǐF�X�Ȃ��̂��g���Đ������Ă��ꂽ�̂ŁC�悭�킩�����B�v�Ȃǂ̐��������ꂽ�ق��C�u�p�������������̂Ŏ���ł��Ȃ��������ǁC�F���ɐ����͂���̂��������������B�v�Ƃ����悤�ɉF���ɑ��ċ����E�S���[�܂����q�������悤�ł��B 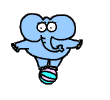 ���w���̐E��̌����I���� ���w���̐E��̌����I�����@���������w�Z��2�N��9�����C11��28���i���j�`30�i���j��3���Ԃ�{�Z�ŐE��̌����s���܂����B�q�ǂ������͒��w�Z�̂��o����C���Z����ɗ��Ă��炢�C�Ƃ��Ă����ł��܂����B �u���̂��CS����Ɂw�ւ��܂̂ց[����[�x��ǂ�ł�����āC�E�E�E�����ȏ��̎q�̂��ꂳ�� �u�����˂��C���イ��ˁ[�B�v �ƌ������Ƃ��낪�������납�����ł��B�܂��C�������{��ǂ�łق����ł��B�ǂݕ������傤���ł����B�E�E�E�E�v ���̂悤�Ȋ��z��3�N���̎q�������Ă��܂����B �s���w2�N���̐E�Ƒ̌��̊��z�t �� ����3���ԂŁu�������v�͂�͂�ƂĂ�����Ǝv���܂����B���������ڂ��ڂ��ƌ����Ă���悤�ł͐搶���Ɏ���Ȃ̂ŁC�������͑傫���C�Ԏ��͂͂��͂��Ƃ������������Ƃ������Ƃ��킩��܂����B �l��������2�N2�g�ł́C�������E�Ԏ����傫�Ȑ��ł͂��͂��Ƙb����q�����������̂ŁC�ƂĂ������܂����B���Ƃ���������Â��ɎĂ����̂ŁC����ɋ����܂����B�Ƃɂ���1���ڂ͋����̘A���ł����B �� 1�N1�g�ɓ������Ƃ��ɁC�u�����Ȋ��v�u�Ђ����炢�̃C�X�v�u���F���J�o�[�����������傫�ȃ����h�Z���v�ȂǂƁC1�N���ɖ߂����C���ł����B�����āC������������C�u�N�H�v�u���H���w���H�v�Ƃ݂�Ȃт����肵���悤�ł����B 1���ڂ̗V�ё̌��ł́C�o�ˌ����ɍs���܂����B�݂�Ȃ��������C�ő����đ����đ���܂����āC�����p���p���ɂȂ�܂����B�v���Ԃ�̋��H���������������������ł��B�E�E�B���͂��ꂩ����ꐶ���������āC���h�Ȑ搶�ɂȂ�܂��B �� ���͐l�Ƙb���̂����Ȃ̂ŁC�ŏ��̓��̓o�Z���ɂ����Ǝ�����搶�Ƙb���邾�낤���ƂƂĂ��S�z���Ă��܂����B���������̃N���X�ɓ����Ă݂�ƁC�݂�ȂƂĂ����ꂵ�����ɂ��Ă���āC���ꂵ�������ł��B�ŏ��̋x�ݎ��ԁC����3�l�̒j�q���悭�b�������Ă���āC���ْ̋������ق����Ă��ꂽ�̂ŁC��������ꂵ�������ł��B���ƒ��ɕ����āC�݂�Ȃ������ƃm�[�g�������Ă��邩�m�F���Ăق����ƌ����Č����̂��C�ŏ��͂ƂĂ��߈���������܂������C���̂������͊w�Z�̐��k�Ƃ��Ăł͂Ȃ��C���K���Ƃ��Ă��Ă���̂��ƁC�^�̈Ӗ��ŋC�Â��āC���ƒ��ɕ����Ȃ��炵������Ƃ݂�Ȃ������Ă���̂��m�F�ł��܂����B �� �ŏ��̓��ɐ搶���珗�̎q���O�ւ��܂�s���Ȃ��ƕ����āC���͂Ђ����ɖڕW�����ĂĂ��܂����B���͏��w�Z�̂Ƃ��ɊO�ł����V��ł����̂ŁC���̎q�����ɂ��O�ŗV�Ԋy������m���Ăق��������̂ŁC�ŏI���܂łɃN���X�S�����O�ɘA��čs���Ĉꏏ�ɗV�ԂƂ����ڕW�𗧂Ă܂����B2���ڂ܂ł͒B�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������ǁC3���ڂ͒B�����邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��B �Ō�݂͂�Ȃ��炶�������ď������l���爬������ċA���Ă������ƂɂȂ��Ă����̂ŁC�Ō�ɂ݂�Ȃ���u���肪�Ƃ��v�u���݂����v�Ƃ����Ă��炦�Ă��������ꂵ�������ł��B 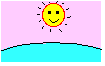 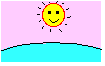 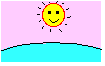 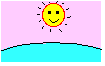 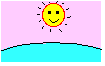 |
||||||
11��26���i���j �@�c�ۏ����A�g�u�w�т̈�̉������g���v �l���s�s����ψ���ł́C�u�w�т̈�̉��v�̐��i�ɂ��u���Ɖ��P�Ƌ����̈ӎ����v��i�߂邽�߂ɁC�A�w�O�E�����w�Z�̘A�g���������C��ѐ��E�n�����̂��鋳��̐��i�v��}���Ă��܂��B���������w�Z��̗c�ۏ����ł��C�u�w�т̈�̉��v�̗��O�ɑ���C�ȉ��̂R�̎��g�݂𒆐S�ɐi�߂Ă��܂��B 1. ���J���Ƃ�ʂ����c�ۏ����̘A�g�̋����Ǝ��Ɖ��P�̐��i 2. �c�ۏ����̗c���E�����E���k���Ƃ��ɏW���C�Ȃ��肠�����������̐��i 3. �����w�Z�̋����̑��ݏ�������Ɠ��ɂ��𗬎w���̎��{ �s�𗬉��y�W��t �@11���X���i���j�ߌ�C����c�t���C���쒆���ۈ牀�C����ۈ牀�̔N���݂̂Ȃ���C���쏬�w�Z�S�Z�����C���������w�Z�R�N�����k���C�{�Z�̑̈�قɏW�܂�C�����̌𗬉��y�W����s���܂����B �@�W��̎n�܂�́C�u�ɂ��v�Ƃ����Ȃ��݂�Ȃʼn̂��܂����B�w���͖{�Z�̂U�N���̑�\�����߁C���X�Ƃ����f�G�Ȏw���ł����B�S�Ղ�A�R�[�f�B�I���ł��U�N�������t�߂܂����B������͂��ꂼ��̔��\�Ɉڂ�܂����B�ŏ��͂R�c�ۉ��݂̂Ȃ���̔��\�ł����B�u�ǂ肱�낱��v�u���E���̂��ǂ��������v���̂��܂����B�R���̎q�ǂ������͖{���Ɍ��C�Ɋy�����̐���͂��Ă���܂����B���͉��쏬�w�Z�̂S�N���ł����B�S�N���͎O���n�揬�w�Z���y��ɏo�ꂷ��̂ŁC�ď��u���͍��v�ƍ��t�u�R�U�T���̃}�[�`�v�\���܂����B�ď��͑�ϔ��������ł���₩�ȋC������͂��Ă���܂����B���t����ς悭���K������Ă��Ă܂Ƃ܂��Ă��Ă������F��������Ă��܂����B�Ō�͂��悢�搼�������w�Z�̂R�N���݂̂Ȃ���̍����ł����B120�����̂R�N�������䂢���ς��ɐ��C��ϖ��͓I�ȍ�����͂��Ă���܂����B�u���������w�Z�Z�́v�u�M����v�ȂǂR�Ȃł������C�ǂ̍��������炵�����|����܂����B���ɒj�q���k�̐��������C�����݂܂����B���̂悤�ɂT����15�܂ł̎q�ǂ��������̂łȂ��肠���𗬂̋@������Ă����Ƃ͂ƂĂ����炵���C�c���͏��w�����C���w���͒��w�������ꂼ��̖ڕW�Ƃ��ĂƂ炦�����Ƃł��傤�B �@11�����{�ɂ͒��w�Z�̐E�Ƒ̌����R���Ԃ���C���쏬�w�Z�ɂ�10�l�̂Q�N�����E�Ƒ̌����s���܂��B12���V���i���j�ɂ͐��������w�Z�̂P�N���Ɣ��������w�Z�Ɖ��쏬�w�Z�̂U�N�������������w�Z�ɏW���C�u�q�ǂ��l���t�H�[�����v���J�Â��܂��B�܂��C���̂Ƃ��̗l�q�����Љ�����Ǝv���܂��B �s�w�т̈�̉����ƌ��J�t ���N�́C���������w�Z�����J���Ƃ��s���܂����B11��13���i�j�̂U���ڂ̎��Ƃ�c�ۏ����̋��E�����Q�ς��܂����B�����āC���̌�C�𗬂�ӌ��������s���܂����B�܂��C�W���ɂ͒��w�Z��̑S���E�����W�܂�C�l������ɂ��Ċw�ԋ@��������܂����B ���w�Z��ł͒n��̎q�ǂ����Ƃ��Ɉ�Ă邽�߂ɁC�u����w�сC����l����q�̈琬�v���e�[�}�Ɍf���C�u�w�э������ƁC�������E�Ȃ��肠���ۈ�v�Ɓu��b��{�̒蒅�v�𒌂Ɍ݂��̘A�g�ƌ��C��i�߂Ă��܂��B�{�Z�ł��u�Ȃ��荇���C�w�э����q�ǂ��̈琬�v���߂����Ď��Ɖ��P���Ɏ��g��ł��܂����C���̂��Ƃ��O����15�܂ł̒n��̎q�ǂ�������A����������̂Ȃ��Ŋw�т��͂����݁C�炿�̎x�������Ă������ƂɂȂ��邱�Ƃ��߂����Ă��܂��B �s�����w�Z�̋����̑��ݏ�������Ɓt �@�{�N�x�͒��w�Z�̗��Ȃ̋��������w�Z�ɗ��Ă��������C�u���̌������̈Ⴂ�i���������j�̎��Ɓv�����w�Z�̋����ƂƂ���TT�ōs���܂��B�{�Z��11��30���i���j�Ɏ��{���܂��B��������Ƃ̂悳�͒��w�Z�̋����̐�含�������������Ƃ����w�Z�ł��W�J����邱�ƂƁC���w�Z�̋����Ɗw�K�̏�Ō𗬂����Ă邱�ƂȂǂ�����ƍl�����܂��B �@�u�w�т̈�̉��v�̎��g�݂͓r�ɂ�������ł����C�c�ۏ����̋��E����ۈ�m���S���C�n��̎q�ǂ����������ꂼ��̗�����āC�w�тƈ炿�̘A�������@���ɓw�͂��d�˂Ă��������ƍl���Ă��܂��B �@���ː����Ƃ��s���܂��� �@10��30���i�j5�E6���ڂɁC6�N���͎O�d��w�����������āC���ː��ɂ������w�K���s���܂����B�܂��C����ꋳ�E����11��19���i���j�ɖ��É���w���_�������}���āC���C��������܂����B�������̌��q�͔��d���̎��̈ȗ��C���˔\�ɂ��Ď��ɂ��邱�Ƃ�L����ڂɂ��邱�Ƃ���������܂����B����́C�u���ː����ĂȂ낤�H�v�C�u���ː��͂ǂ̂悤�Ɏg���Ă���̂��v�C�u���ː����o�����̂��āC�Ȃ낤�H�v�C�u���ː��͂ǂ�����đ���́H�v�ȂǁC���܂ł��܂�l���Ȃ��������Ƃ�m��Ȃ��������ƁC���ː������ۂɑ��邱�Ƃ�ʂ��āC���ː��ɂ�������đS�̓I�Ɋw�ׂ����Ƃ͑�ϗL�Ӌ`�ł������ƍl���܂��B �E �������́C�F���C�n�ʁC��C�C�H�ו��Ȃǂ̎��R�E�����ɕ��ː����Ă��邱�ƁB �E ���ː����g���āC�����ď�v�ȃS�����������C�a�@�Ŏg���Ă��钍�ˊ�Ȃǂ��ۂ̂��ĂȂ����ꂢ�Ȃ��̂ɂ����肷�铭�������邱�ƁB �E ���ː����l�ɗ^����e�����l����Ƃ��́C���ː��ʂ�m�邱�Ƃ���ł��邱�ƁB �E ���ː��ɂ��e����\���P�ʂƂ��ăV�[�x���g��p���邱�ƁB �E �w�Z���̕��ː��𑪂�Ƃ��낢��ȏꏊ�ŕ��ː��ʂ��Ⴄ���ƁB �E ���̂��N�������Ƃ��ɁC���ː���������g������Ƃ́H ���b�������ʂ��āC���낢��ƒm�邱�Ƃ��ł��܂����B����̊w�K�⌤�C�͂��ꂩ��̎������̐�����ЊQ����g����邱�Ƃɖ𗧂ĂĂ��������ƍl���Ă��܂��B�������m����g�ɂ��C���������f�ƓK�ȍs�����������厖���Ǝv���܂��B �@          |
||||||
10��29���i���j    �C�w���s�����w���� �@10��22���i���j�C23���i�j�ƁC�U�N���͋��s�E�_�˂̏C�w���s�ɍs���Ă��܂����B �s�P���ځ@���s�t �@���V���ɑS�������C�Ȋ�ŏW�����܂����B���s�ψ��i��̏o�����ŁC�w�N�s���ڕW�Ƃ��Čf�����u�݂�Ȃ͈�l�̂��߂Ɂ@��l�݂͂�Ȃ̂��߂ɁI�v���m�F���C���̖ڕW�ɏ����ł��߂Â��悤�ɐS�|���C����̂��Ƃ��v�����C�����ōl���C�����Ŕ��f���C�[�������Q���Ԃ��߂������Ƃ̂��b�����C�o�����܂����B �@���s�̗��͐��E��Y���߂�����̂ł����B�ŏ��͍��N�ɂł������s�����ق�K�ˁC�I�I�T���V���E�E�I�C�吅���̊C�̋��C���{�̐싛�ȂǁC�����͂�������܂����B�r���ŃC���J�V���[�������̂ł����C��l���̒�����{�Z�̎�������l�I��C�C���J�Ƀ^�b�`����h�_�����܂����B�ŏ��͂Ȃ��Ȃ����܂���������Ȃ������ł����C�Ō�ɂ͂��܂������C�݂�Ȃ���傫�Ȕ�������炢�܂����B �@���H��C�����C���t���C�������Ƃ߂���܂����B�����͂�͂���̏��ɋ���������悤�ł����B���t���ł͋t�����t�����ꂢ�ɉf���o���ꂽ���Βr�̑O�Ŕǂ��Ƃ̎ʐ^���Ƃ�܂����B�������ł͕��䂩��̒��߂��y����ł��܂����B���̌�͂��y���݂̂��������^�C���Ŕǂ��Ƃɂ܂Ƃ܂����s�����ł��Ă��܂����B �@���قł͂�����Ɏq�ǂ������̐S���J�����ꂽ�̂��g�����v��������C�������s���������肵�Ċy�����i���Ă���悤�ł����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �s2���ځ@�_�ˁt �@���̓��͂����ɂ��̉J�ł������C���ق��W���ɏo�����C�_�˃|�[�g�^���[��15���x��Œ����܂����B���Ԃ��Ȃ���}���̃^���[���w�ł������C���{�ŏ��߂ă��C�g�A�b�v����C�p�C�v�\���̃^���[����̐_�˂̒���C�͑�ϔ������C���̍�_��k�Ђ̎S�����o�����������܂���ł����B�����`�̈�p�ɕۑ�����Ă���k�Ђʼnꂽ�������A���p�[�N���������̓����̗l�q����Ă��܂����B �@���̌�͂Q���ڂ̃��C���ł���l�Ɩh�Ж����Z���^�[��K��܂����B�S�K�ɂ���k�ВǑ̌��t���A�̉f���C�k�В���̃W�I���}�C�����Ɍ������l�X�̊X�Â���Ɗ肢�Ȃǂ����������āC�q�ǂ������͋�����ۂ��Ă����悤�ł��B �@�R�K�̐k�ЋL���t���A�̓W����k�Б̌��̃R�[�i�[�ł͎q�ǂ������͂�������̂Ƃ���ɗ����~�܂�C�������Ƃ�C�̌��k�Ɏ�����������ƌX���Ă��܂����B�Q�K�͖h�ЁE���Б̌��t���A�ʼnt��h��̎����C�Q�[�������Ȃ���C�M�S�Ɋw�K�����Ă��܂����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@����̏C�w���s�̑̌���ʂ��āC�q�ǂ������͈�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�\���ɂł��Ȃ������Ƃ��������܂������C�o���Ɠw�͂��d�˂�Ƃ���ɉ��l������̂ł��B�����ǂ̎q�Ɍ��g�I�ɐ��������Ă���p�C�����������������ƒ��߂Ȃ���P���̍s�������Ă����ǒ��C���ꂼ��ɓw�͂��d�ˁC�����ł��ڕW�ɋ߂Â��悤�Ƃ����l�ЂƂ�̎p����ۂɎc��܂����B �@           |
||||||
10��15���i���j �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�l�������[�ߍ��������Ƃ��߂������@�@  �@�O���Ŏ��Ɖ��P�Ɍ��������g�݂ɂ��Ĉȉ��̂��Ƃ��w�Z�����ł��`�����܂����B �E �u�b���E�����v�u�����v���Ƃɔ�ׂāC�u�ǂނ��Ɓv�����Ƃ��Ă���B�Ǐ��w���̏[���͂��Ƃ��C���t�ɂ�������ƌ��������w�������Ă����B �E �w�э����w�K��i�߂Ă��邪�C�����̍l�����o�������C�[�ߍ������߂ɁC�O���[�v�w�K�i��w�N�͂Q�`�S�l����{�ɁC���w�N�ȏ�͂S�l�O���[�v����{�Ɂj�����ƂŐϋɓI�Ɏ�����Ă����B �@���Ƃ̏[����ڎw���āC���ƌ���������I�ɍs���Ă��܂����C10��10���i���j�ɂ́C3�N1�g�̑���搶�̍���̎��ƌ����Ɏl���s�s����ψ���w���ێw���厖�������āC�S�E���ōs���܂����B �@�R�N���ꉺ�w���������̂���������x16���Ԓ���6���Ԗڂ��Q�ς��܂����B�܂��C�w���������̂���������x�̂��炷�����Љ�܂��B �o������O�̓��C���Ƃ�����́C�u����������v�Ƃ����V�т��C���������ɋ����܂����B���Ƃ�����C����������C���������C���ɂ������̎l�l�Łu����������v�����āC�l�l�̉e����ɏオ��܂����B����́C�傫�ȋL�O�ʐ^�̂悤�ł����B �@���̌�C�푈�͌������Ȃ�C��P�̂Ȃ��C���������͉Ƒ��ƁC���ꗣ��ɂȂ��āC��l�ڂ����ɂȂ�܂����B �@��P��������C���������́u����������v�����āC���ɂ��Ƃ�����C����������C���ɂ������̉e�����āC��ɋz�����܂�Ă����C���������̖��̉͏����܂����B �@�q�ǂ������͂��̕���̃N���C�}�b�N�X�i�ǂݎ�̃n���n���C�h�L�h�L�������Ƃ����܂�Ƃ���C�o�����i�����j���������C���̕��ꂪ�ǂ�Ȃ��b�ł��邩�����܂�Ƃ���j���l������ƂɗՂ݂܂����B���̕���̃N���C�}�b�N�X�́u������������Ȃ������u�ԁv�ƍl�����C�q�ǂ������͂�������̈ӌ����o�������Ă����܂����B �搶�F�N���C�}�b�N�X�͂ǂ����ƍl���܂������B �����P�F�u�Ă̂͂��߂̂�����v�Ǝv��������ǁC�u�������āC�����ȏ��̎q�̖����E�E�E�v�Ƃ���̂ł������O���ƍl���܂����B �����Q�F����͓o��l�������������t�ł͂Ȃ�����B �����R�F�N���C�}�b�N�X�́u���������B�v���Ǝv���B���ꂳ��C���Z�����P�ŎE���ꂽ�B���������ɂ͂�������厖������B �����S�F����������Ȃ�������C�����������m��Ȃ�����B �����T�F����������Ȃ�������C�����������m�炸�Ɏ����� �����U�F�u���ꂿ���C���Z�����B�v�̂Ƃ���B���������͂������܂�Ă����āC����ł��܂����Ǝv��������B�N���C�}�b�N�X�͔߂��݂₤�ꂵ�������܂�Ƃ���B���́C�߂��݂����܂�C�ł��C����������ɉ�Ă��ꂵ���C����������Ǝv���B �����T�F���������͎��B���l�ɉ���̂�����C�������������̂ł͂Ȃ����B�u���ꂿ���C���Z�����v���N���C�}�b�N�X�ɕt�������܂��B �@���̂悤�Ɏq�ǂ������́C�����̍l�����C���R��Y���ďo�������C�܂��C�l�̍l�����Ď����̍l�����C��������C�t�������������肵�܂����B���ɕ���̗����ЂƂЂƂ̌��t�ɂ������C���������Ȃ��玩���̍l����z���グ�Ă���悤�Ɋ����܂����B �@�܂��C�q�ǂ�������4�l�O���[�v�Ō݂��̍l�����𗬂������C���̌�C�S�̘̂b�������ւƂȂ��Ă����܂����B �@3�N���́C�O���[�v���������p���邱�ƁC�������Ƃ����낢��ȏ�ʂŎ�����邱�ƁC�����̍������l���邱�Ƃɗ͂����Ă��܂��B�q�ǂ��������f���Ɏ����̎v�����o�����������w�K�ւ̈ӗ~�C�݂��̎v����l�����~�߂�����W�Ȃǂ����������邱�Ƃ��ł��܂����B�������q�ǂ������̎p������ɍ��߁C�w�т��L����[�܂荇����W����w�z���グ�Ă����悤�S�E���œw�͂����Ă܂���܂��B �@�T�N���Љ�w�ɍs���Ă��܂����@�@ 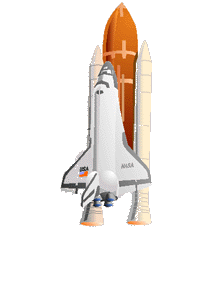 �@10��9���i�j�C5�N���͎Љ�w�Ƃ��āC�u�������ۋ�`�i�Z���g���A�j�v�ƃR�J�R�[���E�Z���g�����W���p�����C�H��v��K��܂����B5�N���͎Љ�ȂŁu�킽�������̐����ƍH�Ɛ��Y�v�ɂ��Ċw��ł��܂��B���̓��e�������̖ڂŌ��āC�����āC�m���߂邽�߂ɁC�Љ�w�ɍs���Ă��܂����B �@�@  �@ �@ �@ �@ �s�������ۋ�`�i�Z���g���A�j�t �@��8���Ɋw�Z���o�����āC�Z���g���A�ɒ������̂�9��30���O�ł����B�����Ƃ����̂Ől�͂��܂葽���͂Ȃ������ł����C�傫�ȗ��s�J�o���������l�̊O���̐l�ɓ�����ŏo��C�q�ǂ������̓n���[�Ɛ��������Ă��܂����B �@�E�G���J���K�[�f����6���̃{�����e�B�A����Əo��C���w���n�܂�܂����B�܂��͑傫�����ɕ�����āC�������̃O���[�v�̓o�X�ɏ��C���i�ł͐�ɓ���Ȃ���s�@�Ɖݕ�������ݕ��n��⊊���H�X�y�[�X�̌��w�ɁC�u�Љ�w�ؖ��v���Ԃ牺���ďo�����܂����B�ē��͓�����ݕ��œ����Ă���JAL�̕��ł����B��ϒ��J�Ő�����������₷���D�������Ă܂����B �@�ݕ��n��₻�̑��̃G���A�ł͑�ϒ���������Ԃ�{�݂����邱�Ƃ��ł��܂����B����ԂƂ��ẮC�g�[�C���O�g���N�^�[�i�R���e�i�h�[���[��p���b�g�h�[���[�Ȃǂ���������ԗ��j�C�v�b�V���o�b�N�g���N�^�[�i�q��@�̃v�b�V���o�b�N��g�[�C���O�Ɏg�p�����^�ԗ��j�C�n�C���t�g���[�_�[�i�ݕ������̍q��R���e�i�̓��~�ڂɎg�p����ԗ��j�C�x���g���[�_�[�i�o���ς݉ݕ����֎�ו���ݕ����R���x�A�ɂ���Ĉڑ�����ԗ��j�C�R���e�i�h�[���[�i�q��@�R���e�i���ڂ��ĉ^���E�ڑ�������ԗ��j�C�f�A�C�V���O�J�[�i�q��@�Ɍ������Ėh�X�܂������Đ����菜���ԗ��j�Ȃǂ�����܂����B�����œ����l�����́C�������ɋC�y�Ɏ��U���Ă���܂����B �@���������̂Ƃ��ẮC��s�@�̋@���H������Ă���u�P�[�^�����O�v�̌��������܂����B��`���ɂ��̎{�݂�����C�����ō���Ă���Ƃ͏����\�z�O�ł����B �@�o�X����~�肽��́C���q�^�[�~�i����3�K����Ɍ��w���܂����B��s�@�ɂ̂�Ƃ��̎������̐����⍑�O����̎����֎~���Ȃǂ����߂Ċw�т܂����B�W�]�f�b�L����͔�s�@�̗����������܂����B���Ɍ������Ĕ�Ԃ悤�ɂ��Ă���̂ŁC���̌����ɂ���Ċ����H�̎g�����ɈႢ�����邱�Ƃ�Z���g���A�̖����n�̌`���Ȃ��l�p�łȂ��ʂ�`���Ă���̂��̂��b�������[�������ł��B�q�ǂ������͔�s�@�ɋ���������C��������̂��Ƃ�m���Ă��܂����B �@�q�ǂ������́C���̌�C�R�J�R�[���H������w���C�A�H�ɒ������킯�ł����C���w���͔M�S�Ƀ������Ƃ�C�������ꂸ�ɗ��\�����g���Ă��܂����B�w�K�͂܂Ƃ߂邱�Ƃ������̖{���̗͂ɂȂ�̂ŁC�����蒮�����肵�����Ƃ�܂�����ɒ��ׂ邱�Ƃ���������Ƃ��āC�����̒m���Ƃ��Đg�ɂ��Ă��������B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@        |
||||||
| 9��20���i�j �@�@  �@ �@ �@ �@ �@  �g�̈��S�����Ƃ��@�@�@�@ �g�̈��S�����Ƃ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�u�[��ꎞ�C������Ƒ��߂̃��C�g�E�I���^���v�| �@9��22���i�y�j�͏H���̓��ł��B���̓������ɓ��ɓ��ɗ[��ꂪ�����Ȃ��Ă����܂��B10��1���̓��̓���͌ߌ�5��37������ł��B�悭�w�Z�Ɂu���]�Ԃ����C�g���_�����ɑ����Ă��ĂԂ��肻���ɂȂ����B�v�Ƃ����n��̕�����̐����͂��܂��B �@��ʎ��̂𖢑R�ɖh�����߂ɁC10��1���i���j�`12��31���i���j�܂ł�3�����ԁu�[��ꎞ�C������Ƒ��߂̃��C�g�E�I���^���@�`�Z�[�t�e�B�[�E���C�g�E�I���^���`�v�����{����܂��B �@���i�����Ƃ��Ď���2�_���������Ă��܂��B �@�@ �[��ꎞ�̑��߂̃��C�g�̓_���i���]�ԗ��p�ҁC��֎ԁC�����ԗ��p�ҁj �@�A ���ˍނ̒��p���i�i���s�҂���ю��]�ԗ��p�ҁj ���̂͋N�����Ă��܂��Ă���ł͉����Ȃ�܂���B�Ԃɏ���Ă���l���\���ɋC�����Ă���Ƃ͎v���܂����C���]�ԗ��p�҂���s�҂����̂���g����邱�Ƃ��\���ɐS�����Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́C �@�@ ���v�O����K�����]�Ԃ̃��C�g��_����B �@�A ���]�Ԃ̃y�_����ԑ̂̊e�����ɔ��˔����t����B �@�B ���s�҂͖��邢�����Ɣ��ˍނ𒅗p���āi�^�X�L���j�ԂɃA�s�[������B �@�C ���]�ԗ��p�҂̓w�����b�g�����Ԃ�B�i�w�����b�g�ɂ����ˍނ��j �@�ȏ��4�_�ɐS�����Ă��������B���ƒ�ł����q����ւ̓��������⎩�]�ԓ_�������肢���܂��B���X�̐S�������C�傫�Ȏ��̂𖢑R�ɖh���܂��B �s�Z�[�t�e�B�[�E�o�C�V�N���E�f�[�iS�EB�f�[�j �@������P���j���́u���]�Ԉ��S�����v�ł��B���]�Ԉ��S���p�ܑ����Љ�܂��̂ŁC�S�|���Ď��̂̂Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�P�@���]�Ԃ́C�ԓ��������C�����͗�O �@�Q�@�ԓ��͍�����ʍs �@�R�@�����͕��s�җD��ŁC�ԓ��������s �@�S�@���S���[������� �@�@�@����l���C���i�̋֎~ �@�@�@����Ԃ̓��C�g��_�� �@�@�@�������_�ł̐M�������C�ꎞ��~�ƈ��S�m�F �@�T�@�q�ǂ��̓w�����b�g�𒅗p �@���̂͋N������̂ł���ƍl���s�����邱�Ƃ��C���̂�h�����ƂɂȂ���܂��B 9��21���i���j�`9��30���i���j�͏H�̑S����ʈ��S�^���ł��B�݂�ȂŋC�����܂��傤�B �@�V�����p�ꊈ���̐搶������Ă����@  �@9������V�����p�ꊈ���̐搶�ɑ���܂����B���O�̓u�����g������ł��B���{�ɗ��Ă���3�N�ڂɂȂ邻���ł��B���{�����Ϗ��ŁC����1���Ԃ͓��{��̕��𑱂��Ă��āC���������Ȃ菑����悤�ɂȂ��Ă����悤�ł��B�u�����g���搶�͑�ϐe���݂����āC���Ƃ��������낢�ł��B1�N������4�N���݂̂Ȃ�����y���݂ɂ��Ă��Ă��������B �@�u�����g���搶�Ɏ��ȏЉ�������Ă��炢�܂����̂ŏЉ�܂��B �@My name is Brenton Shelby Gettmann. I am from Huntington Beach, California. I like playing baseball and surfing. �@If you can enjoy English, you can speak English. It�fs OK to make mistakes, so please try. Let�fs enjoy English class together. �@�킽���̖��O�̓u�����g���E�V�F���r�[�E�Q�b�g�}���ł��B�J���t�H���j �A�B�n���e�B���g���E�r�[�`�������Ă��܂����B�킽���͖싅�ƃT�[�t�B�����D���ł��B �@�p����y���ނ��Ƃ��ł���Ȃ�C�p���b�����Ƃ��ł��܂��B�Ԉ���Ă������̂ŁC����Ă݂Ă��������B��������ɉp��̃N���X���y���݂܂��傤�B        |
||||||
| 9��10���i���j �@�@  �@ �@ �@ �@ �ۈ牀�E�c�t���Ƃ��������P��  �@9��4���i�j�ɓ��C���n�k�����i�k�x�T�����l8.0�j�C��d�ƒ����쌈���z�肵�����P�������{���܂����B�n�k�������ɒ�d�������߁C����������ɂăx����炵����Ƀn���h�}�C�N�Ŏw�����o���P�����s���܂����B�^����ɔ��C�l���m�F�̌�C�����������x�ꂽ�Ƃ����z��̂��ƁC���q���h�g�D�Ɋ�Â��āC�~�����������{���܂����B �@���߂ĕۈ牀�E�c�t���Ƃ̍����̔��P�����s���܂����B�ۈ牀���c�t�����傫�Ȓn�k�̎��ɂ͖{�Z�̉^���ꂪ��1�����ꏊ�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁC�����ł��邱�Ƃɂ����̎菇��A�g�E�ۑ�����邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��C����͒����쌈���z�肵�C�c�t���E�ۈ牀�̉����̊F����͏��w�Z��3�K�̎����o���ɔ������܂����B�����őҋ@���C�^���������̂�҂Ƃ����z��ł����B�����o�����ł͒n�k�Ɋւ��鎆�ŋ����玩�������̍s���ɂ��čl���鎞�Ԃ��Ƃ�܂����B �@���w�Z�̎�����3���ڑ̈�قɓ���C�h�Њw�K���s���܂����B�����Ō����̂́C3��11���̓����{��k�Ђł͐��������s���̃A�j���ł����B�u���̊�Ձv�ƌ�����o�����ł��B����́C�L�Z�����w�Z�Ɗ��Γ����w�Z�̎������k�̍s���ŁC���ꂩ��̂����ɂƂ��Ċw�Ԃׂ����Ƃ���������܂����B �@�Z��3�K�ɔ������w�Z�̎����͊��Γ����w�Z�̐��k���Z��ɔ���̂����āC�����̒��w�Z�Ƃ̍����P�����v���o���āC����̔��f�ōZ��ɂ����o���܂����B�������k��500������ɂ��鍂��̃O���[�v�z�[���ɔ��܂����B���̎��C�����̗����̊R�������̂����āC�������k�͊댯�Ɣ��f���Ă����500����̍���̉�앟���{�݂Ɍ����܂����B���̖�30�b��ɃO���[�v�z�[���͒Ôg�ɓۂݍ��܂�܂����B�w�ォ�甗�鍌����g�̂��Ԃ������ď����w�������͎{�݂�肳��ɍ���ւ����܂����B�Ôg�͉��{�݂̖�100����O�Ŏ~�܂�܂����B���J�n����10�����炸�̏o���������������ł��B �@�ЊQ�͎��ۂɂ͑z��ʂ�ɂ͂����܂���B�z��ɂƂ��ꂸ�C���̏ꂻ�̏�̍őP�̔��f���K�v�ɂȂ�܂��B�����āC���悵�Ĕ������邱�ƁB���̊�Ղ͎������ɑ����̂��Ƃ������Ă���܂����B �@�ȉ��̂��Ƃ͖h�Ѓm�[�g��f��C�����Ŋw���K�ɂȂ�܂��̂ŁC�悭�ǂ�ŁC���̒��ɐ������Ă����Ă��������B���ƒ�ł��@����Ƃ炦�Ęb�������C�n�k�ɔ����Ă������������Ǝv���܂��B ���w�Z�ɂ���Ƃ��ɒn�k�����������ꍇ �s�����ɂ���Ƃ��t �@�}���ŋ��������яo�����肵�Ȃ��悤�ɁC�܂��͊��̉��ɂ������ďォ�牽�������Ă��Ă����v�Ȃ悤�ɓ������܂��傤�B�����Ēn�k�̗h�ꂪ���܂�����C�搶�̎w���ɏ]�����܂��傤�B �s�L���ɂ���Ƃ��t �@�@�L���ɂ���Ƃ��ɒn�k���N��������߂��̋����ɓ�����̉��ɂ�����܂��傤�B���ꓮ�����Ƃ��ł��Ȃ����炢�h�ꂪ�Ђǂ����́C�K���X����|������ȂǓ|��₷�����̂��痣��Ă��Ⴊ��őҋ@���܂��傤�B �s�K�i�ɂ���Ƃ��t �K�i�ɂ���Ƃ��ɒn�k���N�������ꍇ�C����ĂĊK�i�����肽�������肷��̂͊댯�Ȃ̂ł��̏�ɂ��Ⴊ��őҋ@���܂��傤�B �s�^����ɂ���Ƃ��t �O���b�Ƃ����Ƃ��^����ɂ�����C�����|��Ă��Ȃ��^����̂܂ő҂��܂��傤�B ���w�Z�o���Z���ɒn�k���N�������ꍇ �@�܂����œ������܂��B����Ɍ����C�d���C�u���b�N���⎩���̔��@������C���̏ꂩ����S�ȂƂ���܂ŗ���܂��B���̏�ɂ���Ƃ��͑f�������������Ă������痣��܂��傤�B �s�߂��̈��S�ȏꏊ�i�����E�Z��j�֔��t �w�Z���߂��ꍇ�͂��̂܂܍Z��ɔ��܂��傤�B�w�Z���狗��������ꍇ�͋߂��̌�����L���ꏊ�ł�ꂪ�����܂�܂ł������痣��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���̌�C���炭�l�q�����ĉƂɈ����Ԃ����C�w�Z�֍s���Đ搶�̎w�����܂��傤�B �ƂɋA��ƉΎ��������ȂƂ���ŋN�����Ă�����C�Ƃ��|��Ă����肵�ċt�Ɋ댯�ȏꍇ������܂��B���̓_�C�w�Z�Ȃ�A�������₷�����ꏊ�ɂ��K���Ă��܂��B ���������������������������������������������������������� ������x�u�n�k�x���錾���ւ̎����̑Ή��v�ɂ��Ċm�F���܂��B �� �Ƃɂ���Ƃ��u���ӏ��܂��͌x���錾�v���o���ꍇ �@�@���ӏ�o�����_�ŁC�w�Z�͋x�Z�ɂȂ�܂��B�w�Z����̘A����Ƃ̐l�̌������Ƃ��悭���C���S�ȏꏊ�ɂ��܂��傤�B �� �w�Z�ɂ���Ƃ��u���ӏ��܂��͌x���錾�v���o���ꍇ �@�@�����C�S�����͕ی�҂̏o�}��������܂ŁC�w�Z�őҋ@�����܂��B �@  �y����̊F������̂����т������܂��� �y����̊F������̂����т������܂����@9��7���i���j�̌ߑO���ɁC����n��̊y����݂̂Ȃ�������������C�u�̗V�сv�������܂����B1�N���̎q�ǂ������͖{���Ɋy���݂ɂ��Ă��āC�҂��ɑ҂������������Ƃ��������ł����B �@�����͑̈�قɁu���ʁC�|�ۂ�����C����܂��Ƃ��C�߂C�܂莆�C����ʁC����Ƃ�C���͂����C�|�Ƃ�ځC���܁v��10�̃u�[�X��݂��đS�������ׂĂ̗V�т��o������Ƃ����`�����Ƃ�܂����B�q�ǂ������͖{���ɐ��������Ƃ��Ă��܂����B�ǂ�ɂ���ϋ����������C�{���ɏ��ɂ���Ƃ��������C���܂��܂킵����C�ς�������y���肵�܂����B�����̂��y�������͕̂ς��Ȃ����̂��Ɗ����܂����B�y����݂̂Ȃ���̕\��������ւ���炩���C�{���ɒn��̎q�ǂ������������厖�ɂ��Ă��������Ă���̂��悭������܂����B �@�q�ǂ������̖ڕW�́u���l�ɂȂ낤�v�ł��B���ꂩ�獡��������̂������ς����K���C�܂���9�����̎q�ǂ��Ղ�̂Ƃ��ɗc�t����ۈ牀�̊F����ɔ�I���C�������������܂��B1�N���̎q�ǂ������̐������y���݂ł��B �@��ς��Z���������Ă��������܂����y����݂̂Ȃ���ɉ��߂Ă����\���グ�܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@  3�N���u�M�������}�Y���v�̕���������܂��� �@3�N����6���̏��߂̃v�[���|���O�Ƀv�[���̃��S�̋~�o�����s���܂����B�v�[���ɂ������S�̓V�I�J���g���{�Ɛԃg���{�̃��S�ł����B����������ʼnH�������܂����B�ł͂Ȃ��v�[���Ƀ��S������̂ł��傤���B����̓V�I�J���g���{��ԃg���{�͐��ʂɋY�������邩��ł��B �@9��5���i���j��3�N���͒�����̉͐�~�Ɉ����Ƃ�ɏo�����܂����B����́C�v�[���ɃM�������}�̎Y���ꏊ����邽�߂ł��B�M�������}�̓V�I�J���g���{�Ƃ͈Ⴂ�C�Y�����s�킸�C���ӂ̑��ɎY�������邩��ł��B�����ŁC�v���X�e�B�b�N�̂����Ƀy�b�g�{�g���̕��������t���C�����Ɉ���}�������ׂ܂����B�ʐ^�̂Ƃ���C�v�[���ɐl�H�̐��ӂ̑������o�����܂����B3�N�����������ׂ�Ƃ����Ƀg���{������Ă��Ē�@�����Ă���悤�ł����B�s�v�c�Ȃ��̂ł��ˁB �@3�N���̂��̃M�������}�̕������͊m���ɁC�M�������}�̎Y���ꏊ�����܂����B�����āC���N�̃v�[������̓M�������}�̃��S����������̂�܂��B���̑���C�V�I�J���g���{�Ȃǂ̃��S�͍̂�Ȃ��Ȃ�܂��B����͂ǂ����Ăł��傤���B���̂��Ƃ͂܂����N�ώ@���Ȃ���������Ă݂����Ǝv���܂��B3�N���̕������͐������̂��̂����Ȃ�����ł��������̂ł��B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@ �@�@�@  �@ �@ �@ �@           |
||||||
9��3���i���j �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�������܂������̂悳���̂��� �@44���Ԃ̉ċx�݂��I���C9��3���i���j���炢�悢��2�w�����n�܂�܂����B�C�w���s�C���R�����C�O�����y��C�Љ�w�C�������L�^��Ȃǂ�������̍s������ƁC���犈����ʂ��āC�����̂悳���o���C������傢�ɂ̂��Ă��������B �@���N�̉Ă̓����h���I�����s�b�N������C���{�̑I�����ϊ��܂����B�������́C�I�肽���̂����Ɍ��C�������ς����炢�܂����B�܂��C�I�肽���͎������ɂ�������̃��b�Z�[�W���c���Ă���܂����B �@�Ȃł����W���p�����q�T�b�J�[���V��H�I��́C�u�ꂵ���Ȃ�����C���̔w�������āB�v�u�������Ă��Ƃ́C�����Ȃ����Ƃ���Ȃ��B�����Ă��܂����邱�ƁB�v ���j�̖k���N��I��́C�u�����]���ɂ��Ă܂���B�������]���ɂ��Ă���C�����邱�ƂȂ�Ė����ł��B�����j���̂��D��������C�ł��������ł��B�v �@�싅�̕������I��́C�u�V�ˏ����H�V�˂��ĕ֗��Ȍ��t����ˁB�����āC�V�˂��Ă�������C�w�͂����Ȃ��ŁC�����Đ��܂ꂽ���̂����ł���Ă����悤�Ɏv�����Ȃ����Ȃ��B���C�N�������K���Ă��B���̎q���݂�ȋA���Ă��C�ЂƂ�ŗ��K���Ă��B�v�u���_�����|���Ă�����Ė������Ȃ����Ǝv�����B�i�����{��k�Ђ́j��Вn�Ɏ����ċA���̂ł��ꂵ���B�v �@�I�����s�b�N�̑I�肽���́C�u�����܂ł���ꂽ�̂�����̐l�����̎x�����܂��C�Ȃ��܂Ƃ̂Ȃ���C���{�݂̂Ȃ���̉����v�����ꂼ��̌��t�Ō���Ă��܂����B�����������X�̐����Ŏ�����M���C�����̉\����悳��L���w�͂�����K�v������܂��B��l�ł͂ł��Ȃ��Ă��Ȃ��܂�����ł��邱�Ƃ���������܂��B2�w���̓N���X��w�N�̂Ȃ��܂����Ɗ���������@���������܂��B�Ƃ��Ɉ炿�������Ƃ�����āC�Ƃ��ɋP��2�w���ɂ��Ă����܂��傤�B�搶�������F�����ƂƂ��ɕ��݁C�Ƃ��Ɋ��������Ǝv���܂��B���̂��߂ɂ́C�݂Ȃ���ւ̎x���͐ɂ��݂܂���B |
||||||
7��20���i���j �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�������g��\���ł���1�w���ł������@�@  �@�����C7��20��(��)��1�w�����I���ƂȂ�܂��B����3�ӏ��̍Z��ɗ����C�q�ǂ������̓o�Z�̗l�q�����Ă��܂����B�o�Z�ǂł�����ƕ���ŕ����Ă�����ǂ��قƂ�ǂł����B�܂��C�����������X�Ɏ�������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������C�M���ŗ��ꗣ��ɂȂ肻��킸�ɗ���ǂ₠�������C�p���������̂��C���ɂȂ�Ȃ��q�����܂����B�o�Z�ǂ͈يw�N�̑厖�Ȋ����ł���Ƃ��l�����܂��̂ŁC���ɍ��w�N�̎q�����̊w�N�̎q�̋C���������݂݂�Ȃŋ��͂��ēo���Z�ł���悤�Ɍ���肽���Ǝv���܂��B �@�Ƃ���ŁC�q�ǂ������ɕK�v�ȎO�́u�ԁv�Ƃ����̂��C���̎q�ǂ������ɂ͏��Ȃ��Ȃ����ƌ����Ă��܂��B�q�ǂ����������������ƈ���߂ɂ́u���ԁC��ԁC���ԁv�̎O�́u�ԁv���s���ł��B �@�� �����̂��������Ƃ�����������g�ގ��ԁC�������l���鎞�ԁ@�Ȃ� �@�� �v��������V�ׂ�X�y�[�X�C���R�ƑΘb�����@�Ȃ� �@�� �ꏏ�ɏW�܂��ėV�Ԓ��ԁC�ٔN��łƂ��Ɉ炿�������ԁ@�Ȃ� �@�݂�Ȃ��W�܂�ꏊ�Ǝ��Ԃ�����C�F�����Ƃ������W�������C�q�ǂ������͎��R�Ƒ��҂�厖�ɂ��C�܂��������g�����������̂Ȃ����݂ƋC�Â����Ƃł��傤�B��������l�͂��̊��𐮂���w�͂�����K�v������܂��B �@�ċx�݊��Ԓ��C�q�ǂ������͉ƒ��n��ɋA��C������肽���Ă��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��������Ƃ�C���̋@��ɂ����ł��Ȃ��̌�����Ɏ��g�ނ��ƂƎv���܂��B�Ƒ��̈���Ƃ��Ă̖����C�Ƒ��E�e�ʂƂ������Ɖ߂�����C�v��������V�Ԏ��ԁC�F�����ƂƂ��ɍl���������邱�ƂȂǂ�厖�ɂ��Ȃ���C�ċx�݂��߂����Ăق����Ǝv���܂��B��l�ЂƂ肪��i�Ɛ����̐߂����݁C���̂�a�C�ɏ\���C�����C�����܂������������p��2�w���ɓo�Z���Ă��Ă���邱�Ƃ�S�������Ă��܂��B ���āC7���ɓ����Ă��낢��Ȋw�K����g�݂�����܂����̂ŁC�Љ�܂��B �@4�N���u������T���v���s���܂����@ �@ �@7��10���i�j�ߑO����4�N���͒�����ɍs���C�������������s���܂����B�l���s�s���w�K�Z���^�[�E��2���C������ɂ��킵���{�����e�B�A4���̕������������C�����w�K�̂����b�ɂȂ�܂����B �@�̈�ّO�ɏW�����C�u�t�̕��̏Љ�C��̒����̐S�\����C�����邱�Ƃ�����C������Ɍ������܂����B������ł͂܂���̃`�F�b�N���s���܂����B�V�C�͐���C������22�x�C�앝��25m70�p�C�����͖��b5m�C�[����30cm�C��͍��ƐB��{�I�Ȑ�̒��������Ă���C���悢�搶�����������n�߂܂����B1�g�͉��싴������100m���̒n�_�ŁC2�g�͉��싴�t�߂Œ������J�n���܂����B �@���ʂ��������������̂ŁC�ĐA���������Ă����̒[�ɍs���āC�쉺�ɖԂ�u���C���ł������ċ���ǂ�����ł����܂����B�͂��߂̓R�c�����߂Ȃ��q�����X�ɋ��₢�낢��Ȑ��������Ԃɓ���Ɗ������オ���Ă��܂����B �@������ɐ쌴�ŃN���X���Ƃɐ������̕��ޕ������s���܂����B �@���ł́C���V�m�{���C�J�����c�C�A�u���n���C�^�����R�C�h���R�C�V�}�h�W���E�C�M���u�i�C�A�J�U�Ȃǂ����܂����B2cm���炢�̏����ȃA�J�U�ł������C��ϒ������������邱�Ƃ��ł��܂����B �@���сE���ɂł́C�X�W�G�r�C�k�}�G�r�C�A�����J�U�j�K�j�Ȃǂł����B �@�����ł́C�n�O���g���{�C�R�I�j�����}�C�^�C�R�E�`�C�i�x�u�^���V�C�~�Y�J�}�L���C�J���Q���Ȃǂ܂��܂����܂����B �@���̂悤�Ȓ����̌�C4���ڂɑ̈�قɏW�܂�C�ǂ��ƂɂƂ炦���������̎�ނ␔�̔��\�����C������ꗗ�ɋL�����Ă����܂����B���̐��������璩����̐����́u��������Ă��鐅�v�ɕ��ނ��܂����B �@�Ō�̎���R�[�i�[�ł́u�Ȃ��w�r�g���{������Ƃ��ꂢ�Ȑ��ƕ�����̂ł����v�Ƃ������₪�ł܂����B�w���҂̕�����́u�w�r�g���{�͐��ɑ����������C���ꂢ�Ȑ��ɂ������߂܂���B���̂��߁C������≺����ł͂قƂ�ǐ������݂��܂���B���̂悤�ɐ����ɂ�肻���ɐ��ސ���������ނ����܂��Ă��܂��B�v�Ƃ��b���f���܂����B���싴�t�߂͒�����̒�����ŁC������ς��ꂢ���Ɗ����܂����C���̂悤�ɐ���������������Ƃ��ꂢ�Ȑ��ɐ���ł��鐶�������قƂ�nj�����Ȃ��ƋC�Â����Ƃ��ł��܂����B �@4�N���͎Љ�Ȃ���w�K�Ń��T�C�N������ɂ������w�K�����Ă��܂��B����̊w�K�͔��W���Ȃ��瑱���Ă����킯�ł����C�n��̐�⎩�R���ɂ��C�n��̍��Y�Ƃ��Ď���Ă����l�Ɉ���Ă����Ɗ���Ă��܂��B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�~�b�V�F���搶�C���悤�Ȃ��@�@  �@��N9������1�N�Ԃ����b�ɂȂ�܂����B9������͐V�����w�Z�ɋΖ����邱�ƂɂȂ�C7��5���i�j�͖{�Z�ł̍Ō�̉p�ꊈ���ƂȂ�܂����B 6�N���̎��Ƃł́C �@When is your birthday? My birthday is �iMarch 9th�j.�@�̕��̗��K���r���S�Q�[���`���Ŋy���݂Ȃ���s���܂����B �@�Ō�Ƃ��āC�~�b�V�F���搶����A�����J�̏��w�Z�̘b������C�݂�Ȃ������ÁX�ł����B �E �w�Z�ւ̓X�N�[���o�X���C�ی�҂̎ԂŒʂ��Ă���B�w�Z�܂ł͉Ƃ̐ӔC�œo�Z������B�i���{�ƈ���đ�ύL���G���A����w�Z�ɗ��Ă���̂ŁC���{�̂悤�ɓk���Œʂ����Ƃ��ł��Ȃ��B�j �E �����͂��ׂ�1�K���ĂŁC1�N����3�N��4�N����6�N�̓�̊w�Z�ɕ�����Ă���B�v�[���͂Ȃ��B �E �����h�Z���łȂ��C�����b�N�T�b�N�̂悤�ȃo�b�N�œo�Z���C�����̓��X�g�����̃��j���[�ł��ٓ��ł��悢�B�ٓ��̓T���h�C�b�`�C�������́C��������B �E �Љ�w�≓���͂��邪�C�C�w���s�͂Ȃ��B�����ŃC�`�S���ɍs�������C�e�����Ă���B �E ���R������5���ԂقǍs���B �E ���Z�ŏ��߂ĊO������K���B �@�ʐ^�������ăA�����J���X�N�[���̘b���C���{�Ƃ̈Ⴂ��A�����J�̒��ł��B�ő傫�ȈႢ�����邱�Ƃ��q�ǂ������͒m�邱�Ƃ��ł��܂����B9���ɂȂ�Ƃ܂��V�����p��w���������܂��̂ŁC�V���ȏo��Ɗy�������Ƃ�W�J�������Ǝv���܂��B�ǂȂ��������邩�܂��������Ă��܂���̂ŁC�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B �@�@  �@ �@ �@ �@ 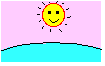 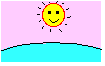 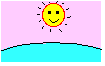 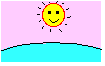 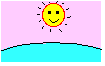 |
||||||
| 7��6��(���j �@�@  �@ �@ �@ �@ �@6�N���u�Ós�ޗǁv��K�˂� �@6��26���i�j�C6�N���͎Љ�ȂŏK�����ޗǂ̂��Ƃ��w�Ԃ��߂ɁC�Љ�w�ɏo�����܂����B�ޗǂƂ����ƁC���������Ԃ��Ƃ�����܂��B����͓ޗǂƂ������t�̌ꌹ�̖��ł��B�u�ޗǁv�̌ꌹ�͒��N��Łu���v�Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ������ƁC�u�ޗǁi�i���j�v�̌ꌹ�Ƃ��Ắu����ȁC���R�ȁi�y�n�j�v���Ӗ�����u�Ȃ�i���j�v�ł���Ƃ������i�R�����Ȕ��畽�R�ȓޗǖ~�n�̐^�Ɉڂ����s�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���Ƃ����j������܂��B�ǂ̌ꌹ���L�͂Ȃ̂��͕�����܂��C���ꂾ���ޗǂ͗��j���Â��C�Ñ�ւ̃��}�����������Ă܂��B �@���쏬�w�Z��7�F30�ɏo�����܂����B�����V�S�z����܂������C�ޗǂɋ߂Â��ɂ�ēV���C�ޗǂł͐��V�ł����B �@���r�̑O�Ŋw���ʐ^���B������C�o�X�K�C�h����̈ē��œ��厛�����w���܂����B�啧�̑傫���ɋ������C�q�ǂ������͒��̌���ʂ邱�Ƃɖ����ɂȂ�啧�̑傫�����������Ă��܂����B���̌�͔Ǖʕ��U�w�K�̊J�n�ł��B�S�C�̐搶���玭����ׂ���n���ꂽ��C�q�ǂ������͎�����ׂ���������̂Ɋy����ł��܂����B�������C���͂����Ɋ���Ă���̂ŁC�����f���q�����܂����B �@���C�O�����C�l�����C���O�C�s��C���q�@�C����ȂǂƓޗnj��������C�H��������ᑐ�R�̑O�̂��X�ɏW�����܂����B���߂Ă̂Ƃ���Ȃ̂Ŗ������ǂ�����܂������C�قƂ�ǂ̔ǂ����͂��Ȃ��炤�܂��s�����ł����悤�Ɏv���܂����B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�H����̓o�X�ŕ���{�ՂɈړ����܂����B�o�X�͕���{�Վ����ْ��ԏ�ɒ����܂����B�����ł�4�l�̕���{�Ճ{�����e�B�A�K�C�h���҂��Ă��Ă���܂����B4�ǂɕ�����āC�܂������ق����w���܂����B�����̕��鋞�̐l���͖�10���l�ł��̂�����l��7��l�������ƁB����{�Ɠ��厛�Ƃ̈ʒu�W��傫�������ۂ̖ڂŊm�F���܂����B�܂��C���̓����̋L�^�̖؊ȁC�u�h�i���j�v�Ƃ������̃`�[�Y�̂悤�ȐH�ו��ⓖ���̐����l���Ȃǂ����낢��w�т܂����B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�����ق��o�āC�������ꂽ��ɓa�����w���܂����B�����Ȍ����ŁC�����̂��낢��Ȃ��̂̐������C�m�邱�Ƃ���������܂����B������i�����݂���j�C�l�_�C�����C�哏��������Ȃǒ��������̂���ł����B �@�@  �@ �@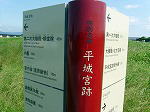 �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@��ɓa���o�āC��\�W���قɌ������܂����B�����ɂ͎��ۂɔ��@���ꂽ�܂܂Ɏc���ꂽ�����̈�˂⌚���̒����Ȃǂ����邱�Ƃ��ł��܂����B�����̏d�Ȃ肩��ޗǎ���̊ԂɌ�������������đւ���ꂽ���Ƃ��킩��܂����B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@���̂悤�ȎЉ�w��ʂ��āC6�N���̂��낢��Ȗʂɐڂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�݂�Ȃ��܂Ƃ܂��ĔǍs�����ł������ƁB�Ȃ��ł����q�����܂��j�q�����[�h���Ă������ƁB�Љ�w�̂�����ɁC�����蕷�����肵�����Ƃ��ꐶ�����Ƀ������Ƃ����肵�Ă������ƁB�҂��Ƃ��ł������ƁB���Ƃ��͂��Ƃ����p���������Ă��ꂽ���ƂȂǁB�������C���ׂĂ����i�_�ł͂���܂���ł����B�w���ŗF�Ƃ̂Ȃ����厖�ɂ��āC���ꂩ��ɂȂ���悤�Ɉ�w�̓w�͂Ƌ��͂ɗ��ł��������B�F����ւ̉�����x���͐ɂ��݂܂���B �@�����肳������Ă����@�@  �@6��25���i���j�̌ߑO���ɉ��쒓�ݏ��̂����肳��Ǝl���s�k���̕w�x����ƃp�g���[���J�[��2�N����K�˂Ă��������܂����B2�N���͉���n��ɂ�����̂�l�Əo���ʂ��āC�����Ȃ̊w�K�����Ă��܂��B2�N���͂܂����쒓�ݏ���K��܂����B����͂����肳��ɗ��Ă��������C�ǂ̂悤�ɂ݂�Ȃ̐����̈��S������Ă��邩�̂��b�₨���肳��2�N���̎q�ǂ������ւ̈��S�ւ̂��肢������܂����B���Ɏ��]�Ԃ̎��̂������̂ŁC���]�Ԃ̈��S�_���C���H��ł̏����C�w�����b�g�̒��p�C�s�R�҂ւ̑Ώ��̎d���i�����̂������j�Ȃǂ̘b��傫���f���o���ꂽ�ʐ^�ƂƂ��ɕ����܂����B �@���̌�́C�x�@�Ŏg���Ă��镨�������Ă��������C�G�����肵�܂����B�p�g�J�[�ɂ͏�点�Ă��炢�C�ׂ��ȑ��u�������g�����Ƃ��ł��܂����B�{���ɋM�d�ȑ̌��������Ă��炢�܂����B�q�ǂ������͌x�@�̎d���ɂ��Ȃ苻�����������悤�ł��B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
7��3���i�j 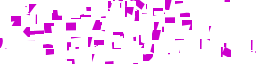 �@�@�@ �@�@�@ ��1�N�����@���[������Ɖ^����̎�����`���܂��� �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@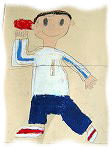 ��4�N�����@�q�ǂ������̂��̂������z�������������� �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ 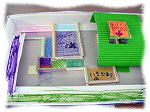 �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ ��5�N�����@���������Ă����o���܂� �@ 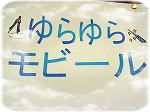 �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@           |
||||||
6��25���i���j �@    �@�w�Z�Â��苦�͎҉�c���J�Â��܂��� �@  �@6��21���i�j�ߌ�ɕ���24�N�x�̑�1��w�Z�Â��苦�͎҉�c���J�Â��܂����B�{�N�x�̈ψ���7���ł��B �@�w�Z�Â��苦�͎҉�c�́C�n��Z���C�ی�ғ����w�Z�Ƌ������Ċw�Z�Â���r�W�����̎�����}�邽�߂ɐݒu���ꂽ�g�D�ł��B�Љ�v������w�Z�Â������w���i���Ă������߂ɁC�ی�҂�n��Z���Ȃǂ̑��݂̈ӎv�a�ʂ⋦�͊W�����߂邱�Ƃ�ڎw���C�w�Z�Â���ɗ��ł܂��肽���Ǝv���܂��B �@�w�Z�Â��苦�͎҈ψ��̕��X�ɂ͖{�Z�̋�����j��w�Z�Â���r�W���������������ŁC�S�w���̎��ƎQ�ς����Ă��炢�܂����B��̉�c�ł͎��̂悤�Ȃ��ӌ��Ȃǂ����������܂����B �s�ψ��̊F����o���ꂽ���ӌ��⎿��Ȃǁt ? �X�̎q�ǂ��������N���X�̗ւ̒��ɓ����Ă��āC��ϗ����������l�q�ł��ꂵ���v�����B�����Ɛ搶�̊W�����܂������Ă���悤�Ɋ������B�悢�X�^�[�g����Ă����������B ? ������g�C�����ƂĂ����ꂢ�ŁC�X���b�p��G�Ђ����ꂢ�ɐ����Ă����B ? �}���{�����e�B�A����̋��͂�����C��������[������Ă��邵�C������������ƂȂ���Ă����B ? �d�q���̊��p�ƌ��ʂɂ��ċ����Ăق����B�i�������e�@����Ɋ��p���C���ƒ��Ɏ����̃m�[�g�⎑�������f���Ĕ��\�����肵�āC���p���Ă���B����������1�䂸����Ɗ��p����ʂ�������B�j ? ���Ȃ̎����͂ǂ̂悤�ɂȂ���C�[���͂���Ă��邩�B�i������厖�ɂ��Ă��邪�C5�E6�N�̗��Ȃɂ����Ă͋��ȒS�C�����l���Ă��������B�j ? �搶�ɂ�蓾�ӕs���ӂ�����̂ŁC�݂��̂悳���o�����������������C��[�߂Ă����Ă�����Ă͂ǂ��ł����B ? �����̌u�����̐F�ꂵ���ق������邭�Ȃ�B ? �w�Z����̓��H��ܑ��������Ă�������̂ŁC�ƂĂ��Â��ɂȂ��Ă悩�����B ? ���]�Ԃɏ��Ƃ��͐g����邽�߂Ƀw�����b�g�����Ԃ����ق����悢�B����C�n��C�ƒ�C�w�Z���������Đ��i����L�����y�[���ł��s���Ă����̂��悢�B ? ���w�Z�E���w�Z���ꂼ��̎����ɑ̌����Ȃ��Ă͂����Ȃ��l�ԊW��R�~���j�P�[�V�����C���ԂƂ̗V�тȂǂ�������Ƒ̌������ɑ�l�ɂȂ��Ă��܂��ƁC�L�єY��C���ȍm�芴�̒Ⴂ�l�Ԑ����`�����ꂽ�肷��B ? �q�ǂ���L���ɂ͌ɉ��������̂ւ����Ȃ��Ă����Ƃ悢�̂ł͂Ȃ����B �@�M�d�Ȃ��ӌ��Ȃǂ��������������܂����̂ŁC����̊w�Z�^�c����Ɖ��P�Ɋ������Ă��������Ǝv���܂��B �s�Z�N���̕ی�҂Ƃ�������̓��|�����t�@�@  �@6��21���i�j�͍��w�N�̎��ƎQ�ςł����B���̌ߑO���ɁC6�N���͕ی�҂ƂƂ��Ɋ���������u���|�����v���s���܂����B����Â���ɂ�郉���v�V�F�[�h�����܂����B�Ƃ��玝���Ă����傫�ڂ̃r���ɔS�y���������C�N�b�L�[�̂Â���̌^������y�b�g�{�g���̊W�Ő���C�����\��t���Ȃǂ��āC�ƂĂ����Ă��Ȃ��̂��o���オ��܂����B���w���ɂ͉H�Òn��Ő��������o�c���Ă݂��铡�䂳��ɂ��Ă��������C�����o���Ƃ������̂��ł��܂����B�Ă��オ�肪�y���݂ł��B�ƒ�ň��p���Ă��������B �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@        |
||||||
| 6��20���i���j �@    �@���[�������������߂������@�@  �@�@�@�@�@�@�@�|�@���ʔ��u�t������}���ā@�| �@�{�N�x������ʔ��u�t������}���āC���Ƃ̏[����}���Ă��܂��B�O�ɂ������܂����悤��3�N���̖ѕM�ɖx������C5�E6�N���̉p�ꊈ���ɐ�C3�E4�N���̐��j�w���Ɋ�c����Ɏ��Ƃɂ�������Ă��炢�܂��B���ʔ��u�t���x�Ƃ́C���L���o���������C�����ꂽ�m���ƋZ�\�����Љ�l�����p���邱�ƂŁC����������w��̓I�Ɋw�K�Ɏ��g�ދ��犈�������҂�����̂ł��B �@�p�ꊈ���ɂ��́C����23�N�x����5�E6�N���ɏT�P���ԉp�ꊈ���̎��Ƃ��n�܂�܂����B���݁A�N��35���Ԃ̎��Ƃ��s���Ă��܂����A���̂���25���Ԃ�ALT�ƒS�C�Ƃ̎��Ƃł��B�c��̖�10���Ԃ���ʔ��u�t�ƒS�C�Ƃōs���Ă��܂��B �@��搶�ɂ͒S�C��TT�Ŏ��Ƃ�i�߂邱�Ƃɂ��A�p�ꂪ���R�Ƒ̂ɓ����Ă��āC�p���b���g�����ƂɊ���e����ł��炢�����Ǝv���܂��B �@�x���搶�ɂ͏��߂Ă̖ѕM�Ƃ����̂ŁC��{���炵������Ǝw�������Ă��炢�C�����ł��Ă��˂��Ɏ����������Ƃ�g�ɂ��Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B �@��c�搶�ɂ͉j�͂ɉ������O���[�v�̈ꕔ��S�����Ă��炢�C�����ł����ɒ�R���Ȃ��Ȃ�C�����j��������L����悤�ɂ��Ă��炢�����Ǝv���܂��B ��l�ЂƂ�̎q�ǂ������́C�����\�͂Ɖ\�����߂Ă��܂��B���t�͂��Ƃ��C���̓��̐��Ƃ̐l������������w�сC�����̔\�͂�L���C�����̎��M�ɂȂ��Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B �@�l���s��P��m���Ă��܂����@�@�@  �@ �@1945�N�i���a20�N�j�A6��18���ߑO0��45���A�l���s���ɒB�����a�Q�X�d�����@89�@�����e���J�n�A�ĈΒe11,000���E567.3�g���𓊉����A���ɂ��đS�s��35���ɂ�����s�X�n���œy�Ɖ����A����736�l�E�s���s����63�l�̔�Q���o���܂����B����6��18������8��8���ɂ�����9��̋�P����808�l�����S���܂����B �@�l���s�w���ɂ���L�X�����ɂ͎l���s��P��`����L�O��i�l���s��P�}���j������܂��B�����ɂ͎��̂悤�ȕ������܂�Ă��܂��B �@�@�@�@��@�@�� �@���a�\�Z�N�\�����ɖu�����������m�푈�́A�|�c�_���錾����ɂ���āA����\�N�����\�ܓ����ɉ䂪���̔s��ɏI������B �@���̊ԁA�A�����J��R�d�����@�a�Q�X�ɂ����{�{�y�ւ̋�P�͓��܂��Ɍ������A��Ђ͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ������B�C�R�R�������͂��ߑ����̍H��Q��i�����l���s�s�́A�O��Z��ɂ킽���Ȕ����ɂ���œI��Q�����B�킯�Ă��ŏ��̔��������Z���\�����̍ЉЂ͐��S�̈��ɐs����B�����ߑO�뎞�l�\�ܕ��������ꎞ�Ԃɂ킽��A�a�Q�X�O�\�܋@�̈ꖜ���ɂ���Ԗ����ĈΒe�����O�~�����ɂ��s�X�n�͎ܔM�̂�ڂƉ����A�ޘH��₽�ꂽ�����̎s���́A���@�����̍J��f�r�����B���̋]���ƂȂ���́A���ɕ����ꒂ����������́A�g��������݂����Ɉꖽ��q������́A���킹�Ĕ��S�]���ɂ̂ڂ����B���|�̈�邪������ƁA��]�œy�Ɖ������ĐՂɁA������R�Ƃ������ނ��́A�����ɉ��̂����Ԃ钆����e�����߂ĉE������������́A�܂��ɐ푈�̂��ߌ��ł���B �@�I���O�\�ܔN���o�������A�e���ʂ̏���ɂ���āA�����ɐV�����l���s��P�}�������������̗�̈��炩�Ȃ邱�Ƃ��肢�A�㐢�ߎS�Ȃ�푈�̐�ł������A���E�i�v�̕��a���F�O������̂ł���B�@ �@���̕��͓���ł����A�Ƒ��̐l�����ƂƂ��ɓǂ�ł��������B�������͐푈�̑̌��͂���܂���B�������A���̕��a�ȎЉ����邽�߂́A�푈�̂��Ƃ����A�l���������Ƃ��厖���Ǝv���܂��B���E�ł͍����Ȃ������퓬��Ԃɂ��鍑�X������܂��B�����납�炢�낢��Ȃ��Ƃ��l����@���厖�ɂ��Ă����܂��傤�B          |
||||||
6��11���i���j 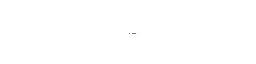 �@�@ �@�@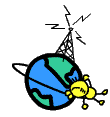 ��1�N�����@�u�킽���̃}�[�N�v�@�@�N�������ł�������Ǝ����̂��C�ɓ���̃}�[�N��`�����Ƃ��ł��܂����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@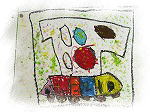  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@   �@ �@   �@ �@ �@ �@ ��4�N�����u�t�̑��ԁv�`�˂������Ă������낢�ȁ` �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��3�N�����@�u���ł������@�F�ł���ɂ��́v�@�@4�l�̃f�U�C������ɂȂ�܂��� �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@          |
||||||
| 6��7���i�j �@  �@ �@ �@ �@ �݂�Ȃ̗͂����킹���^�����@�@  �@6��2���i�y�j�ɉ^��������{���܂����B��^�A�x�ォ����K�Ɏ��g�݁C�����͂��ꂼ�ꂪ���K�̐��ʂ�]���Ƃ���Ȃ��������C�q�ǂ������̋C�������f���ɂ����ꂽ�ƂĂ����Ă��ȉ^����ł����B�W�芈����5�E6�N�����O���̏������瓖���̊����ɐϋɓI�ɓ����C�D��ۂ������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �@1�N����4������܂�2���������o���Ă��Ȃ��̂ɖ{���ɂ悭��������Ǝv���܂��B���N���w����q�����̊����̊��̐�������܂����B�܂��C�k������\���Ȃǂ�������̂��Ƃ��悭���Ȃ��Ă��܂����B�̒��������C��ϗ��h�ł����B Program 4�@3�N�\���u�Ԋ}�����v �@�\���̃g�b�v�o�b�^�[�B��ς��Ă��ȗx����I���Ă���܂����B���ɉԊ}�̏�ʼn̂������ł����B���₢�����ƌ��܂����|�[�Y�C�{���ɂ悭���K������Ă��āC�����悤�ȓ����ł����B3�N���̎q�ǂ������̑f���őO�����ȋC�������`����Ă��܂����B Program 7�@2�N�\���u�����̂��q�\�[����2012�v �@�q����������̂悢�����ł����B���`�ړ����X���[�Y�ŁC�C�������������͋����\���ł����B2�N���̎q�ǂ������͍����̂��߂ɑ務�������܂����B���ƒ���x�ݎ��ԂɎ��������ŋ��Ȃǂ������グ�Ă��܂����B�Ō�Ɍf����ꂽ2���̑務���͌����ȐF�����œh���C2�N���̂܂Ƃ܂�ƐS�ӋC�������܂����B Program 10�@1�N�\���u���͂悤�I�V���C�j���O�E�f�C�v �@�Z�����K���Ԃł������ƂĂ����Ă��ȗx��������Ă���܂����B���̓�������������ƕ\������Ă��āC1�N���̈ꐶ�������ƌ��C�����悭�����ꂽ�_���X�ł����B�ړ�������4�̉~��`���̂���Ϗ��ŋ����܂����B���ꂩ����͂����킹�Ă�����Ă����܂��傤�B Program 16�@4�N�\���u�G�C�T�[2012�v �@��Â���̃}�C���ۂƂƂ��ɉ��Z�����܂����B����̃��Y���ɂ̂�C�����������������Ƃ��Ȃ��C����l���y���܂��Ă���܂����B��������4�N����������C�͋����Ƒ傫�ȓ����Ŏ��͂������ɂ��߂��܂����B Program 19�@5�E6�N�\���u�����܂��傤�I�킽�������́w�Ȃ���x���I�v �@�Ō����߂�����̂ɂӂ��킵��5�E6�N���̑g�̑��ł����B��l�C��l�C�O�l�Ə��X�ɐl���𑝂₵�C�\����������܂�C���ʂȓ��������ЂƂȂ������Ȃ��̂ł����B�S���ɂ��s���~�b�h�͂��炵�������ł��B���ł����������ł�������Ǝx����l���������āC�����Ƃ���ŋC�𗎂��������ăo�����X���Ƃ��Ă���l�Ȃǂ��ꂼ��̖������ʂ����Ȃ���C�ЂƂ̃s���~�b�h�����肠���܂����B�{���Ɍ����ł����B �@�V��ɂ��b�܂�C��l�ЂƂ肪�͂Ǝv�����o���ꂽ���炵���^����ł����B�^����ŋ��͂������C��܂������C�x���������Ȃ��܂Ƃ��J�����ꂩ���1�N�ł���ɋ������Ă����Ă��������B �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ ��ʈ��S�������s���܂����@�@�@  �@6��5���i�j��2���ڂɒ�w�N�C3���ڂɍ��w�N�̌�ʈ��S�������s���܂����B���N�̓N���l�R��}�ւŗL���ȃ��}�g�^�A�̕��������Ă̌�ʈ��S�����ł����B�P�`3�N���͊w�N���Ƃɕ�����āu���p�P���v�u�W���w�K�v�u���v��3�̓��e�����Ԃɉ���Ċw�K������e�ł����B���w�N�́u���v�̑���Ɂu���]�Ԃ̏����v�ł����B �@���p�P���ɂ͎��ۂ̑�}�֔z�B�Ŏg���Ă���Ԃɑ�\�̎�������荞�݁C�^�]���Ȃ���Ԃ̂��ɂ���l�������邩�ǂ������m���ߍ����܂����B���Ȉʒu�������Ԃł������C�Ԃ̋߂��ɂ����w�N���炢�̏��w�Z  ���ƌ����ɂ����Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂����B�u�Ԃ̉��Ƀ{�[���Ȃǂ������Ă������Ȃ�C��Ɉ�l�łƂ�ɍs���Ȃ����ƁB��肽���Ƃ��͎���̑�l�̐l�ɕK�����݂܂��傤�v�Ƃ������b�Z�[�W������܂����B ���ƌ����ɂ����Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂����B�u�Ԃ̉��Ƀ{�[���Ȃǂ������Ă������Ȃ�C��Ɉ�l�łƂ�ɍs���Ȃ����ƁB��肽���Ƃ��͎���̑�l�̐l�ɕK�����݂܂��傤�v�Ƃ������b�Z�[�W������܂����B�@�W���w�K�ł͂��낢��ȕW��������܂����C�W�������Ȃ���l���܂����B�C�Â����Ƃ́C�������͕W�����킩���Ă���悤�ł��܂�킩���ĂȂ��Ƃ������Ƃł��B���]�Ԃ��~�߂Ă͂����Ȃ��W���C���]�Ԃ̉��f�тȂǓ�����̐����ɕK�v�Ȃ��̂͊o���Ă����K�v������ł��傤�B �@���]�Ԃ̐����������ɂ��Ă����Ő��������Ă����܂��B �@�s���]�Ԃɏ��O�ɂ͂������`�F�b�N���悤�t  �@�@1. �^�C���ɋ�C���͂����Ă��܂��� �@�@2. �u���[�L�͂悭�����܂��� �@�@3. ���C�g�͓_���܂��� �@�@4. �x���͂悭�Ȃ�܂��� �@�@5. ���ˍނ͉��ꂽ���ꂽ�肵�Ă��܂��� �@�s���]�Ԃ𗘗p����Ƃ��̃��[���ɂ��Ċw�т܂��傤�t �@�|�C���g�P�@�u���]�Ԃ͎ԓ��������v �@���]�Ԃ͎ԓ��̍����Ɋ���Ēʍs���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��C���]�Ԃ͓�{���̕W���i���s�җp�H���сj������ꍇ���̂����C�H���т�ʂ邱�Ƃ��ł��܂��B �@�|�C���g�Q�@�u���]�Ԃ�������ʍs�ł���ꍇ������v �@���̇@�`�B�̏ꍇ�ɂ́C���]�Ԃ�������ʍs���邱�Ƃ��ł��܂��B�������C�����̒�������ԓ����̕��������s���C���s�҂̖W���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���s�҂̒ʍs�̖W���ɂȂ�悤�ȏꍇ�͈ꎞ��~�C�܂��͎��]�Ԃ���~��ĉ����ĕ����܂��傤�B �@ �����ʍs�������W��������ꍇ �A �^�]�҂��u13�Ζ����̎q�ǂ��v�u70�Έȏ�̍���ҁv�u�g�̂̕s���R�Ȑl�v�̏ꍇ �B �ԓ��܂��͌�ʂ̏���݂Ă�ނ����Ȃ��ꍇ �@�|�C���g�R�@�u�q�ǂ��̓w�����b�g�����Ԃ�܂��傤�v �@�@���]�Ԃł̃P�K�̑����͓����̃P�K�ł��B13�Ζ����̎q�ǂ������]�Ԃɏ�Ԃ���Ƃ��́C�ی�҂̕��͎q�ǂ��ɏ�ԗp�w�����b�g�𒅗p������悤�ɓw�߂܂��傤�B �@�|�C���g�S�@�u���]�Ԃ���ʎ��̂��������ΐӔC�����܂��v �@�@���]�Ԃ�������v���낤�ƁC�y���C�����ł���ƁC�����҂��o���悤�ȑ傫�Ȏ��̂ɂȂ��邱�Ƃ�����܂��B���]�Ԃ��ԗ��̒��Ԃł���ȏ�C���̂��N�����đ��肪�P�K�������ꍇ�Ȃǂɂ́C��Q�҂̉Ƒ��ɑ��đ��Q�����ӔC��Ȃ���Ȃ�܂���B �@���̂͂��N���邩�킩��܂���B�����Ă���Ƃ��Ɍ����_��Ȃ���p�ŎԂɊ������܂�鎖�̂�����܂��B�܂��C���]�Ԃɏ���Ă���Ƃ��ɎԂƐڐG������C�l�ƂԂ������肷�邱�Ƃ�����܂��B�����납�玩�]�Ԃ̓_����������C��ʃ��[���ɑ������������⎩�]�ԑ��s�����Ă��������B�����̖��͎����Ŏ�邱�Ƃ��厖�ł��B �@���ƒ�ł���ʈ��S�ɂ��Ĉ�x�������b�������Ă��������B���̂��N�����Ă���ł͒x���ł��̂ŁC�����납��̌�ʈ��S�ւ̈ӎ��Â�����s���Ă��������B 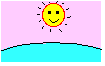 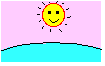 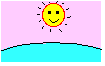 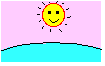 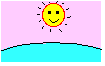 |
||||||
5��28���i���j �@  �@ �@ �@ �@ �h�{���@����Ƃ̎��Ɓu�H�ו��Ƃ��炾�v�@�@  �@���N�͑��m�������w�Z�����̏�h�{���@�ɖ��T�Ηj���ɗ��Ă��������C���H��H��ɂ��Ďw�������Ă�����Ă��܂��B�H��Ƃ́C�H����H�����o�����X�悭�H�ׂ邽�߂̂��܂��܂Ȓm����g�ɂ��邱�Ƃ�H�i�̑I�ѕ����w�Ԃ��ƁC�H���̊��ȂǁC�L������Łu�H�v�ɂ��Ċw��C�l�����肷�邱�Ƃ������܂��B���̐H��͒�w�N�ł͍͔|�������܂߂āC�����ȂŊw�K�����Ă��܂��B���w�N�ł͎�ɑ����w�K�ōs���܂��B���w�N�ł͉ƒ�Ȃ𒆐S�Ɋw�K��i�߂܂��B �@5��15���i�j�͏��搶�̎w����2�N���̐H��Ɋւ���w�K���s���܂����B�ǂ�Ȋw�K���s��ꂽ�����Љ�����Ǝv���܂��B �@�܂��͌����Ȃ������g���āC���̔��ɓ����Ă����Ȃǂ�������Ă��Ă�Ƃ������Ƃ��s���܂����B���イ��C�ɂ�C�卪�C���C���߂��C�j���ł����B�����̖�Ȃǂ͂��ׂĂ��̓��̋��H�Ɏg����H�ނŁC���߂���j���͎q�ǂ������ɂ͂Ȃ��݂̂Ȃ����̂ł��Ă�̂ɋ�J���Ă��܂����B������āu���ׂ��̑��̃}���\�����v�Ƃ������ŋ������āC�l���܂����B�H�����o�����X�悭�Ƃ��Ă���A���p���}���C���َq�����H�ׂĂ���h�L�������C�������H�ׂĂ���o�C�L���}�����}���\�������܂������C�����ɑ���Ȃ��Ȃ����̂��h�L�������ŁC�o�C�L���}�����S�[���ڑO�œ|��Ă��܂��܂����B���̂��Ƃ���q�ǂ������́C�H�ו��̓����ɂ��čl���܂����B �@��������́u���炾������v���������邱�ƁC��́u���炾�𐮂���v���������邱�ƁC���͂��p���́u�G�l���M�[�̂��Ɓv�ɂȂ邱�Ƃ���C�D���������������ł��H�ׂ�ƌ��C�Ȃ��炾������邱�Ƃ��m�F���C�Ō��3�l�Ɏ莆�������C�����̍l����v����`���܂����B  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
5��16���i���j �@  �@ �@ �@ �@ �@5��21���̒��C���H���N����܂� �@2012�N5��21���i���j�̒��C���H���N����܂��B���������Z��ł���l���s�s���ŋ����H�������܂��B�l���s�ł�1080�N12��14���ɋ��H�����Ă���C����͂Ȃ��932�N�Ԃ�ł��B����̋@������Њw�K�ɂȂ������ƍl���C�����H�̎��g�݂��s�����Ƃɂ��܂����B �@�H�̌����n�߂�6��17�����炢�ł��B �@���H��7��24������7��33���ɂ����Č����܂��B �@�H�̏I����8��55�����炢�ł��B �@���̂悤�ȋ@���厖�ɂ������ƍl���C�w�Z�ł͓��H�ɂ��Ă̘b����H�ώ@�O���X�������g�݂��s���܂��B�ώ@�ɂ��Ă͑����œo�Z�O��o�Z�r��ł̋��H�ƂȂ�܂��̂ŁC�W�c�o�Z�̏W��������x�点�ώ@�����ƒ�ł��Ă���o�Z�Ƃ����悤�ɂ����Ă��������܂����B �@���H�ɂ�����C����ꋳ�E�����l���s�s�����ق̈ɓ��搶�����������C���H�ɂ��Ă̊w�K�Ǝ��������S�Ɋώ@������@�Ȃǂ��w�сC���ۂ̊ώ@�O���X�����܂����B���̒��Ŋw�K�������e�������Љ�����Ǝv���܂��B �@? ���H�ɂ�3��ނ���C�F�����H�C�����H�C�������H������B �@? ����́C���{�̐l����3����2���Z�ޒn��ŋ��H�����邱�Ƃ��ł���B �@? ���̒��a��1�Ƃ���ƁC���z�̒��a��400�ł���B�܂��C���ƒn���̋������P�Ƃ���ƁC���z�ƒn���̋�����400�ł���B���̂悤�ɋ��R���d�Ȃ�C���z�ƌ��̔䗦�͉�����Ƃ�����B �@? ���S�Ȋώ@���@���厖�ł���B���z�ڂ݂���C�]�����C�ʐ^�̃t�B�����C���~���Ȃǂő��z�������肵�Ă͂����Ȃ��B �@? ���H�t�B�����ł�30�b�����x�ł���B �@? �ؘR�����s���z�[�����g�����ώ@�͈��S�ŁC�Ȃ��Ȃ��������낢�B �i�ڂ����́C���ʂ̏��p�����悭�ǂ�ł��������B�j �s�����̓��ʒʉ߂�������t�@�@  �@ �@6��6���i���j�ɂ́u�����̓��ʒʉ߁v�Ƃ����V�̃V���[�����邱�Ƃ��ł��܂��B���z�̕\�ʂ������ȋ������ʂ�߂��Č����錻�ۂŁC�����105�N��ƂȂ�܂��B���H�ώ@�p���K�l�͂��̂Ƃ��ɂ����p�ł��܂��B �@�u�����̓��ʒʉ߁v�́C���z�̏���C�����̏����Ȋۂ��e�������Ă������ۂł��B�n�����猩�đ��z�̎�O���C�������ʂ�߂��邽�߂ɋN���܂��B����́C���z�Ɍ��������ۂ���邽�߁C���Ɍ����܂��B�����̏ꍇ�́C�n������̋���������艓�����߁C���z��ɏ����ȊۂƂȂ��Č����܂��B���a�ŁC���z�̖�30����1�ł� �@�ʉߎ��ԑт����Ԃɓ�����n����̏ꏊ�Ȃ�C�ǂ�����ł��ϑ��ł��܂��B���{�̏ꍇ�C�S���I��6��6���i���j�̌ߑO7�����O�ɋ����̊ۂ��`�����ʂɓ���C��6���Ԕ������C�ړ����܂��B�����H�ɔ�ׂāC�ϑ��ɗ]�T������C���Ƃł��ώ@���������Ǝv���܂��B �@�@           |
||||||
4��25���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�ꊈ�����͂��܂�܂���   ����23�N�x����V�w�K�w���v�̂����S���{����C5�E6�N�ɏT1���ԉp�ꊈ������������܂����B���N�͂���2�N�ڂƂȂ�܂��B�{�Z�Ƃ��܂��Ă��C�X�Ȃ�p�ꊈ���̏[����ڎw���Ă��܂��B�{�N�x�͖ؗj����5�E6�N�̉p�ꊈ�������{���܂��B�N�Ԏ�����35���ԂŁC�l���s�s����ψ���̉p��w�����~�V�F���搶��25���Ԏ��Ƃ�S�C�ƈꏏ�ɍs���܂��B�܂��c���10���Ԃ������ʔ��u�t�̐�搶�ɉ�����Ă��������āC�S�C��TT�ʼnp�ꊈ����i�߂Ă����܂��B1�N������4�N���ɂ��ẮC�l���s�s����ψ���̕��j���āC�e�w�N�N��4���Ԃ̉p�ꊈ�����C�����O�����p���ă~�V�F���搶�ƒS�C�ƂŎ��{���Ă����܂��B �@���w�Z�̉p�ꊈ���́u�����𒆐S�ɊO����Ɋ���e���܂��銈����ʂ��āC����╶���ɂ��đ̌��I�ɗ�����[�߂邱�ƁB�ϋɓI�ɃR�~���j�P�[�V������}�낤�Ƃ���ԓx���琬���C�R�~���j�P�[�V�����\�͂̑f�n��{�����ƁB�v��ڕW�ɉ����𒆐S�ɂ����������s���܂��B����āC�P��╶���͎��Ƃň����͂��܂����C��������ǂ�ł���w���͍s���܂���B �@���N�x�ŏ��̃~�V�F���搶��5�N���̎��Ƃ��Љ�܂��B4��19���i�j�͎��ȏЉ�̓��e�ł����B My name is �iMichelle�j. I am 10(11) years old. I am from �iKitayama,�@Asake, �@Satsuba �E�E�E�j ���w��C���[�N�V�[�g�Ɏ����̏Љ�����[�}���ŏ����C�C���^�r���[�Q�[�����s���܂����B���߂Ăōŏ��͌˘f���Ă���q�ǂ����������܂������C���������犵��Ă��āC��ϊy�������Ɍ݂��Ɏ�����������C�T�C�������킵�Ă��܂����B���̌�́C�~�V�F���搶�Ƃ̈�Έ�̎��ȏЉ���s���܂����B�搶�͕��D�l�`��p�ӂ��C������p�X���Ȃ���R�~���j�P�[�V��������荇���S���̔��\���I���܂����B �@�~�V�F���搶�Ɏ��ȏЉ�������Ă��炢�܂����̂ŁC�Љ�܂��B �@Hello! My name is Michelle Brown. I am from San Diego, California. This is my second year living and working in Japan. My hobbies include surfing, snowboarding, and camping. I am also studying kanji! I love teaching at Shimono Elementary School! �i����ɂ��́I�@���̖��O�̓~�V�F���E�u���E���ł��B���̓J���t�H���j�A�B�T���f�B�G�S�������Ă��܂����B���N�͓��{�ŏZ�݁C�����悤�ɂȂ���2�N�ڂɂȂ�܂��B���̎�̓T�[�t�B���C�X�m�[�{�[�h����уL�����v�Ȃǂł��B����ɁC���͊���������Ă��܂�!�@���͉��쏬�w�Z�ŋ�����̂��ƂĂ��D���ł��B�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1�N�����}�����   �@4��20���i���j2���ڂɁu1�N�����}�����v���Â��܂����B�A�[�`�̒���1�N�������ꂵ�܂����B6�N������̊��}�̂������Ɖ̂��݂�Ȃʼn̂��܂����B2�N�������l�ЂƂ�Ƀv���[���g����n����܂����B �@���̌�́C�w�Z�́��~�N�C�Y���݂�ȂŊy���݂܂����B�]�����Ă����搶�̐��C�Z�R�C�A�̎��̍����C�w�Z�̗��j�ɂ��Ȃ��e�ł����B1�N���ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ���������悤�ł��B�Ō��1�N������̂���̌��t�ł����B�u���肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ������t�̒��ɁC�����낢�낢��Ƃ����b�ɂȂ��Ă���v���������܂����B �@�w�Z�݂͂�Ȃőn��グ�Ă������̂Ȃ̂ŁC�܂��͎������y�������Ƃɂ�����Ă��������B���݂͂�Ȃł�������ɂ���y��������������Ă��������B�݂��ɐ������������C�v�������������Ă����܂��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�w�Z�Â���r�W�����̋�̓I�Ȏ��g��   �@�O��̊w�Z�����Łu���쏬�w�Z�w�Z�Â���r�W�����v���f�ڂ��܂����B���̋�̓I�Ȏ��g�݂̃|�C���g�ɂ��č��`���������Ǝv���܂��B �s������j����t �P�@�킩����ƁE�y�������Ƃ̑n�� �E 1�N���`6�N���̎Z���̎��Ƃ����ׂ�TT�Ȃ����͏��l���ōs���܂��B �E 1�N����2�N���̍���Ȃǂɂ͂�����l�̋��t������C���Ǝx�����s���܂��B �E ����10���ԃ^�C���ł͓Ǐ���w�͕�[���s���܂��B�w�N�̔��B�i�K�ɉ��������e���H�v���Ă����܂��B �E 3�N����5�N���ł͍���E�Z���̓��B�x���������{���܂��B���w�N�͊w�͂�L���鎞���ł�����̂ŁC2�N�Ԃ̌��ʂ������Ӗ��Ō�����{�Z�Ǝ��Ŏ��{���܂��B5�N���i�Z���͖{�Z�Ǝ����{�j�͍��܂ł̊w�K�̏K���̌������ƍ��w�N2�N�Ԃ̌��ʂ������Ӗ��Ŏ��{���܂��B �E �����ʔ��u�t�̓������s���C3�N���̏��ʁC���3�E4�N���̐��j�C5�E6�N���̉p�ꊈ���̏[����}��܂��B �E �}���َi�������p���C�}�����̐�����u�b�N�g�[�N�C�}�������Ȃǂ̏[����i�߁C�}�������p�y�ѓǏ����̊�������}��܂��B �E �̈�̖����Ԃ�5���ԉ^����������C�^���̊y�����Ɖ^���ʂ𑝂₵�Ă������g�݂�i�߂܂��B �E �삯���C�Ȃ�Ƃт̋����T�Ԃ�݂��C�̗͂Â����i�߂܂��B �E �����ʔ��u�t�̊��p�C���j���������{���C�����S����25���̉j�͂�ڎw���܂��B �Q�@�S�̋���̏[�� �E 2�w���ɂ����ߒ��������{���܂��B�����߂⍷�ʂ��Ȃ����̔c������������ƍs���C��l�ЂƂ�̎v������ɂ����Ȃ��܂Â����ڎw���܂��B �E �X�N�[���J�E���Z���[�����p���C�ی�҂̊F����̎q��Ă̔Y�ݑ��k�Ȃǂ̋��瑊�k�̐��̏[����}��܂��B �R�@�l�Ƃ̏o����ɂ������犈���̏[�� �E �n��̓����������̌�������i�߁C�O���u�t�Ȃǂ�ϋɓI�ɓ������C�w�K�̏[����i�߂܂��B �E �w�Z�s����w�N�s���C���犈����ʂ��C���s�ψ��Ȃǂ�g�D���Ȃ���C�q�ǂ�����̓I�ɍl���C���f���C�s����������e�����߂܂��B �s�o�c���j����t �@�@�ƒ��n��̐M���ɉ�����w�Z�Â��� �E �w�K�x���{�����e�B�A�i�ǂݕ������C�}���Ȃǁj�̐ϋɓI�ȓ�����}��܂��B �E �z�[���y�[�W�̍X�Ȃ�[����}��܂��B �E �w�Z�Â��苦�͎҉�c�▯���ψ��E�����ψ�����Ƃ̍��k����J�Â��C�����ʂ̕�����̈ӌ��𑽂������C�w�Z���P�ɂȂ��Ă����܂��B �E ���Ƃ��[�������邽�߂ɁC���E�����C�ɑ�w�������̊O���u�t�������C���Ƃ̍H�v��w�͌���ɓw�߂܂��B �E �ۗc�����A�g��i�߁C�𗬊�������ђ��w�Z���t�ɂ��o�O���Ƃ��s���܂��B |
||||||
4��19���i�j �@�@�s�w�Z����ڕW�t �@�@�@�@�@�@�@�@�u�����l���@�������������q�ǂ��v �@�@�@�`������Ƃ��ɐ����钆�ōl���C���悭�����悤�Ƃ���q�̈琬�` �k�߂����q�ǂ��̎p�l �@�@�@���Ƃ��ɐ����邱�Ƃ��v���q �@�@�@���m�邱�Ɓ@�w�Ԃ��Ɓ@�l���邱�Ƃ��y���ގq �@�@�@�����N���ɂ���q �@4��6���i���j�n�Ǝ��C���w�����I���C66���̐V1�N�����}���܂����B4��10���i�j�ɂ͋��H���n�܂�C���Ƃ��X�^�[�g���܂����B���C�Z��O�ŗ����Ă���ƁC6�N���̎�����1�N���̃����h�Z���������Ă����āC���Ɏ�������ă��[�h������C�ǒ����������Ȃ��琺���������肵�Ă���p�Ȃǂ�����܂����B�܂��C��������ł��������C�ɂ����Ă��ꂽ��C������1�N�����x�݂���Ɨl�q��`���Ă��ꂽ�肵�܂��B���w�N�̎q�ǂ������ɂ͎��o�ƐӔC���������܂����B��w�N�̎q�����͎��ƂŎ����̎v����f���ɏo���Ă��āC���S���������Đ����𑗂��Ă���悤�Ɏv���܂����B��ς悢�X�^�[�g����܂����̂ŁC1�N�Ԃ������āC�w�N���ĂȂ��荂�߂�����Ȃ��܂ɂȂ��Ă�����悤�ɂ݂�Ȃœw�͂����Ă����܂��傤�B �@���āC���쏬�w�Z�̊w�Z����ڕW�́u�����l���@�������������q�ǂ��v�ł��B�q�ǂ������͓��X�̐�����̌��C�o�����炽������̂��Ƃ��w��ł����܂��B���܂��������Ƃ����܂������Ȃ����Ƃ������ς�����ł��傤�B��l�ł͂ł��Ȃ��Ă��C�Ȃ��܂ƈꏏ�ɂ���ł��邱�Ƃ������Ă���ł��傤�B���̂悤�ɁC�w�K�⊈����ʂ��āC�w�э����C������荇���C�炿�����W��厖�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B�����āC�����̂悳�ɋC�Â��C�������D���ɂȂ�C����̖���`���C��̓I�ɐ�����q�ǂ���������悤�ɁC���E����ۂƂȂ��ēw�͂����Ă܂���܂��B��N�Ԃ�낵�����肢���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���P���������Ȃ��܂���  �@ �@ 4��13���i���j3���ڂɒn�k�ƉЂ�z�肵�����P�������{���܂����B����̔��P���̖ړI�́C���o�H�̊m�F�ł��B�n�k��Ύ����N�����Ă��p�j�b�N�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁC�����̐g�̈��S���m�ۂł���悤�ɔ��P�����s���܂����B�q�ǂ������̌�����͂悭���̌��t��������܂��B����́C�u���͂����v�ł��B���̌��t�͐T�d�ȍs��������悤�ɒ��ӂ𑣂����̂ł��B�u���͂����v�́u�����Ȃ��C����Ȃ��C����Ȃ��C�߂�Ȃ��v�̓��������Ƃ������̂ł��B ����̎w���̏d�_�͈ȉ��̂��Ƃł��B �i�P�j��������������Â��ɕ������C���̉��ɔ���B �@�i�Q�j�搶�̎w���ɏ]���C���ꏊ�Ɉ��S�Ɉړ��ł���B �@�i�R�j���ꏊ�ł͐Â��ɑ҂��Ƃ��ł���B �n�k�͂��ǂ��ŋN���邩�킩��܂���B�q�ǂ������ɂ͂��̂��Ƃ��l���āC�n�k���N�����ꍇ�͕���d���ȂǓ|�����̂��痣��邱�ƁC�w�Z�ł��|��₷�����̂̂��ɂ��Ȃ����ƂȂǂ̘b�����܂����B�܂��C�厖�Ȃ͎̂����Ŕ��f���邱�Ƃł��B���̔��f���ł���悤�ɍ���h�Њw�K���v��I�ɐi�߂Ă��������ƍl���Ă��܂��B���ƒ�ł��n�k��ЂȂǂɔ����āC�ƒ�ł̔��̎d����Ƌ�̓]�|�h�~�ɂ��āC�m�F�����Ă����Ă��������B |
||||||
| 4��6���i���j    �@���邢�傫�ȗ��ɂȂ낤�I�@�@  �@ �@�V1�N���݂̂Ȃ���C�����w���߂łƂ��������܂��B �@�݂Ȃ����쏬�w�Z�ɓ��w���Ă���̂�2�N������6�N���̎q�ǂ������͐S�҂��ɂ��Ă��܂����B4��5���i�j�ɂ͐V6�N��������������o�Z���C�V1�N���̋�������Ȃǂ̑|���E�����J�ɂ��Ă���܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �u���邢�傫�ȗւɂȂ낤�v�Ƃ������t�͖{�Z�̍Z�̂ɂ���܂��B�ƂĂ��������t���Ǝv���܂��B�w�Z�݂͂�Ȃ��W���C�w�ԏ�ł��B��l�ЂƂ肿�����Ă��āC���̂��������~�ߍ����C�݂��ɕ₢�����C�����Ɍ������Ă����C�����āC��l�ЂƂ�̂悳���P����������Ȋw�Z�ɂ��Ă��������ƍl���܂��B��l����l�C��l���O�l�ƒ��Ԃ𑝂₵�C�傫�ȗւ��݂�Ȃőn��グ�Ă����܂��傤�B �@ �@�@�Z���搶���ƂĂ��D���Ȏ�������̂ŁC�Љ�܂��B �@�@�@�@�@�����D �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�O�Y �@�@�@�@�����Ă����� �@�@�@�@���x�� �@�@�@�@�����ƍ��� �@�@�@�@���x�ł� �@�@�@�@�ł��グ�悤 �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@������ �@�@�@�@�肢���Ƃ̂悤�� �@�݂Ȃ���́C�����D�ŗV���Ƃ�����܂����B���ꂢ�ɐ܂�܂���ꂽ�����D�ɑ��𐁂����݁C��ꂻ���ɂӂ���Ƃ��̊��o�����ڂ��Ă��܂����B�܂��C�����ł��グ�悤�Ƃ��āC�����������Ă����܂��オ�炸�C�t�ɂ�Ԃ�Ă��܂����Ƃ�����܂��B���܂��ł��グ��ɂ͂�͂�R�c�Ǝ����D�Ɏv�����悹��K�v������ł��傤�B ���Ȃ��������������g�̎����D�����N��N�����Ă��܂��ł��グ�Ă��������B��l�ЂƂ�̊肢����������ƍ�(��)�߂āI     |
||||||
| �@ | ||||||
| �l���s�s���@���쏬�w�Z �O�d���l���s�s������475-1 Tel 059-336-2000�@�@�@�@�@Fax 059-336-2001 Copyright Shimono Elementary School |
||||||