| |
||||||
11��8���i���j �@�Z�R�C�A�w����PTA����u�����@ 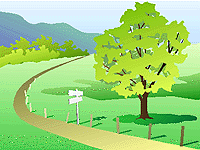 �@11��23���i�y�j�ɃZ�R�C�A�w���Ƃ��Ċw�Z���J���s���܂��B�Q���Ԗڂ͐l������̈�Ƃ��Ă̓����̎��Ƃ��s���܂��B�R�E�S���Ԗڂ�PTA����u����ƎO�����w�Z���y��ɏo�ꂷ��U�N���̍������\��̈�قōs���܂��B�T���Ԗڂ܂Ŋw�Z���J�����Ă��܂��̂ŁC�Q�w���������߂�������̂��q�����w���̗l�q��������育�����������B �@10��45������́u����u����v�́C���쏬�w�Z�ɂ������̂����V��Y����ɗ��Ă��������܂��B�搶�͕��䌧�ŏ����w�Z�̋����C���w�Z�Z���߂܂����B���̋��������Ƃ��̌�̃T�|�[�^�[�����̑̌�����ɁC�u�]�܂����ƒ닳��̂�����@�`������w�͂ƌ����Ȃ��w�͂��`�v���e�[�}�Ɍ���Ă��������܂��B����̎��s�k�荞�݂Ȃ���́C�����Ə��̓��e�B���l�ȉ��l�ς̒��ŁC�q��ĂɔY�ސe�����Ɍ����Č��C������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ă��Q�������������B �@�����ɍZ���}�H�W���̈�قŊJ�Â����Ă��܂��̂ŁC�����Ă������������B �@  �@�ƊԂ����������n�܂�܂��� �@�ƊԂ����������n�܂�܂����@11��7���i�j���20���x�݂ɋƊԂ��������n�܂�܂����B���Ԃ�12��3���i�j�܂ł�15��ł��B�ƊԂ������́C�����̑��i2���j���N���X�ŕ���ŃW���M���O�i1���j���e���̃y�[�X�ő���i5���j�����̌�N���X�̏ꏊ�ɂ��ǂ�C�����̑��̓��e�ōs���܂��B �@12���S���i���j�́C�u�������L�^��v�i�\�����F5���j�ł��B���N���^����y�ъw�Z���ӂ𑖂�܂��B��w�N��900���C���w�N��1200���C���w�N��1800���𑖂�܂��B ���̂悤�Ɏq�ǂ������͑傢�ɑ̂�b���C�����Ȃ�̂߂��Ă������Ĉꐶ�����Ɏ����ւ̒���Ɍ����Ď��g�݂܂��B�L�^����͉�������낵�����肢���܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
| 11���P���i���j    �@�o���厖�ɂ����C�w���s�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�\�@�_�ˁE���s�ւ̗��@�\ �@10��10���i�j�E11���i���j�̓����ŁC�U�N���͐_�ˁi���j�E���s�ւ̏C�w���s���s���܂����B����ڂ̐_�˂̓L�b�U�j�A�b�q���E�l�Ɩh�Ж����Z���^�[�C����ڂ̋��s�͋��t���C���s�䏊�C�m���@�O��C���R�E�G�U��C��������K�ˊw�K��ς�ł��܂����B �@�{�N�x�̏C�w���s�́C�������⎩�Ȏ����C�����ɂȂ���L�����A����̈�Ƃ��ăL�b�U�j�A�b�q����K��܂����B�܂��C�l�Ɩh�Ж����Z���^�[�ł͑�k�Ђ�h�Ђɂ��čl����@��������܂����B���s�ł͐��E��Y����j�C�����ɂ��Đ[���w�Ԃ��߂ɁC���s�ό��{�����e�B�A����Ƃ̔Ǖʕ��U�w�K�����{���܂����B���̂悤�ɂ������̖ړI�������ėՂC�w���s�ł������C�U�N���̎q�ǂ������͉����w�тƂ��Ă����̂ł��傤���B �s�P���ځ@�_�ˁt �� �L�b�U�j�A�b�q���� �@���C�V��10���Ɋw�Z���o�����āC9�F40���ɃL�b�U�j�A�b�q���ɒ����܂����B�L�b�U�j�A�̒��ł́C�Q�`�R�l�̃O���[�v�ɕ�����āC�q�ǂ������͎����̂��ړ��Ă̊�Ƃ̐E�Ƒ̌����s���܂����B���h�m�C��}�ցC���W�I�����C�f�U�C�i�[�C���z�ƁC�����H���C�z�e���}���C�}�W�V�����C�e���r�ԑg����ȂǁC��������̐E�Ƒ̌����ƂĂ��y�������ɂ��Ă��܂����B�e���r�ԑg����ł̓A�i�E���T�[�C�@�B����C�J��������C�f�B���N�^�[�Ȃǂ̖����ɕ�����āC�N�C�Y�ԑg����邱�Ƃɒ��킵�Ă��܂����B�V�i���I�͂�����̂̎��X�ɕς���ʂɎq�ǂ������͌��\���܂��Ή����ăX���[�Y�ɐi�s���Ă����܂����B���̂悤�Ȍo�����Ƃ����āC�d���̗���͂��Ƃ��C��l�ЂƂ肪�ƂĂ��厖�Ȗ������ʂ����Ă��āC���߂Ĉ�̂��Ƃ��ł������邱�Ƃ����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��C���A������グ�����M�Ɩ��������傫�������Ǝv���܂��B �@  �@ �@ �@ �@ ���l�Ɩh�Ж����Z���^�[�� �@2��50���߂��ɓ������C�l�Ɩh�Ж����Z���^�[�̑O�ŋL�O�ʐ^���B������C�Z���^�[�ł̊w�K�ɓ���܂����B �@�܂��́C�S�K�u�k�ВǑ̌��t���A�v�ɏ��܂����B1.17�V�A�^�[�̍�_�E�W�H��k�Ђ̒n�k�j��̂����܂������q�ǂ������͂ǂ̂悤�ɑ������̂ł��傤���B�U�����Ɏl���s�s�����̊�@�Ǘ����̏��c������������ۂɓ��C�E����C�E��C��n�k�ɂ��Ă̊w�K�����܂������C����̂��ƂƎq(��)�ǂ������͂ǂ̂悤�ɏd�ˍ��킹���̂ł��傤���B���̑�k�Ѓz�[���ł́C�����Ɏ���܂ł̂܂��Ɛl���ǂ̂悤�ȉۑ�ɒ��ʂ��������l���邱�Ƃ��ł��܂����B���ЂƂ����l����m�邱�Ƃ��ł��܂����B���̌�C�R�K�k�Ђ̋L���t���A�C�Q�K�h�ЁE���Б̌��t���A�ւƊK��i�߁C�q�ǂ������͔M�S�Ȋw�K��i�߂܂����B��蕔�����̉f����{�����e�B�A����̐����ȂǂɎ����X���C���Ԃ������߂��Ă������悤�Ɋ����܂����B �s��蕔�{�����e�B�A����Ƃ̏o��t 5������́C��_�E�W�H��k�Ђ�̌����ꂽ��蕔�{�����e�B�A�̍��X���炨�b�����������܂����B1995�N�i����7�N�j1��17���i�j�ߑO5��46��52�b�ɋN��������k�Ђ͒W�H�E��_�n��ɐr��Ȕ�Q�������炵�C���҂�6000�l�ɂ��y�т܂����B���X����͓������c�n��̓�t���w�Z�̂S�N���̒S�C������Ă��܂����B�܂��͊w���̎q�ǂ��T������n�܂��������ł��B10����ɂ͑S���������ł��邱�Ƃ��������������ł��B ���@A����͎q�ǂ������Őe�ʂ����ǂ��ē��k�̎R�`�֍s���C�u�����_�˂ɋA�肽���Ƌ����Ă���v�ƁC�e�ʂ̕��Ɠd�b�Řb���܂����B ���@B����͑��̖�^�s�̉��ݏZ��ɓ���C���Ǝ��ɂ͓�t���w�Z�ɖ߂��Ă��܂����B �@���̂悤�Ɉ�l�ЂƂ�̊w���̎q�̈��ۂ��m�F���������ł��B �@���ƂȂ�����t���w�Z�̎q�ǂ������Ɂu�q�ǂ������ɂ��ł��邱�Ƃ�����v�ƍl���C�{�����e�B�A���W���܂����B48�l�̉��傪����܂����B��8������20�����炢�͊w�Z�̎���̑|�������܂����B�w�Z�ē���͂��邱�Ƃ����܂����B�Z���̔����͊w�Z�ɏZ��ł����̂ŁC4���ȍ~�͌��������̉̂��̂��Ȃ��猨�������{�����e�B�A�����܂����B���̂悤�ɁC�q�ǂ������͎����������ł��邱�Ƃ����C�݂�ȂŐ������x�������܂����B16�N��ɂ́C�{�����e�B�A�������ς������o������C�����̓������߂�Ƃ��ɋ��t�̓���I�q�����������ł��B���X����̂��b�͂��ꂼ��ɂł��邱�Ƃ�����C�݂�ȂŎx�������Ƃ͉����C�Ƃ��ɐ�����Ƃ͉����������Ă��������܂����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �� �_�˔��F�V�[�p���{���� ���Ă��ȃz�e���ŁC�`��X�̓��肪�ƂĂ����ꂢ�ł����B�[�H�̃o�C�L���O�͍D���ȕ���H�ׂȂ���b���e�݂܂����B�����C�̓N���X���Ƃɓ���C�q�ǂ������̊y�������Ȑ����L���܂ŕ������Ă��܂����B  �@ �@ �@ �@ �s�Q���ځ@���s�t �@��7��30���Ƀo�X�̓z�e�����o�����C�r�����̏a������܂������C9��40���ɋ��t���ɒ����܂����B���ꂼ��̃o�X�̒��łX�l�̃{�����e�B�A�K�C�h����Əo��C���t���̌��w���s���܂����B�ړ��͈ꏏ�Ƀo�X�ōs���C���s�䏊�Ɍ������܂����B�䏊�̓����͂߂����Ɍ����Ȃ��̂ŁC�����a���͂��߁C���낢��Ȍ����̔z�u��뉀��������蒭�߂邱�Ƃ��ł��C�����[�����̂ł����B �@���H�͒m���@�߂��̘a����قŋ��s�Ȃ�ł͂̏��a���̗�����H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B���̌�́C�ǂ��Ƃɒm���@�̎O��ɓo��܂����B�}�ȊK�i����Ƌ��s�̒����݂���]���邱�Ƃ��ł��C�ƂĂ��K���ȋC�����ɂȂ�܂����B�O��̓����̓V��ł͔����Ă��间�̊G�����邱�Ƃ��ł��܂����B �@�O�����ɁC�ǂ��ƂɃ{�����e�B�A�K�C�h����Ɗy�����b���Ȃ���́C���R�U��ό����n�܂�܂����B����_�ЁE���m���E�Ԍ����H�ʁE�_���E�˂˂̓��E���䎛�E����̓��E��{���n�̕�E��N��Ȃǂ�ǂ��Ƃ̌v��ɏ]���ē��R�E�G�̋�C�������Ȃ���C���j�U����s���܂����B�Ō�ɐ������ɓ���C3��10�����ɉ��U�����āC�Ō�̔NJ����̂��݂₰�^�C���ƂȂ�܂����B �@�������ԏ��4��10������ɏo�����C6��15������Ɋw�Z�ɓ������܂����B �@�v��ʂ�Ɍ��w��w�K���ł��C�q�ǂ����������ꂼ��̏ꏊ�ňꐶ�����ɂ��Ă���p������C�Ǎs�������͂��Ȃ���ł����悤�Ɏv���܂��B�������C�\���ɂł������Ƃ����ƁC�X�̉ۑ���܂߁C�w�N�S�̂ō��߂Ă����Ƃ�������������Ǝv���܂��B�݂Ȃ���̂��ꂩ��̂����Ɋ��҂��܂��B ����̗��͑����̐l�����Ƃ̏o�������C�C�w���s�̖ړI�����̏o����������g�ɂȂ��邱�Ƃɂ���܂������C�C�w���s�Ŋw�тƂ������Ƃ����ꂩ��̎��Ȃ̐����⎩�Ȃ̐����Ɍ��т��Ă��������B�ƂĂ����Ă��ȏC�w���s���ł������Ƃ���������ƐS�ɍ���ł����܂��傤�B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  �@�T�N���u�J���m���ߍ��������R�����v �@�T�N���u�J���m���ߍ��������R�����v10��23���i���j�E24���i�j�Ǝl���s�s���N���R�̉ƂŁC�T�N���͎��R���������{���܂����B ����ڂ͂����ɂ��̉J�ł������C���Ԃ͗\��ʂ�u���R�ۑS�����v�u�I���G���e�[�����O�v���ł��܂����B   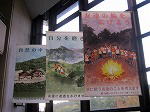 �� ���R�ۑS�����@�� �u���R�Ƃ́v�u���R�ۑS�������Ȃ��K�v�Ȃ̂��v�������Ŋw�K������C���R�ۑS�����ɏo�����܂����B��l��{�̂̂�����������C��l�ň�{�C�r���炢�̑����̖��܂����B��|���������ɉ^�сC���Ǝ}�ɐ蕪���C����������30�p���炢�̐d�ɂ��܂����B���͂��đ����ł����l�����͑��̃O���[�v����`���C�{���Ɋy������Ƃ��s���Ă���p����ۓI�ł����B  �@ �@ �@ �@ ���I���G���e�[�����O�� �@�J�̒��̃I���G���e�[�����O�ɂȂ�܂������C�ǂ̔ǂ��J���[�̐H�ނ����߂āC�|�C���g�ɂ���搶��T���ď��N���R�̉Ƃ̎R���s�����藈���肵�Ȃ���C�ꐶ�����ɕ����Ă��܂����B�J�łڂ�ڂ�ɂȂ����n�}�ŋ������Ă���ǂ����邩�Ǝv���C�n�}�Ƀr�j�[���������X���[�Y�ɕ����Ă���ǂ�����܂����B�����C�u���̖Ȃ�̖v�͓���炵���قƂ�ǂ̔ǂ��ł��ĂȂ��悤�ł����B�������C�݂�ȂŒn�}�����ē����m���߁C���͂��Ȃ���K���ŕ����Ă���p����q�ǂ������̂Ȃ���Ƃ܂Ƃ܂�������܂����B  �@ �@ �@ �@ ���L�����h���t�@�C���[�� �@�H���ł̗[�H�̌�C�J�̂��߁C�̈�قŃL�����h���t�@�C���[���s���܂����B�䌅�ɑg�܂ꂽ�̋����R����͂���܂���ł������C��l��l�������[�\�N�͎̉����������������ł���܂����B�̂�Q�[���C�_���X�Ɩ{���Ɋy����1���Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B��N�܂ŋΖ����Ă����ѐ搶�����Ă����������̂ŁC���ʂɁu�ҏb���ɍs������v���s���܂����B���߂͂͂����������Ă����q�������Ō�ɂ̓m���m���Ŗ{���Ɋy����ł��܂����B  �@ �@ �@ �@ �@����ڂ͔�ᴐ���������܂����B���̓��͓V��Ɍb�܂�C����������������₩�Ȓ��Œ��̂ǂ����s���܂����B  �@ �@ �@ �@ ���J���[���C�X�Â��聜 �@���H�C�ЂÂ��C�|�����ς܂��āC���悢���ᴐ�����ł��B��O������߂��̃R���e�i�O�ɏW�܂�C���R�̉Ƃ̌W��̐l����̐����̌�C�����n����C�S�l�ǂ��Ƃ̃J���[�Â��肪�n�܂�܂����B�d�C�āC��،W�ɂ킩��Ă̍�Ƃ��n�܂�܂����B���܂ŏK�������Ƃ������ċ�J���Ȃ���ꐶ�����ɂ��Ă��܂����B���߂Ă̎q�����āC�����o���ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�J���[�Ƃ������J���[�X�[�v�Ƃ����ǂ�����܂������C�u���������������ȁv�u�Ȃ���������������ȁv�u�ׂ̃J���[���܂������ȁv�ƌ����Ȃ��犮�H���Ă��܂����B �@�Q���Ԃ̎��R������ʂ��āC�T�N���̎q�ǂ������̂Ȃ�����[�܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��l�ł͂ł��Ȃ����Ƃ��݂�Ȃŋ��͂��Ă��C�����ł��邵�C�ł�����т��������͂��ł��B�ƂĂ������͂��������킹�Ă���q�ǂ������Ȃ̂ŁC���ꂩ����͂����킹�Č����P��������邱�Ƃ����҂��܂��B�搶�������݂Ȃ���̂����ɋ��͂͐ɂ��݂܂���B  �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
10��9���i���j �@    �@�@�R�N���Љ�w���I�����@�@  �@10���S���i���j�ɁC�R�N���͎l���s�`�|�[�g�r���C�l���s�w�O���X�X�U��C���ƐU���Z���^�[�C���_����K�₵�w�K�����Ă��܂����B �@�͂��߂Ẵo�X�ł̎Љ�w�Ƃ����̂��C�q�ǂ������͒������₤���������C������Ă��܂����B �@�l���s�`�|�[�g�r���ɂ͑����������̂ŁC�`���ӂ��o�X�ʼn���Ă��炢�܂����B���т��������R���e�i��т����肷��悤�ȑ傫���̃L�����i�K���g���[�N���[���j�C�┑����D�C�H�Ɨp�̉��̎R�Ȃǂ��߂��Ō��邱�Ƃ��ł��܂����B �@�l���s�`�|�[�g�r��14�K�̓W�]�W�����u���݂Ă炷14�v�ł͎l���s�`�̐̂��獡�ɂ��Ẳf�����������ƁC�W�]����������ƂƂ��ɍ`�ɂ��Ċw�K���܂����B�A���ň�ԑ����̂������ł��邱�ƁC���[�^�[�v�[���C�ΒY�̎R�C�V�R�K�X�̃^���N�C�D����̉~�낵�̍�ƂȂǂ����낢�댩�C���߂Ēm�邱�Ƃ������ς�����܂����B �@�ߌ�̒��ƐU���Z���^�[�ł́C����݂̂���������̌��������Ă��炢�܂����B���߂Ă̑̌��ł݂�Ȃŋ��͂��Ȃ��璃�t����������Ƃ��ނ��Ƃ��ł��܂����B�����̍��Ɏq�ǂ������͂ƂĂ����ꂵ�����ł����B�Ō�Ɏ��������ł������Β��ł��������݂܂����B���͊i�ʂ̂悤�Ŗ{���ɂ����������Ɉ���ł��܂����B �@�Ō�ɐ��_����K��C�������~�����Ă���q�ɂ������Ă��炢�܂����B���܂ŕ������̂ł����C�T���̑q�ɂ͖{���Ɋ����āC�q�ǂ������͑呛���ł����B �@�Љ�w�̗ǂ��́C���܂Œ��ׂ���w�K�����肵�����Ƃ��C�����Ō����蕷�����芴������l�����肷�邱�Ƃł��B�{���ɂ�������̌��n�w�K����ł����̂ŁC��������Ƃɋ����Ŏl���s�s���≺��n��̒���Y�Ƃɂ��Ă̊w�K������ɐ[�߂Ăق����Ǝv���܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@���������w�Z�E�Ƒ̌����� �@���������w�Z�E�Ƒ̌������@ �@���������w�Z�̂Q�N���V�����C10���P���i�j�`�R���i�j�܂Ŗ{�Z�ŐE�Ƒ̌����s���܂����B�P�N�`�R�N�܂ł̑S�N���X�ɂP��������C�q�ǂ������̊w�K�̕⏕��������C�V�肵�܂����B���w���̊��z���ꕔ�̂ݏЉ�܂��B �@�s�u�E�Ƒ̌��w�K���I���āv�̊��z���t �� 1���ڂ͎��Ƃ̌�����V��C����ׂ����肵�Č𗬂�[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���ƒ��C�����Ɨ������ςȂ��������̂ŁC���������������ł��B�u���ꂪ�搶�Ƃ����E�Ƃ��v�ƁC�����̂Ȃ��ŒɊ����܂����B�Q���ڂ́u�`�搶�v�ƌĂ�邱�Ƃ����������ł��B�ڕW�́u�����ς�����ׂ낤�v�́C���ʂ���Ƃł��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ͍���ƈ���Ē��ǂ��ł����������ŁC�y�������Ƃ�����邱�Ƃ�������ł��܂����B �� �R���ځC���C�搶�Ɏd���𗊂܂�܂����B���w���ɓǂݕ����������܂����B�S���ڂ̏��ʂ݂͂�Ȃƈꏏ�ɐ��������܂����B�T���ڂ͑̒��������Ȃ����q�����ĕی����ɘA��čs���܂����B�A��̊w���ł͍Ō�̂����������܂����B�ł��C�ْ����ď��ɘb���܂���ł����B���̌�ɃT�b�J�[�̃w�f�B���O�������܂����B���̂R���Ԃ͂ƂĂ��y���������ł��B �� �R���ڂ̂U���ڂɎ��ŋ���ǂ݂܂����B���Ƃ��Ɛl�̑O�ɗ��̂����Ȃ̂ŁC���ɓǂ߂邩�S�z���������ǁC�Â��ɒ����Ă���Ă��܂�܂炸�ɓǂ߂Ă悩�����ł��B�����搶�ɂȂꂽ��C�݂�Ȃ̑O�ł��Ă��ς��Ɠ�����悤�ɂ������Ǝv���܂��B �� �搶�̎d���͂ƂĂ���ςł����B��l�ЂƂ肻�ꂼ��\�͂��Ⴄ���߁C�l�ɂ���đΉ��̎d����ς���̂�����đ�ςł����B�������C���ƒ��ɃT�|�[�g��������C�������肷��Ƃ��ɁC�����Ƙb�������Ă���Ȃ�������C�����Ă���Ӗ���������Ȃ��Ƃ������X����C������̂ɂ�������̎��Ԃ��g���Ă��܂��܂����B����ƁC���ꂭ�炢�̌��x������{���Ă����̂���������Ȃ��āC���������Ƃ�������̂ɂ���������̎��Ԃ��g���Ă��܂��܂����B���̐E�Ƒ̌��������Ȃ��I���邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��B �� 20���x�݂ɂ̓h�b�`�{�[�������ėV��ł��܂����B�h�b�`�{�[�������Ă���Œ��Ɂu�{�C���o���āv�ƌ����܂����B���ǁC�{�C���o���C�͂�����܂���ł����B �� ���߂Ă̎��Ƃ͍���ł����B�j�C���Ƃ��������������Ă�����Ă���Ƃ��ɁC�݂�Ȃ̐Ȃ̎��������܂����B���̂Ƃ��ɁC���������Ԉ���Ă����̂Łu���̊����͂������珑����v�Ƌ����Ă�������C�u�����C�������B���肪�Ƃ��B�v�ƌ����Ă��炢�܂����B�V�я�T���ł͂��낢��Ȍ����Ȃǂɍs���āC�̎����E������ǂ낾����������C���ɂ�������������C�����Ȃ��Ƃ����ėV�т܂����B�E�E�E�R���ԁC���w�Z��̌����āC���܂ł�苭���w�Z�̐搶�ɂȂ肽���ȂƎv���܂����B �� ���H�̂Ƃ��ɂ́C�u���̂Ƃ�������āv�Ƃ݂�ȂɂЂ��ς��ĐȂɍ���Ȃ��قǂł����B���x�݂ɂ݂͂�ȂŃh�b�`�{�[�������܂����B�v���Ԃ�ɏ��w�Z����ɂ��ǂꂽ�Ȃ����������ł����B�E�E�E�E���̐E�Ƒ̌����I���āC�搶�Ƃ����E�Ƃ͂ƂĂ���ς��Ǝv���܂����B�ł��C�ꐶ���������Ă���搶�����āC�ƂĂ���������܂������C�����������Đ搶�ɂȂꂽ�炢���ȂƎv���܂����B �@ �@�@          |
||||||
| 9��19�i�j �@�����̐g�̈��S�����Ƃ��@�@  �@�@�@�|�u�[��ꎞ�C������Ƒ��߂̃��C�g�E�I���^���v�| �@9��23���i���j�͏H���̓��ł����B���̓������ɓ��ɓ��ɗ[��ꂪ�����Ȃ��Ă����܂��B10��1���̓��̓���͌ߌ�5��38�����炢�ł��B�q�ǂ������̎��̂ő����̂��C���]�ԏ�Ԓ��̔�яo����H��ʍs�s���ӎ��̂ł��B�܂��Ă�Â��Ȃ�Ƃ��̊댯���������Ă��܂��B�悭�w�Z�Ɂu���]�Ԃ����C�g���_�����ɑ����Ă��ĂԂ��肻���ɂȂ����B�v�Ƃ����n��̕�����̐����͂��܂��B �@���N�̂��Ƃł����C�ƂĂ��厖�Ȏ��g�݂�����܂��B����́C�u�[��ꎞ�C������Ƒ��߂̃��C�g�E�I���^���@�`�Z�[�t�e�B�[�E���C�g�E�I���^���`�v�ł��B��ʎ��̂𖢑R�ɖh�����߂ɁC10��1���i�j�`12��31���i�j�܂ł�3�����Ԏ��{����܂��B �@���i�����Ƃ��Ď���2�_���������Ă��܂��B �@ �[��ꎞ�̑��߂̃��C�g�̓_���i���]�ԗ��p�ҁC��֎ԁC�����ԗ��p�ҁj �A ���ˍނ̒��p���i�i���s�҂���ю��]�ԗ��p�ҁj ���̂͋N�����Ă��܂��Ă���ł͉����Ȃ�܂���B�Ԃɏ���Ă���l���\���ɋC�����Ă���Ƃ͎v���܂����C���]�ԗ��p�҂���s�҂����̂��玩���̐g����邱�Ƃ��\���ɐS�����Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́C �@ ���v�O����K�����]�Ԃ̃��C�g��_����B �A ���]�Ԃ̃y�_����ԑ̂̊e�����ɔ��˔����t����B �B ���s�҂͖��邢�����Ɣ��ˍނ𒅗p���āi�^�X�L���j�ԂɃA�s�[������B �C ���]�ԗ��p�҂̓w�����b�g�����Ԃ�B�i�w�����b�g�ɂ����ˍނ��j �ȏ��4�_�ɐS�����Ă��������B���ƒ�ł����q����ւ̓��������⎩�]�ԓ_�������肢���܂��B���X�̐S�������C�傫�Ȏ��̂𖢑R�ɖh���܂��B �s�Z�[�t�e�B�[�E�o�C�V�N���E�f�[�iS�EB�f�[�j �@ ������P���j���́u���]�Ԉ��S�����v�ł��B���]�Ԉ��S���p�ܑ����Љ�܂��̂ŁC�S�|���Ď��̂̂Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�P�@���]�Ԃ́C�ԓ��������C�����͗�O �@�Q�@�ԓ��͍�����ʍs �@�R�@�����͕��s�җD��ŁC�ԓ��������s �@�S�@���S���[������� �@�@�@����l���C���i�i���ɕ���ŏ��j�̋֎~ �@�@�@����Ԃ̓��C�g��_�� �@�@�@�������_�ł̐M�������C�ꎞ��~�ƈ��S�m�F �@�T�@�q�ǂ��̓w�����b�g�𒅗p �@���̂͋N������̂ł���ƍl���s�����邱�Ƃ��C���̂�h�����ƂɂȂ���܂��B 9��21���i�y�j�`9��30���i���j�͏H�̑S����ʈ��S�^���ł��B�݂�ȂŋC�����܂��傤�B �s�铹�Ȃǂɂ͋C�����܂��傤�t ? ���v�������Ȃ邱�Ƃ��܂߁C�A��Ԃ�ꏏ�ɏo������l�̖��O�C�s���擙���Ƃ̐l�ɕK�����܂��傤�B ? �l�C�̂Ȃ��Ƃ���ւ͏o�����Ȃ��C��l�����͔�����C���v��̊O�o�͕ی�ғ��������]�܂����B ? ���q����̍s����c�����Ă��������B �@��ϕ����Ȏ���ł��̂ŁC���Z��̊O�o��s���ɂ��ẮC�Ƒ��ł悭�b��������i�߁C���̂₯���Ȃǂ̂Ȃ������𑗂��悤�ɏ\���ɋC�����܂��傤�B �@�T�N���u�n�k�̌��v�����܂��� �@9��13���i���j��5�N���́C���h�Б����ƌ�����ψ���̐E���̕��������āC�n�k�Ɋւ���w�K�ƒn�k�̌��Ԃɂ��̌��̖h�Ћ������s���܂����B�n�k�̃��J�j�Y����傫�Ȓn�k�̕|���C�n�k�ɂǂ������邩�Ȃǂ��w�K���܂����B�܂��C�̌��Ԃł͐k�x�V�܂ł̗h���̌����܂����B�k�x�T�ȏ�̗h��ł͂��Ԃ��̑̐��ł����ɐg����邩���l���邱�Ƃ��厖���Ƃ������Ƃ��������܂����B�傫�ȍЊQ�ɔ����āC�ǂ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������������Ď��g��ł��������ƍl���Ă��܂��B �@ �@�@ |
||||||
9��17���i�j �@�傫�Ȓn�k�ɂ��Ȃ��ā@�@  �@9��6���i���j�ɔ��P�����s���܂����B9��3���ɉ��쒆���ۈ牀�Ɖ���c�t���ƍ����Ŕ��P�������{����\��ł������C�����̂���6���͒P�ƂŎ��{���܂����B����̔��P���́u���C���n�k���������C�l���s�s���k�x5�ȏ�ɏP��ꋋ��������o�Ό�C��d�v��z�肵�C�s���܂����B�����@�킪�g�p�s�\�Ȃ��߁C�x���E�n���h�}�C�N���g�p���C���납��Ăт����C�^����ɔ��܂����B���C�E����C�E��C�n�k���S�z����钆�C�n�k��z�肵�����P����������厖�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B �@��������P���ȊO�ɂ�����w���Ƃ��āC�h�Ѓm�[�g�����p�����w�K���s���܂����B�����̖��͎����Ŏ�邱�Ƃ��߂����āC���Ƃ���l�ł���Ƃ��ɒn�k���N�����Ă��K�ɑΉ��ł���͂����Ă������Ƃ��K�v�ł��B���̂��߂ɁC���P����ʂ��āC�h�Јӎ��̍��܂�⌸�ЂɌ��������X�̎��g�݂����Ă��������ƍl���Ă��܂��B �@�w�Z�ł͎��̂悤�ȑ���Ƃ��Ă��܂��B �@�@ �������⋳���O�̘L���̃K���X���ɂ͂��ׂĔ�U�h�~�t�B�����������Ă��܂��B�i�g�C�����̈ꕔ�̃K���X���̓t�B�����������Ă��܂���B�j �@�A �L���ɂ͕���u���Ȃ��悤�ɐ������ڂɐS�|���Ă��܂��B�i���H�p�̃��S���C�G�Ђ����͒u���Ă���܂��B�j �@�B �L���ɂ���|������C�������̒I�͌Œ����ł����ɓ|��Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B �@�C ����25�N�x��1�N������h�Г��Ђ��������Ă����܂��B �@�D ���N����͂��߂܂������C6���̎��ƎQ�����ɂ́u�ً}�������P���v�����{���Ă����܂��B �@�E 6�N���͏C�w���s�Ő_�ˎs�̐l�Ɩh�Ж����Z���^�[��K��C�h�Њw�K���s���Ɠ����ɁC���O�w���Ŗh�Ђɂ���������w�K���s���C�����������Z��ł��钬�̖h�Ђɂ��čl���܂��B �@�F ���N�x���5�E6�N���ɎO�p�Ђ��g�������}�蓖����e�Ƃ����ی��w�����s���Ă����܂��B �@�������m�点���Ă��邱�Ƃł����C������x�ȉ��̂��Ƃ����ǂ݂��������C���ƒ�ł��h�Ђɂ��čl�������Ă��������B ���w�Z�ɂ���Ƃ��ɒn�k�����������ꍇ �s�����ɂ���Ƃ��t �@�}���ŋ��������яo�����肵�Ȃ��悤�ɁC�܂��͊��̉��ɂ������ďォ�牽�������Ă��Ă����v�Ȃ悤�ɓ������܂��傤�B�����Ēn�k�̗h�ꂪ���܂�����C�搶�̎w���ɏ]�����܂��傤�B �s�L���ɂ���Ƃ��t �@�@�L���ɂ���Ƃ��ɒn�k���N��������߂��̋����ɓ�����̉��ɂ�����܂��傤�B���ꓮ�����Ƃ��ł��Ȃ����炢�h�ꂪ�Ђǂ����́C�K���X����|������ȂǓ|��₷�����̂��痣��Ă��Ⴊ��őҋ@���܂��傤�B �s�K�i�ɂ���Ƃ��t �K�i�ɂ���Ƃ��ɒn�k���N�������ꍇ�C����ĂĊK�i�����肽�������肷��̂͊댯�Ȃ̂ł��̏�ɂ��Ⴊ��őҋ@���܂��傤�B �s�^����ɂ���Ƃ��t �O���b�Ƃ����Ƃ��^����ɂ�����C�����|��Ă��Ȃ��^����̂܂ő҂��܂��傤�B ���w�Z�o���Z���ɒn�k���N�������ꍇ �@�܂����œ������܂��B����Ɍ����C�d���C�u���b�N���⎩���̔��@������C���̏ꂩ����S�ȂƂ���܂ŗ���܂��B���̏�ɂ���Ƃ��͗��������đf�����������痣��܂��傤�B �s�߂��̈��S�ȏꏊ�i�����E�Z��j�֔��t �w�Z���߂��ꍇ�͂��̂܂܍Z��ɔ��܂��傤�B�w�Z���狗��������ꍇ�͋߂��̌�����L���ꏊ�ł�ꂪ�����܂�܂ł������痣��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���̌�C���炭�l�q�����ĉƂɈ����Ԃ����C�w�Z�֍s���Đ搶�̎w�����܂��傤�B �ƂɋA��ƉΎ��������ȂƂ���ŋN�����Ă�����C�Ƃ��|��Ă����肵�ċt�Ɋ댯�ȏꍇ������܂��B���̓_�C�w�Z�Ȃ�A�������₷�����ꏊ�ɂ��K���Ă��܂��B ���������������������������������������������������������� ������x�u�n�k�x���錾���ւ̎����̑Ή��v�ɂ��Ċm�F���܂��B �� �Ƃɂ���Ƃ��u���ӏ��܂��͌x���錾�v���o���ꍇ �@�@���ӏ�o�����_�ŁC�w�Z�͋x�Z�ɂȂ�܂��B�w�Z����̘A����Ƃ̐l�̌������Ƃ��悭���C���S�ȏꏊ�ɂ��܂��傤�B �� �w�Z�ɂ���Ƃ��u���ӏ��܂��͌x���錾�v���o���ꍇ �@�@�����C�S�����͕ی�҂̏o�}��������܂ŁC�w�Z�őҋ@�����܂��B �� �������������������������������������������������������� �@  �@3�N���u�M�������}�̎Y���v�̕����Â��� �@3�N���u�M�������}�̎Y���v�̕����Â����@3�N����6���̏��߂̃v�[���|���O�Ƀv�[���̃��S�̋~�o�����s���܂����B���N�̃v�[���ɂ̓M�������}�̃��S�������ς����܂����B�����4�N������N9���ɃM�������}�������Y�ނ悤�Ƀv�[���Ɉ��̕�����p�ӂ��Ă��ꂽ����ł��B �@�����ŁC���N��3�N�������N�x��3�N���̂��߂ɁC�v�[���ɃM�������}�̎Y���̂��߂̕����Â����9��10���i�j�ɍs���܂����B�����璩����ɏo�����C�����̂�ɏo�����܂����B�搶���������������������ł����ς��Ɏ����C�v�[���O�ŁC�y�b�g�{�g���̕��������t�����v���X�e�B�b�N�̂����Ɉ���}�����ݕ��������܂����B15�̕������v�[���ɕ����ׂ܂����B�ʐ^�̂Ƃ���C�v�[���ɐl�H�̐��ӂ̑������o�����܂����B �@���N�̃v�[��������M�������}�̃��S����������̂�܂��B���̑���C�ԃg���{��V�I�J���g���{�Ȃǂ̃��S�͍̂�Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��Ƃ��܂߁C�݂�Ȃŕ������Ă݂����Ǝv���܂��B3�N���̕����Â���͐������̂��̂����Ȃ���Â���ł��B �@          |
||||||
9��2���i���j �@�݂�Ȃł������Ƃł��� �@9��2���i���j���炢�悢��2�w�����n�܂�܂����B����2�w�����牺�쏬�w�Z�ɐV�������Ԃ�3�������܂����B�����ł������Ȃ��߂�悤�ɂ݂Ȃ�����ϋɓI�ɐ����������Ă��������B �@2�w���́C�C�w���s�C���R�����C�O�����y��C�Љ�w�C�������L�^��Ȃǂ�������̍s���⋳�犈��������܂��B�����̊�����ʂ��āC�����̓��ӂƂ��Ă��邱�Ƃ⎩���̂悳��傢�ɏo���C������ڂ����ς��ɕ\�����Ă��������B�܂��C��l�ł͂ł��Ȃ����Ƃ��݂�Ȃŗ͂��o�������C��������̂��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B �@2�w���̎n�܂�ɂ�����C��̂��Ƃ��Љ�����Ǝv���܂��B �@��ڂ́C�݂Ȃ�����悭�m���Ă���j���[���[�N�����L�[�Y�̃C�`���[�i��؈�N�j�I��̂��Ƃł��B�ނ͓��{��9�N�C�č���13�N�C���ĒʎY4000�{�ڂƂȂ���ł��L�^���܂����B�C�`���[�I��͂��̎����̂悤�Ɍ���Ă��܂����B�u������������̂��������́C����1�����Ȃ��B�����4��d�˂�ꂽ���Ƃ͂���Ȃ肩�ȂƎv���B4��̈��ł�łɂ�8���ȏ�͉������v�������Ă����B����Ə�Ɍ��������Ă����̂ŁC�ւ��Ƃ����炻������Ȃ����ȁB�v �@�C�`���[�I��̌��t�͖{���ɂ킽�������ɑ����̂��Ƃ��l�������Ă���܂��B�킽�������͋L�^��悢�Ƃ��낾������(��)�ɂ��܂����C���͂����z���܂łɐ₦�ԂȂ��w�͂������ɏd�˂Ă��邩�ɋC�Â�����܂��B�C�`���[�I��ɂ͍����x����u���߂��Ɓv�����邻���ł��B �@�����J�n�̖�4���ԑO�ɂ͋���ɓ���C�X�g���b�`�ő̂��ق����܂��B�x�����W����܂���B�u����ǂ��Ǝv�����Ƃ͂��邪�C�����������ǂ���B�v�܂��C�O���[�u��X�p�C�N�̎����͌����������Ƃ��Ȃ������ł��B�x���`�ł��o�b�g����ɖ����Ă��܂��B�����������炵���I��قǁC�������x���Ă���Ă��铹����ƂĂ��厖�ɂ��C�̒��Ǘ��ɂ��l��{�C�������Ă��܂��B�킽�����������̎�������������ƌ��߂Ă����������̂ł��B �@��ڂ́C���֑O��3�N���̉Ԓd�ɍ炢�Ă����Ђ܂��̂��Ƃ����b�������Ǝv���܂��B�{�Z�̐E���œ����{��k�Јȗ��C����I�ɓ��k�x���{�����e�B�A�ɏo�����Ă���l�����܂��B���̃{�����e�B�A�ŊG�{�w�Ђ܂��̂����x�̂��ꂳ��Əo��C�𗬂��钆�łЂ܂��̎���Ă��炢�܂����B���̂Ђ܂��̎�����N��3�N�����Ԓd�Ɍ����ɍ炩���܂����B�w�Ђ܂��̂����x�̊G�{�͎��̂悤�ɂ��Ăł��オ��܂����B �@�u�{�錧�Ί��s����쏬�w�Z�B�����{��k�Ђɂ��Ôg�ŁC�S�Z����108���̎����ɓ�����C74�����s���s���E���𗎂Ƃ��Ƃ����ߌ��Ɍ������܂����B���̊G�{�́C�Ôg�ł��q�����S�����C�����悤�̂Ȃ��߂��݂̒�ɂ���Ȃ���C�Ȃ�Ƃ��O�����ɐ����Ă����˂ƁC���w�Z���ɂЂ܂��̎��A���͂��߂�8�l�̂��ꂳ���ɂ��G�{�ł��B�h�L�������^���[���B�邽�߂Ɍ��n�֍s���Ă�����ƁE�t���O����ɑ����ꂽ�C���ꂳ������̎莆�B�����ɂ́C�h���߂��݂Ɠ����ɁC�q�ǂ������ւ̈���ӂ�郁�b�Z�[�W���l�܂��Ă��܂����B�G�{��ƁE�����^���q��������n�֕����C���ꂳ���̘b�Ɏ����X���C���ꂼ��̎v����肢���������グ�C�G�{�Ƃ����`�ɂ��܂����B ����8�l�̂��ꂳ��̂ق��ɂ��C�k�Ђł��q�����e�����l��S�����C�[���߂��݂������l�͂������܂��B�����悤�ȑr������߂��݂�S�Ɏ��l���吨���܂��B����ȕ��X�̐S�ɁC�����ł����Y�����Ƃ��ł�����Ƃ̊肢�ŁC���̊G�{�̏o�ł����܂�܂����B�v�i�{�̏Љ���j �@7������8���ɂ����ĂЂ܂��͌����ɍ炢�Ă��܂����B�{�Z�̐E����7���ɓ��k�x���{�����e�B�A�ɍs���Ƃ��ɁC3�N���̎q�ǂ������́w�Ђ܂��̂����x�̂��ꂳ��Ɉ��Ă����b�Z�[�W����l�ЂƂ肪�����C�����܂����B�{�����e�B�A��ɁC��ϊ��ł݂������Ƃ����������C�{���ɂ��ꂵ���v���܂����B �@�Ђ܂��̎킪�������ꂽ�l�Ɛl�̐S���Ȃ��Ă���܂����B�����Ǝq�ǂ������̎v�����͂����̂ł͂Ȃ��ł��傤�B���N�Ƃꂽ������З��N��3�N���ɂ������[���C���k�̐l�����̎v������������Ǝ~�߂Ă��������Ǝv���܂��B �@�@ |
||||||
7��19���i���j  �@���Ȃ��́C�������g��Ȃ��܁C�Ƒ��� �@���Ȃ��́C�������g��Ȃ��܁C�Ƒ����@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɂ��Ă��܂��� �@�P�w���̒��߂�����Ɉ�̎����Љ�����Ǝv���܂��B���̎��́C2013�N�U��23���̉����́u�ԗ�̓��v�Ǔ����ŁC���{�̂����ɂ��鉫�ꌧ�^�ߍ������v���Ǐ��w�Z�P�N�̈����L������i�U�j���ǂݏグ������̎��ł��B���ꌧ���a�F�O�����ق�������u���a�̃��b�Z�[�W�v�Ɋ�ꂽ1690�_�̒�����I�ꂽ���̂ł��B �@���̎����C�e���r��ʂ��ĕ������Ƃ��ɖړ����M���Ȃ�܂����B����ɐ��܂ꉫ��Ɉ炿�C�����̂���������₨�������̗��j�Əo��C�����̐�����U��Ԃ肱�̎������܂ꂽ�̂ł��傤�B �@�@�@�ւ�����ĂȂɂ��ȁB �@�@�@�ڂ��́C��������B �@�@�@���Ƃ������ƂȂ��悵�B �@�@�@���������C���B �@�@�@�������ł����ԁB �@�@�@�˂�����炤�B �@�@�@���Ȃ��������ς��B �@�@�@�€���̂�т肠�邢�Ă�B �@�@�@�����Ă������Ȃ��Ȃ���B �@�@�@���傤�߂���������������͂��C �@�@�@��Ȃ��ɂ��܂��C�q�q�[���ƂȂ��B �@�@�@�݂ȂƂɂ́C�t�F���[���Ƃ܂��Ă��āC �@�@�@���݂ɂ́C���߂₩���������悢�ł�B �@�@�@�₳���������낪�ɂ��ɂȂ�B �@�@�@�ւ�����Ă����ˁB�ւ�����Ă��ꂵ���ˁB �@�@�@�݂�Ȃ̂����납��C �@�@�@�ւ��킪���܂��ˁB �@�@�@�����́C�����낵���B �@�@�@�u�h�h�[���C�h�J�[���v �@�@�@���������Ă��邱�킢���ƁB �@�@�@���Ȃ��������āC���邵�ނ��ǂ��B �@�@�@������������ł��܂��ĂȂ��ЂƂ����B �@�@�@�����C�ڂ��́C�ւ���ȂƂ��ɂ��܂�Ă悩������B �@�@�@���̂ւ��킪�C�����ƂÂ��Ăق����B �@�@�@�݂�Ȃ̂��������C�����ƂÂ��Ăق����B �@�@�@�ւ���Ȃ������C �@�@�@�ւ���Ȃ��������C �@�@�@�ւ���Ȃ�Ȃ��ɂ��܁C �@�@�@�ւ���Ȃ����Ȃ�C �@�@�@�ւ���Ȃ������C �@�@�@�ւ�����Ă��Ă����ˁB �@�@�@���ꂩ����C�����Ƃւ��킪�Â��悤�� �@�@�@�ڂ����C�ڂ��̂ł��邱�Ƃ��炪����B  �@�s�W���U���͉��̓��t �@�s�W���U���͉��̓��t�@����E��햖����1945�N8��6���L���s�Ƀ��g���{�[�C�Ɩ��Â���ꂽ���q���e����������C8��9������s�Ƀt�@�b�g�}���Ɩ��Â���ꂽ���q���e����������܂����B�����āC���{��8��15���ɏI����}���܂����B�W���U���͐��E�ŏ��߂Ď��ۂ̐푈�Ō������������ꂽ�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����Ȃ̂ł��B �@���{�̉ĂƂ����C�ǂ����Ă�������悤�ȏ����ƃA�u���[�~�̂т�т������Ɛ푈�̂��Ƃ�Y��邱�Ƃ��ł��܂���B�L���ʼn��ł������̍D���Ȃ��Ƃ��ł��鎞��ɐ��܂ꂽ��X�ɂ͑z�����ł��܂��C�������������ꂽ�L���s���ł͂��ׂĂ̂��̂��Ă��s������C���S�n�߂��̍L�����Y�Ə���ق��B�ꂻ�̎p�̈ꕔ���Ƃǂ߂Ă��܂����B����50�N�͑�����{�������Ȃ����낤�Ƃ���ꂽ���炢�ł��B���̉�ق���Ɂu�����h�[���v�ƌĂ�C�����̏ے��Ƃ��ĕ��a�����̈�p�Ɏc����܂����B�����č��́C��x�Ɠ����悤�Ȕߌ����N����Ȃ��悤�ɂƂ̊肢�����߂āC�u���̐��E��Y�v�Ƃ��ēo�^����܂����B �@�w�͂����̃Q���x�́C����[���ɂ��C���g�̌����̔픚�̌������ɂ�������ŁC�L���s�M���{���ɏZ�ލ����w�Z2�N���̎�l���ł��钆������1945�N8��6���ɓ������ꂽ�����ŕ��E��g�C�o�E�p�q�C��E�i����3�l��S�����Ȃ�����C�����܂���������p��`���Ă��܂��B �@8���͕K���푈�Ɋւ����Â���e���r�ԑg�Ȃǂ�����͂��ł��B�����ł������̂ŁC���А푈�ɂ��čl���鎞�Ԃ������Ă��������B  �@�l�N���u�p�b�J�[�Ԃ�����Ă����v �@�l�N���u�p�b�J�[�Ԃ�����Ă����v�@7��3���i���j�ɁC�k�����|���Ə���s�����̐E���T���ƃp�b�J�[�Ԃɗ��Ă��炢�܂����B����̊w�K�͂U���ɍs�����Љ�w�̔��W�w�K�Ƃ��čs���܂����B �@�����ł́C�u���݂Ƃ��̌�v�ɂ��Ă��b���`�Ŋw�K���s���܂����B���ɔR�₳�Ȃ����݂ɂ��Ă͓암����������ōs���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�����̓T���h�C�b�`�H�@�Ƃ��������i�������݂̏�ɓy�����Ԃ��C����ɂ��̏�ɖ������݂�u���C����ɓy�����Ԃ��Ă������ƁB�j�ōs���Ă��܂����B�y�͏d�̖�����ɂ�����h���C�����Ւf���闘�_�����邱�ƁC�������݂̂Ȃ��Ƀ��C�^�[�Ȃǂ���ł������Ă���Ƒ�ЂɂȂ��鋰������邱�Ƃ������Ă��������܂����B �@�܂��C�����̎��p�b�N���U������ƃg�C���b�g�y�[�p�[�P���[���ɕς�邱�ƁC�y�b�g�{�g����������h�Z���Ȃǂɕς�邱�ƁC���^�[�i�u���r���̂��ƂȂǁC���T�C�N���ł��݂������Ă��Ă��邱�ƂȂǂ̂��b�����Ƃ��ł��܂����B �@�O�ł̓p�b�J�[�Ԃ̎��������邱�Ƃ��ł��܂����B�{�Z�ɗ��Ă�������p�b�J�[�Ԃ͓d�����o�H���W�ԂőS���ł��l���s�s���������������ꂽ�d�C�����Ԃł����B���^�Ԃ̂Q�l���ŁC���݂��ǂ̂悤�Ƀp�b�N����Ă������̎d�g�݂��ƂĂ��悭�킩��܂����B��ƈ������Ă��镞���y�b�g�{�g������̃��T�C�N���i�ł��邱�ƁC�C�͗����h�~�p�ł��邱�ƁC��ɒ����C�X�q�𒅗p���Ă���ȂLj��S�ʂ̊m�F�ɂ��Ă��w�т܂����B �@�q�ǂ��̎���Łu��Ԃ炢���Ƃ͉��ł����v�Ƃ����₢�ɁC�u�d���̂炢�͉̂䖝�ł��邪�C�d�������Ă��鉡�ŕ@���܂肵�Ă������Ƃ������炢���Ƃł��B�v�Ƃ�������������܂����B �@��ςȎd�������Ă��邱�ƂɊ��ӂ����Ȃ���C���������X�̒��ŏ����ł����݂����炷���ƁC���T�C�N���������Ɗ��p���邱�ƁC���݃X�e�[�V�����ł̃}�i�[�Ȃǂł��邱�Ƃ����m���ɂ��Ă������Ƃ̑���������܂����B�S�N���݂̂Ȃ���͂Q�w�������݂�T�C�N���̊w�K�������Ɛi�߂Ď��������̐������ɂȂ��Ă����Ă��������B �@�o����w�� �@7��12���i���j�ɂU�N���́u�o�����낤�v�̎��Ƃ�o��ɐ��ʂ��Ă݂���J���ԉq����ɍu�t�Ƃ��Ă��Ă����������{���܂����B �@�J������͔o��̍����ő厖�ɂ��������ƂƂ��āC����H�C�Ȃ�قǁC������ƕ����Ă�ȂǁC��������C�C�����Ɏc�����肵�����Ƃ��u�����܂܁C�������܂܁C�v�����܂܂��C���̂܂܂ɕ\�����܂��傤�B�v�Ɠ`���Ă��������܂����B�U�N���̎����͒Z�����Ԃł������C������O�߂āC�o������Ђ˂�܂����B �@�@�@���炾��Ɓ@�����ӂ������@�o�Z�� �@�@�@�搶�́@�����������@�O�ɂ��� �@�@�@�O����@�������ʁ@�݂ǂ�̓c �@�@�@���z���@������������ā@�Ƃ���� �@�ǂݕ��������y���� �@���쏬�w�Z�w�Z�Â���r�W�����Ɂw�{�D���Ȏq�ǂ��ɂ��܂��|�w�ǂݕ������̏[���v�x�Ƃ������e���f���Ă��܂��B�{�N�x�͓��Ɏq�ǂ������ɖ{�̊y������̊����Ă��炤���߂ɁC�{�Z�Ζ��̐}���َi���ɂ��u�b�N�g�[�N�̌v��I�Ȏ��{�C�l���s�s���Ŋ���Ă���ǂݕ������{�����e�B�A�O���[�v�̐ϋɓI�ȓ������l���Ă��܂��B �@7��8���i���j�́C�u��̟D�v�Ƃ����ǂݕ������{�����e�B�A����������āC�P�D�Q�N�����ǂݕ����������Ă��炢�܂����B �@��̟D�̃����o�[�͂���l�ŁC�N���X�P�ʂł��Ă��炢�܂����B�{��ǂ�C�G�{�������Ęb�����肷��ǂݕ������ł͂Ȃ��C����̂͏����Ȋۃe�[�u���̏�ɂ��������C�g���_���������ȃX�^���h�Ɖ̓����ꂽ�傫�ڂ̂낤���������ł����B���ǂ������̕\������Ȃ������镨��͂��ǂ������̑z�����������Ă��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���{�̘̐b�i�u�Z���Ђ߂��v�u�˂��݂̏��������v�j�C�O���̘̐b�i�u���M�ƃ��C�I���v�u���q���܂̎��́C���o�̎��v�u��������������v�j������Ă��������܂����B���x�݂Ƃ��āC��V�щ̂������܂����B �@�ꐶ�����ɒ�������p���݂Ė{���Ɋy����ł���l�q���悭�킩��܂����B18���i�j�ɂ́u�ǂ���������v�Ƃ����{�����e�B�A�O���[�v�ɂ��S�N���ւ̓ǂݕ��������s���Ă��炢�܂����B�O���̕��ɕ������������ƕ������Ă��������܂����B���̎�g�݂�1�N�Ԃ�ʂ��čs���Ă��������Ǝv���܂��B�������̕��ł��Аe�q�Ǐ������Ă�����Ă͂������ł��傤���B  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
7��5���i���j  �@��P���w�Z�Â��苦�͎҉�c���s���܂��� �@��P���w�Z�Â��苦�͎҉�c���s���܂����@�w�Z�Â��苦�͎҉�c�́C�ی�ҁC�n��Z���݂̂Ȃ���őg�D����C�w�Z�ƕی�ҁE�n��݂̂Ȃ��݂��ɘA�g���C�M����[�߁C��̂ƂȂ��Ċw�Z�^�c�̉��P��q�ǂ��̌��S�琬�Ɏ��g�ނ��Ƃ�ړI�Ƃ��Đݒu���Ă��܂��B �@�{�Z�����̎�|�ɑ���C����25�N�x�͈ȉ��̕��X�Ɉψ������肢�������܂����B �@�{�N�x��1��ڂƂ������ƂŁC���쏬�w�Z�u�w�Z����v��v�u�w�Z�Â���r�W�����v���̐��������C���̌�q�ǂ������̗l�q�����Ă��炢�܂����B�܂肵���C���w�Z�̉p��̐搶�̏�������Ƃ�����C���̗l�q�����Ă��������܂����B���̌㍧�k����s���C�M�d�Ȃ��ӌ����������������܂����B �s�ψ�����̈ӌ����t �� �w���ł͗��������Ȃ��l�q�����邪�C���Ƃł͗��������Ă��Ĉ��S���܂����B �� ���D�����Ă���N���X�Ə����������ĂȂ��N���X������悤�ł����C�ǂ̂悤�Ɏw��������Ă���̂ł����B �� ����A��C�C�����̂������������ł���q�������B�q�ǂ������ɂ����������߂邾���łȂ��C��l���C�����悭�����������킷�l�q���q�ǂ������Ɍ����Ă������Ƃ��K�v���B �� �ƒ�ł́u�ӂꂠ���Ǐ��v�ɂ��āC���w�N�ł��e�q�Ŏ��g�߂Ă���ƒ낪��������̂͂������Ƃł���B�u���v�ƌĂԔN��i�`9�j�̂����͓ǂݕ��������ƂĂ���ł���ƕ������B �� �V��ł���悤�����C�悭����ƌ������Ă��������Ă���B�����߂��Ȃ��Ȃ�悤�ɓw�͂����Ăق����B �� �����ŕ������߂邱�Ƃ����邪�C�n��Ŏq�ǂ������ɐ�������w�������Ă�����Ƃ����B���ł���l�����肵�ė\�h������̂ł͂Ȃ��C�q�ǂ������ɍl���������f����͂����邱�Ƃ��K�v�ł���B �� �p�ꊈ�����D���Ȏq�������B���ꂩ���ALT����ʔ��u�t����Ƃ̉p�ꊈ���̏[�������肢�������B  �@�Ƃ��ɖL���ɕ�点�邽�߂� �@�Ƃ��ɖL���ɕ�点�邽�߂��@5�N���́C6��28���i���j�ɑ�����ɂ���u��Y����_�C�J�X�g�H�Ɓi���j�v�̐���В��Ƃ����ɋ߂Ă�����n�u���W���l�̔�����C�x�g�i���l�̃n�[����̎O���̕������������C�H��̎d���̂��Ƃ���{�ł̕�炵�Ȃǂɂ��āC���b������C����������肵�Č݂��ɒm�荇���C���ꂩ��̐����ɂȂ��悤�Ƃ��܂����B �@���n�̔������22�N�O�ɃT���p�E��������{�ɗ���ꂸ���ƃ_�C�J�X�g�H�Ƃœ����Ă��܂��B���̍��C�O���l�͎�����l�ŁC���t�Ɉ�ԍ����������ł��B���C�H��ł̓��{�b�g�e�B�[�`���O��@�B�C���ő�ϊ�������Ă��āC�H��ł̒��S�������ł��B �@������́C��ώ����̎d���Ɏ��M�Ə[�����𖡂���Ă���悤�ł����B�u�V�������i�����邱�Ƃ͑�ςȂ��Ƃł����C�V�����i�����ł���Ɗ�т�������v�ƌ����Ă��܂����B�����āC�d���ł͂���Ȃ��Ƃ͉����Ȃ��ƌ������܂����B �@�x�g�i���l�̃n�[����́C���K���Ƃ��ē��{�ɗ���1�N�������ł��B���K���Ԃ�3�N�Ԃł��̌�̓x�g�i���ɖ߂邻���ł��B�����̓A�W�A�œ��{����g���Ċ����������ł��B����ŁC���͖��T�y�j���Ɏl���s�s�����̖k�ׂɂ��鍑�ی𗬃Z���^�[�ɒʂ��C���{�������Ă��邻���ł��B�n�[����͓��{�ꂪ1�N�ɂ��Ă͑�Ϗ��Ȃ̂ɋ����܂����B �@�n�[����͋Z�p����������w�т������ƁC���{�ɗ��邱�Ƃ����ł��������ƁC�����ɖ��������Ă��邱�ƂȂǂ�����Ă���܂����B�n�[����͖ړI�ӎ��������ē��{�ł̐�������������Ƒ����Ă��邱�Ƃ������`����Ă��܂����B �@5�N���̎q�ǂ������́C�_�C�J�X�g�H�Ƃ̎O���̕����牽�����݂Ƃ����̂ł��傤���B����n��ɂ͑����̊O���̕����Z�݁C�d�������C���������Ă��܂��B�O���Ђ̕��̎v����m��C�n��ւ̊S��[�߂�ƂƂ��ɁC���������ɂł��邱�Ƃ͂Ȃɂ����C���ꂩ��̊w�K�ł�������ƍl����[�߂Ă������Ƃ�����Ă��܂��B �@ �@ |
||||||
| �@ 6��24���i���j �@  �@�S�N���@�Љ�w�Ŋw���� �@�S�N���@�Љ�w�Ŋw�����@6��20���i�j�ɂS�N���́C�u�k�����|�H��v�u�l���s�s�������فv�u���c�����v�֎Љ�w�ɂ����܂����B�Љ�Ȃł́u�Z�݂悢���炵������v�u���傤�y���Ђ炭�v�̒P�����炲�݂␅�̂��ƂȂǂ��w��ł��܂��B�܂��C���ȂœV�̂̊w�K������̂ŁC�v���l�^���E�������邽�߂ɔ����ق�K��܂����B�����ɔ����قł́C���a20�N6��18���̎l���s��P�̋L���������Ȃ����߂ɁC�u�l���s��P�Ɛ펞���̕�炵�v�W���J�Â��Ă��܂����B���̂悤�ɁC���������̐����⋽�y�����m�邽�߂ɁC4�N���͎Љ�w�ɍs���Ă��܂����B  �s�k�����|�H��t �s�k�����|�H��t�@���n�ł͒S���҂̕����������}���Ă�������C�܂��C���|�H��ɂ��ĉf���������C���݂��ǂ̂悤�ɏ�������邩���Ϗڂ������������Ă���܂����B ? �ċp�F��3���C1���ق�300�g���̂��݂��ċp����C�N��200������300�������Ă���B ? ���̐��|�H��ł͎l���s�s���Ɛ�z���C�������̂��݂������Ă���B ? ����24�N�x�Ɏ������܂ꂽ���݂̗ʂ͖�8���g���ŁC���N��1500�g���������Ă���B ? �RR�Ɏ��g��ł���B���݂����炷���ƁiReduce�j�C�ė��p�iReuse�j,�������iRecycle�j�̂R�ł���B�ė��p�Ɋւ��Ă͋��H�̐����݂��o�C�I�̗͂Ŕ엿�ɕς��C�w�Z�̉Ԓd�Ȃǂ̔엿�Ƃ��Ċ��p���Ă���B�܂��C���݂�R�₵���D�̓R���N���[�g�̍ޗ��Ƃ��ĎR�����E��B�Ȃǂɉ^��ł���B ? �����݂����W����p�b�J�[�Ԃ�32�䂠��B ? �ċp�F�̓X�g�[�J�����ł��݂��ォ�牺�Ɉړ������Ȃ���ċp���s���C850�x�ȏ�Ŋ��S�R�Ă�������B �q�ǂ������͎{���w������Ȃ��ŁC���݂̗ʂ𑪂�v�ʊ�ɏ������C�[��10�������邲�݂��W�ς���ꏊ��ċp�F�C�o�C�I�{�݁C�D�s�b�g�Ȃǂ��������茩�w���C���݂��ǂ̂悤�ɏċp�����̂��������̖ڂŊm���߂邱�Ƃ��ł��܂����B  �s���c�����t �s���c�����t�@���̏�̐����ǂ����痈�Ă���̂��C���ݐ����ǂ̂悤�ɂ����Ă���̂��ȂǁC���낢��ȉf��������C���n���w�ŏ��߂Ēm�邱�Ƃ���������܂����B ? ���Ȃs�̒����_���̐����Ԗ쒬�̒����r���o�āC�����Ɉ�����Ă��邱�ƁB ? ��i���g���Đ��������������ł߁C���a������B����ɁC���Ȃǂ��g���Ă��(��)�����邱�ƁB ? �U�����̏�̃R���g���[���Z���^�[��10km���ꂽ�Ƃ���ɂ��邱�ƁB ? �����͖�30���l�̈��ݐ������肾���C�l���s�s�̈ꕔ�C�Ԗ쒬�̈ꕔ�C�鎭�s�̈ꕔ�̐l�����Ɉ��܂�Ă��邱�ƁB �@�{�݂̑傫���C�̗��ꂪ�{���ɂ悭�킩��C�q�ǂ������������ς��̔������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ǂ����Đ���ɏ��������̂��C���a���̐[���͉����[�g�����C�������ɂ͉J���͂���Ȃ��̂��ȂǁC���낢�닻���[�����������܂����B  �s�v���l�^���E���Ǝl���s��P�W�t �s�v���l�^���E���Ǝl���s��P�W�t�@�����ق̈ɓ��搶�ɐ��������Ղ��g���Ă̐��̌������ϒ��J�ɂ��w�����������C���̒T������̕s�v�c���Ȃǂ�m�邱�Ƃ��ł��܂����B�l���s��P�̓W���ł́C�q�ǂ������͋Ȃ���������n�����d�݂̉�Ȃǂɖڂ������Ă����悤�ł��B����搶�͋�P�̔N�\�����āC�L���ƒ���Ɍ��������������O�ɁCB29����@�����Ŕ��āC�����Ɠ����`�̂P���|���h��^���e���ꔭ�����������Ĕ�ы���Ƃ����u�͋[���q���e�v�̓������l���s�ł��C7��24���C8��8���̂Q�������Ă������Ƃ�������Ă���܂����B �@����̎Љ�w��ʂ��āC�q�ǂ������͔M�S�Ƀ������Ƃ�C����������ς����邱�Ƃ��ł��܂����B��������p�C�l�������Ă���W�c�ȂǁC�q�ǂ������̂����ʂ���������Ƃ炦�邱�Ƃ��ł����Љ�w�ł����B�������Ă����������{�݂̕��X�ɉ��߂Ă�����q�ׂ����Ǝv���܂��B �@���|�H��C������w���킩�������Ƃ���������܂������C�S�N���݂̂Ȃ���̖{���̊w�K�͂��ꂩ�炾�Ǝv���܂��B�ƒ��w�Z�C���ł��݂␅���킽�������̐����Ƃǂ����т��C�ǂ̂悤�Ƀ��T�C�N����ߐ��Ȃǂ�����Ă��邩�Ȃǎ��������Ńe�[�}�������C��������Ɗw�K���d�˂Ă����Ă��������B �@��6��23���͉��̓��ł������H�� 2013�N6��23���i���j�C�����68��ڂ́u�ԗ�̓��v���}���܂����B THE BOOM�Ƃ����o���h�̉̂Ɂu���S�v������܂��B�ی�҂̕��Ȃ�悭�m���Ă���̂��낤�Ƃ������܂��B���w���̊F����́C��x�ƂŐq�˂Ă݂Ă��������B �@�@�@�@�u���S�v�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쎌��ȁF�{��a�j �@�@�ł����̉Ԃ��炫�@�@�����Ăс@�������� �@�@�ł������炫����@�@�����Ăс@�������� �@�@�J��Ԃ������݂́@�@���킽��g�̂悤 �@�@�E�[�W�̐X�ł��Ȃ��Əo� �@�@�E�[�W�̉��Ő��ɂ���Ȃ� �@�@���S��@���ɂ̂�@�@���ƂƂ��Ɂ@�C��n�� �@�@���S��@���ɂ̂�@�@�͂��Ă�����@���̗� �@ �@�@�ł����̉Ԃ��U��@�@�����g�����邾�� �@�@�����₩�ȍK���́@�@���������̔g�̉� �@�@�E�[�W�̐X�ʼn̂����F�� �@�@�E�[�W�̉��Ŕ����ɕʂ� �@�@���S��@���ɏ��@�@���ƂƂ��Ɂ@�C��n�� �@�@���S��@���ɏ��@�@�͂��Ă�����@���̈��� �@�@�C��@�F����@�_��@���� �@�@���̂܂܉i���ɗ[��� �@�u�ł����v�̉Ԃ͉��ꌧ�̌��ԂŁC5��������炫�n�߂�썑�̐Ԃ��Ԃ̂��Ƃł��B�u�E�[�W�̐X�v�Ƃ͂��Ƃ����є��̂��Ƃł��B1945�N�i���a20�N�j�t�̘b�̂��Ƃł��B�ˑR�C���ɐ푈�Ƃ������̗�������Ă����̂ł��B�܂��������̉̂ɂ͉����̂��Ƃ��������Ă���̂ł��B �@������1945�N3��26������n�܂�C�g�D�I�Ȑ퓬��6��23���ŏI������Ƃ���Ă��܂��B�܂�6��23���͉���ɂƂ��āC�����I���̓��ʂȓ��Ȃ̂ł��B �@�����Ƃ́C�����m�푈������1945�N�C���ꏔ���ɏ㗤�����A�����J�R�Ɠ��{�R�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ�n���̂��Ƃł��B����E����ʂ��āC����̐l�X�͓��{�ōł��������n����킢�������̂ł��B�������̂����炱����Ɏ��R���i�K�}�j���c��C�����͖��a�@����ꏊ�ɂ��Ȃ�܂������C�ߎS�ȏW�c�����̏�ɂ��Ȃ�܂����B���Ƃ����є��̉��ɂ���K�}�Ő�����Ȃ��قǑ����̐펀�ҁE�����҂��������Ȃ������Ă��܂��B �@�����V���ɂ��̉̂�������{��a�j�����̂悤�ȕ���������Ă��܂����B���p�����Ă��������܂��B �@�w���S�x�́C�{���͂�������l�̂�������ɒ����Ă��炢�����č�����̂��B91�N�~�C���ꉹ�y�ɂ̂߂肱��ł����ڂ��́C����́w�Ђ߂�蕽�a�L�O�����فx�����߂ĖK�ꂽ�B�����Łw�Ђ߂��w�k���x�̐����c��̂�������ɏo��C�{�y����������������߂́w�̂Đx�Ƃ��ꂽ����������n���ő吨�̏Z�����]���ɂȂ�������m�����B �@�ߗ��ɂȂ鎖�����ꂽ���e���m���݂��ɎE�������B �@�Ɍ��̘b�������ɂڂ��́C����Ȏ������m�炸�ɐ����Ă������m�Ȏ����ɓ{�肳���o�����B �@�����ق͎��������������K�}�i���R���A�j�̒��ɂ���悤�ȑ���ɂȂ��Ă���B���̂悤�ȏꏊ�ŏW�c���������l�X�̂��Ƃ��v���Ɨ܂��~�܂�Ȃ������B �@�����C���̎����ق������O�ɏo��ƁC�E�[�W�i���Ƃ����сj���Â��ɕ��ɗh��Ă���B �@���̑Δ���Ȃɂ��Ă�������ɒ����Ă��炢�����Ǝv�����B�̎��̒��ɁC�K�}�̒��Ŏ���������l���̂�������������B �@�w�E�[�W�̐X�� ���Ȃ��Əo� �E�[�W�̉��� ���ɂ���Ȃ�x�Ƃ������肾�B �w���S�x�̓��ƃ����Ȃ����ꉹ�K�ō�������C���̕����͖{�y�Ŏg���Ă��鉹�K�ɖ߂����B �@��l�͖{�y�̋]���ɂȂ����̂�����B �@6�N���ɂȂ�ƎЉ�Ȃœ��{�̗��j�ɂ��Ċw�т܂��B�߂������j����������܂��B�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�l�X�̐S���Ƃ炦��̂��̂��p�����悤�ɁC�푈�̒��Ől�X���ǂ��������̂��C��������Ă����̂����݂�Ȃōl�������C���p���ł�����Ƃ����Ǝv���܂��B �@          |
||||||
6��14���i���j �@   �@�U�N���u �ޗǁ@�̊��I�v �@�U�N���u �ޗǁ@�̊��I�v�����ɂ悵 �ޗǂ̓s�� �炭�Ԃ� �ɂقӂ����Ƃ� ������Ȃ� �i������F�ޗǂ̓s�͍炭�Ԃ��������Ƃ�f����悤�ɁC�����^�����肠��B ���t�W���O���j ���ɂقӁE�E�E�k�o��\����ł͂Ȃ��C�ԂȂǂ̔����������͂ɏƂ�f����l�q���������o��\�������ł������B �@�U��11���i�j�ɂU�N���͓ޗǂ֎Љ�w�ɍs���܂����B��̉̂́C����{�Ղ��ē����Ă����������{�����e�B�A�K�C�h���Љ�Ă��ꂽ���̂ł��B���Њo���ċA���Ă����Ă��������Ɠ`���Ă��������܂����B �����͓V��ɂ��b�܂�C�ƂĂ��[�������Љ�w���ł��܂����B���N�͂R�N���X82���Ȃ̂ŁC�N���X����̂��C�o�X�Q��ōs���܂����B7��30���ɏo�����C�����悭�����_�𑖂�܂����B�q�ǂ������̓o�X�̒��ŁC���j�N�C�Y���o���C���܂ŏK���Ă����ꕶ�C�퐶�C�C�ޗǎ���̕��K�����܂����B�ǂ̃N�C�Y����ς悭�m���Ă��āC���j�̒m������ϐ[���̂ɋ����܂����B�܂��C���R���Ԃɂ̓{�[�C�\�v���m�̑f�G�ȉ̐����S�n�悭�����Ă��܂����B �\��ʂ�ޗnj�����10���O�ɒ����C�����ʂ��āC���r�O�ŋL�O�ʐ^���B��܂����B���ꂩ��C�҂��ł��ꂽ���厛�ɓ���܂����B�O����10���ɁC�^����ɓޗǂ̑啧��������ŕ`���܂����B���̕`�����啧�̈�ۂ������Ď����������̂ł����C�q�ǂ������͂ǂ�Ȉ�ۂ��������̂ł��傤���B �ޗǂ̑啧�a��́C�Ǖʕ��U�w�K�Ɉڂ�܂����B���C�O�����C�l�����C���O�Ȃǂ�Ǖʂŏ���܂����B�ʐ^������Ɏʐ^���B���Ă�������肵�āC�ǂŋ��͂��Ċy�������ɉ���Ă���悤��������܂����B�H���Œ��H���Ƃ�����́C����{�ՂɌ������܂����B ����{�Ղł́C�T�O���[�v�ɕ�����ă{�����e�B�A�K�C�h����ƂƂ��ɁC����{�Վ����فC�������ꂽ��ꎟ��ɓa�C���ɓa�C��\�W���قȂǂ�����܂����B�K�C�h����ɂ�葽���̈Ⴂ�͂��������Ǝv���܂����C�ޗǎ���̈ߐH�Z����Ȃǂɂ��ďڂ����w�K�����邱�Ƃ��ł��܂����B���ɑ�ɓa����鐝��Ɍ����Ă̒��߂┭�@�̂��̂܂܂��݂邱�Ƃ��ł��C�����ł��Â����j�����ޗǂ�̊��ł����͖̂{���ɍK���Ȃ��Ƃł����B �U�N���݂̂Ȃ���͂��̎Љ�w�̍s�����C���̏C�w���s�ɂ��Ȃ����Ă����܂��B�Ǎs���͂قڂ܂Ƃ܂��Ăł������Ǝv���܂��B�ƂĂ����炵�����Ƃł��B����ɂ��݂������k�������Ĕ��f������C���������ł��낢��Ȃ��Ƃ�����Ă����ӎ������߁C���������s���ɂȂ����Ă����悤�ɂ�����Ă��������B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@��ʈ��S�������s���܂��� �@��ʈ��S�������s���܂����U��10���i���j�C�l���s�s�̌�ʈ��S�w�����u�Ƃ݂܂��v�݂̂Ȃ���ɂ��z�����������C�Q���ځC�R���ڂ��g���Č�ʈ��S���������{����܂����B �@�܂��Q���ځB�P�`�R�N���̎q�����ɂ��b���������܂����B �Ƃ݂܂��̂��b�ɂ��ƁC���̂ň�ԑ����̂��u�Ƃт����v�ɂ�鎖�̂��Ƃ̂��ƂŁC�Ƃт����Ȃ����߂̂R�̖u�~�܂�v�u����v�u�҂v�b�p�l�`�̃P�������ƈꏏ�ɁC�y�����C�킩��₷�������Ă��炢�܂����B���́u�Ƃ݂܂��v�̖��O���u�Ɓi�~�܂�j�v�u�݁i����j�v�u�܂i�҂j�v���痈�Ă���Ƃ̂��Ƃł��B �P��������H�܂ł̊Ԃ����Q�����邽�߂ɑޏꂵ����C���x�͂c�u�c�ƃX���C�h���g���Č�ʈ��S�ɂ��Ċw�т܂����B�r���łR�N�������\�R�l�ɏo�Ă�����āu�l�͂����Ɏ~�܂�邩�v�̎���������܂����B�P�x�ڂ̍��}�ő���n�߁C���̍��}�Ŏ~�܂�̂ł����C���}���Ă���X�g�b�v����܂Ő���������܂����B���ꂪ�����S�O�����ő����Ă��鎩���Ԃ��ƁC�C�Â��Ă���~�܂�܂�22�����������Ă��܂��Ƃ̂��ƁB�q�ǂ������́C���̒����ɂт����肷��Ƌ��Ɂu�Ƃт����v�������Ɋ댯����m��܂����B �����̌�͍ĂуX���C�h�ʼn���n���̊댯�ȏꏊ���f���Ă��炢�C���S�ȕ���������(����)���Ă��炢�܂����B �Ō�͎��]�Ԃɏ��Ƃ��Ƀw�����b�g�𒅗p���邱�Ƃ̑���ɂ��Ă��b���Ă��������܂����B�q�ǂ������͂قƂ�ǂ̎q���w�����b�g�������Ă���Ǝ�������Ă��܂������C�u���Ⴀ�C���]�Ԃɏ��Ƃ��ɕK���w�����b�g�𒅂��Ă���q�́H�v�Ƃ̎���ɂ͂R���̂Q���炢�̎q��������������܂���ł����B�u���{�̖@���ŁC�P�R�Έȉ��̎q�͎��]�Ԃɏ��Ƃ��ɂ̓w�����b�g�𒅂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƌ��܂��Ă��܂��B��Ȕ]����邽�߂ɁC�K���w�����b�g�𒅂��܂��傤�B�v�Ƃ̂��b�ɁC�q�ǂ������͑傫�Ȑ��Łu�n�C�B�v�ƕԎ������ĂQ���ڂ��I���܂����B 20���x�݂��͂���łR���ڂ͂S�`�U�N���̎q����ʈ��S�����ɎQ���B�c�u�c���ςȂ��玩�]�Ԃ̓_���̎d����w�����b�g�̐��������p�̎d���C�W���̈Ӗ��Ȃǂ������Ă��������܂����B  �@ �@ �@ �@  �@�S�N���u������ׂ悤�v �@�S�N���u������ׂ悤�v�@�S�N���͂U���V���i���j�Ɏl���s�s���w�K�Z���^�[��{�����e�B�A�̐l���}���āC�u�����쐶���������v���s���܂����B���̊w�K�́C�S�N�����N�Ԓʂ��Ċ��Ɛ����C�����ƏC���T�C�N���Ȃǂ��e�[�}�ɍs���w�K�̈�ł��B �T��28���i�j�ɂ͎s�����̒S�������̐l�����ɗ��Ă��炢�C�������̏o�O���Ƃ��s���܂����B�ƒ�ł���Ȃ��Ƃ��b����܂����B �@�������̕������܂����B�ƂŃp�p�Ɛ��̘b�����܂����B�p�p�� �u�n���́C70�������ŕ����Ă��邯�ǁC�قƂ�ǂ��C���B���Ⴀ�C���߂�͉̂����ł��傤�B�v�Ǝ����������C �u10�����炢�H�v�Ɠ����܂����B�킽���́C �u�R�������Ȃ�B�v�ƌ�������C �u�ւ��`�I�����ȂI�v�ƌ����Ă��܂����B����ɁC �u���Ⴀ�C���������߂�ł��傤���B�v�ƌ�������C �u0.1�����炢�H�v�ƌ����Ă��܂������C �u0.0001���ł����I�v�ƌ�������C�u�ւ��`�B�v�ƌ����Ă��܂����B �@������̐�����������2�N�ڂɂȂ�܂��B��N�Ɉ����������싴����̂Ƃ������ɕ�����āC���������̏W���܂����B�܂���̒�������͂��߂܂����B �앝�F16���C�����F21�x�C�[���F20cm�C�����F���ʁC���F�����C���F���Ɛ� �s�̏W�ł����������t ���@�@�F�J�����c�C�I�I�O�`�o�X�C���V�m�{���C�J�}�c�J�@ �G�r�ށF�X�W�G�r�C�k�}�G�r�C���N�Y�K�j �����ށF�J���Q���C�n�O���g���{�E�R���}�g���{�E�R�I�j�����}�C�w�r�g���{�̃��S�C�i�x�u�^���V�C�`���J�Q���E�C�����L�}���Q���S���E ���̑��F���߂�ڂ��C�G���~�~�Y�C�q�N�i�K�g�r�P���C���X���J�C�K�K���{�C���V�m�{���̂��܂��@�Ȃ� �@�S�N���̎q�ǂ������͊w�Z�ɖ߂�C�����̐��������璩����̐����ׂ܂����B���_�Ƃ��āu���ꂢ�v�ɑ����邱�Ƃ�������܂����B �@�܂��C�U��12���i���j�ɂ́C���w�K�Z���^�[�̐l���}���āC���Ȏ��Ő����̎��������āC����ɒ�����̐��ɂ��Đ[���T��܂����B �@�S�N���̊��w�K�͍���������Ă����܂����C����̊w�K�͂U��20���i�j�̎Љ�w�Ɉ����p����܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@  2�N���u���ՌA�Ɋ肢�����߂��v 2�N���u���ՌA�Ɋ肢�����߂��v�@�{�Z�̑̈�ّO�ɏ����Ȓ뉀������܂��B�����ɂ�2002�N10���Ɋ����������ՌA������܂��B�������C�c�O�Ȃ���C�u�����ɉ�������̂��v�u���ՌA�����Ȃ̂��v���قƂ�ǂ̎������m��܂���B�n��̌𗬂̏�C�w�Z�ƒn��Ƃ̂Ȃ���̏�C�l�̓����ɂȂ���悤�Ɋw�Z�ɐݒu�����Ȃǂ�ړI�ɍ��ꂽ���ՌA������x�q�ǂ������ɒm���Ă��炢�����Ǝv���C�Q�N���Łu���ՌA�w�K�v�����߂čs���܂����B �@2002�N�����C����n��n��Љ�Â��萄�i�ψ���������Ă����J���`��������U���V���i���j�Ɍ}���āC������CTY�̉f���ƒJ������̂��b�������Ċw�K�̎��Ԃ������܂����B �@�w�K�̍Ō�ɂ͎��ۂ̐��ՌA�̉��F�����̂ł����C�݂�Ȃʼn����y���ނ悤�Ƀ}�C�N�ʼn����E���C���������܂����B���ݐ����C�����S���т��Ă������������Ă��܂����B �@���ی�͈�l�ЂƂ肪������悤�ɐ��𗬂��Ă���܂��B�����̒n��̐l�������e���̏��𗬂̏�Ƃ��č��ꂽ���ՌA���w�Z�Ƃ��Ă��C��ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B���N�C���ՌA�w�K�����܂������C���N�x�ȍ~���Q�N���̐����ȂŐ��ՌA�w�K���p�����Ă��������ƍl���Ă��܂��B �@�w�Z�ɂ��݂��ɂȂ����Ƃ��ɁC��x���ՌA�̉��F���y����ł����Ă��������B  �@ �@ �@ �@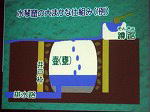  �@ �@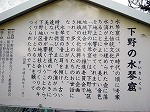 �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
�U���S��(�j �@    �@�^����X���[�K���Q�O�P�R�@�@ �@�@�u�F����J���[�߂ĉ^������CGO!!�v �@�T���Q�T���i�y�j�́C�����ψ�������Ă���܂����X���[�K���̉��C���炵���^������Â����Ƃ��ł��܂����B�Z�����K���Ԃł͂���܂������C�P�N������U�N���܂Ŗ{���ɂ悭�����܂����B�ꐶ�����Ɏ��g�ވ�l�ЂƂ�̎p�ɂ����ς��̊��������炢�܂����B ���S�@�R�N�u������q�Ł@ONE PIECE�v �@�R�N���݂̂Ȃ���̕\���͖{���ɂ݂�Ȃ��킭�킭�����Ă���܂����B�_���X���{���ɍD���Ȃ̂��ȂƂ�����ۂ����������܂����B���Y�����C�̂�傫���g���������C�������C���ׂĂ����͓I�ł����B  �@ �@ �@ �@ ���V�@�Q�N�u�ɂ�ɂ�Q�N���v �@�Ί炪�ƂĂ����Ă��Ɋ����܂����B�y�����_���X�����Ă���̂������ǂ������ł��B�������y�₩�ŁC�ړ�����σX���[�Y�ł����B�܂��C�H�v���Â炵���ޏ�͍D��ۂł����B  �@ �@ �@ �@ ��10�@�P�N�u���܂�@������傢�I�v �@�P�N���݂̂�Ȃ��{���ɂ悭�����܂����B�傫�Ȑ��ł��Ղ�̋C����グ�C���C�����ς��̓����ł悭�W�����v���C���Y���ɂ̂��ĂƂĂ��y�������ł����B�P�N���̑f���ȋC�������X�g���[�g�ɓ`����Ă��܂����B  �@ �@ �@ �@ ��16�@4�N�u�\�[�����߁v �@�{���ɑ傫�Ȋ��������炢�܂����B�S�N���̃\�[�����߂��ԋ߂Ō��Ă���ƁC�k�̊C�Ńj�V����������l�X�̎p���ڂɂ͂�����ƕ�����ł��܂����B�M�̘E�̂��Ȃ�C�Ԃ������p�ȂǁC�͋����������邷�Ă��ȗx��ł����B  �@ �@ �@ �@ ��19�@�T�E�U�N�g�ݑ̑��u�����ւ̒���C�����ցI�v �@�Z�����Ԃł������C���������w�N�Ƃ�����ۂ��܂����B�����܂ŗ���ɂ͖{���ɋ�J�����Ǝv���܂��B�������C����l�߂��ْ����̒��ɂ��C�ق��ē��X�Ƃ����ЂƂ̉��Z�ɁC�݂�Ȃ̈ӋC���݂ƂȂ���������܂����B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@�^����O�ɑS�Z�̎����ɓ`�����u���C�悭�C�͂̌���C�����āC�傢�Ɋy�������v�������ɂ��ׂĂ̋��Z�Ńp�t�H�[�}���X���Ă���܂����B�S�Z�����݂̂Ȃ���Ɂu���������ς��̉^��������肪�Ƃ��I�I�v�Ɖ��߂ē`�������Ǝv���܂��B �@�܂��C�T�E�U�N���݂̂Ȃ���͌W�����ɂ��{���ɂ悭������Ă���܂����B�ꐶ�����ɂ��Ă���p�C���w�N�Ƃ��Ă̐ӔC���C�C�����̗ǂ������Ȃǂ��ׂĂ��ƂĂ��ǂ������ł��B���w�N�݂̂Ȃ���͂��̂P�N�Ԃ̂��ׂĂ̊������ʂł̒��S�ɂȂ��Ă����܂��̂ŁC����Ɏ������g�𐬒������Ă����Ă��������B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �u�����K���a�v���l���� �@�{�N�x����h�{���@�i���m�������w�Z�����j�ɂ��H��w�����ȋy�ё����w�K�C�ƒ�Ȃ̘g���ōs���Ă����܂��B��h�{���@�̖{�Z�̋Ζ����͖��T�Ηj���ł��B���̗j���ɁC���H�w���C�H�Ɋւ���w���C���H���q���w�������s���܂��B �@�T���Q�P���i�j�͂U�N�����u�����K���a��h���H�������l����v�Ƃ����H����Ƃ��s���܂����B�����K���a�Ƃ��āC����C�S���a�C�]�����C�������C���A�a�Ȃǂ������C�ǂ����Ă��̂悤�ȕa�C�ɂȂ�̂����l���܂����B�����̕a�C��\�h����ɂ́u�ǂ������K���v��ςݏd�˂邱�Ƃ��K�v�ł��B�����Ŏq�ǂ������̐H�K�����������Ȃ���C�����K���a�ɂȂ�Ȃ��H�K���ɂ��Ċw�т܂����B �@�����₢�C�y�b�g�{�g�����g���C���t�̗���ɂ��Ď����Ŋm���߂܂����B�܂��C�r�j�[���p�C�v�����ǂɌ����ĂāC���̓����Ɏ��S�y�Ŏ��b��z�肵�Ē�����C���̒��ɓ��𗬂��Ă݂܂����B���b�Ɉ���������C�ǂ�ǂ댌�t�Ɍ����Ă����͎v���悤�ɗ��ꂸ�l�܂�܂����B���b�ɂ�茌�t�������ɗ���ɂ����Ȃ��Ă��邩���m���߂邱�Ƃ��ł��܂����B �@���̂悤�Ȃ��Ƃ��玩���������H�ׂĂ���H���ɂ��āC�ǂ��������������Ԃ炪�����C�̂ɂ͗ǂ��Ȃ������o�������܂����B���Ԃ�̐ۂ肷���ɋC�����Ȃ���Ȃ�܂��C���̂��Ԃ�͌��t�����炳��ɂ��铭��������C���͌��ǂ��������铭�������邩��C��������������ƂƂ�K�v�����邱�Ƃ�������܂����B �@����̎��Ƃ͂Q�w���ɂ����P���ԍs���̂ł����C�����K���a�͓ˑR�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��C�q�ǂ����ォ��̐H�K���̐ςݏd�˂łȂ邱�Ƃ��m���߂܂����B���������̐H�K����������������������������Ă��������Ǝv���܂��B  �@ �@ �@ �@  �M�������}������Ă��� �M�������}������Ă����@�T��30���i�j�Ƀg���{���m�̐Γc���O�搶�������āC�R�N���͖{�Z�̃v�[���Łu�v�[�����S���~�o���悤�v���s���܂����B��N�x�̂R�N�����v�[���̃��S���~�o���C�����ʼnH�����������̂ł����C��N�x�̃v�[������̓V�I�J���g���{��A�L�A�J�l�̃��S�����~�o�ł��܂���ł����B�����ŁC��N�x�̂X�����߂ɁC�R�N���͒�����ɏo�����āC�����������Ă��܂����B������v���X�e�B�b�N�̂����ƃy�b�g�{�g���ō�������Ɉ���}���C���̕������v�[����10�قǕ����ׂ܂����B���̕����ɃM�������}������Ă��āC�����Y�݂����̂ł��B �@�P���Ԗڂ���R�N���͑̈�قŐΓc�搶����g���{�̘b�����������܂����B �� �g���{�͍����̒��ōł��Â����̂ŁC�R���N�O���琶���Ă���B �� �Â��`���g���{�͎c���Ă��āC�H��w���̏�ɏd�˂Ă����߂Ȃ��B����̓g���{�Ƃ����낤�����ł���B �� �M�������}�͂X���`11���ɗ����Y�ނ�10������Q�T�ԂŃ��S�ɂȂ�B���N�Ő����ɂȂ邪�C���S�͂��̊�13��E�������B �� �w�����c����S�͂قڂR�`10���ʼnH�����邪�C�w�����c����S�͉a��H�ׂȂ��B�Ȃ��Ȃ�C�����������̂悤�ɕω����C�a���H�ׂ��Ȃ�����ł���B �� �w�����ւ���ł��郄�S�͂�����˂��o���āC�ڂ̑O�ɗ����������͉̂��ł��H�ׂĂ��܂��B���H��������B �s�v�[���ł̃��S�~�o���t �@���b������C���S�̋~�o�Ƀv�[���Ɍ������܂����B�q�ǂ������͑҂�����Ȃ��l�q�ŁC�v�[���ɓ���܂����B�v�[���̋��𒆐S�ɂ��ꂼ��̖Ԃ����Ă����Ƃ������낢�قǂS�`�T�p�قǂ̃M�������}�̃��S���Ƃ�܂����B����Ȃɂ�������̃��S���������Ƃ͂Ȃ��C�����������ă��S�Ƃ�ɖ����ɂȂ��Ă��܂����B�������C�Ȃ��Ȃ��G��Ȃ��q�����܂����B�~���Ă݂�ƁC���ׂẴ��S�̓M�������}�ł����B����́C�Γc�搶�������Ă��܂������C�v�[���ɃV�I�J���g���{��ԂƂ�ڂ͋��痑���Y��ł����C���S�ɂȂ����̂ł����C�����͂��ׂăM�������}�̃��S�ɐH�ׂ��Ă��܂��C�M�������}���������ރv�[���ɂȂ����̂ł��B �s�M�������}�̃��S�̎������t �@�y�b�g�{�g���������ɐ�C�����Ƀv�[���̐��ƐԒ��Ȃǂ������Ă���Ƃ��������B�����ɂł����50�p���炢�̖_��������Ȃ��悤�ɗ��Ă�Ƃ悢�ƕ����C�L���ł݂�ȂŎ����n�߂܂����B�������烄�S�̉H�����n�܂�C���X�ɑ�ϗ��h�ȃM�������}���a�����܂����B �@���̂悤�ɁC�M�������}�̉H�������邱�Ƃ��ł����̂��C��N�x�̂R�N�����v�[���Ɉ��̕����������Ă��ꂽ�������ł��B�g���{�̖��̌p���ƁC�w�N�̎��g�݂̃����[���ł��܂����B�R�N���͂X���ɂ͗��N�̂R�N���ɃM�������}�̖����p����Ƃ��s���܂��B 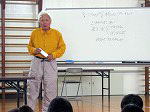 �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
||||||
�S��26���i���j    �p�ꊈ�����͂��܂�܂��� ���N�̉p�ꊈ���͂S��23���i�j����n�܂�܂����B�T�E�U�N�͏T1���ԉp�ꊈ���T���j���ɍs���܂��B�P�N������S�N���ɂ��ẮC�N�ԂS�`�T���Ԃ̉p�ꊈ�����s���܂����C���ƊO�Ƃ��Ď��{���܂��B�T�E�U�N���̔N�Ԏ��Ǝ�����35���ԂŁC �p��w�����Ƃ��č��N��Dorina Araki�i�h���i�E�A���L�j�搶���}����25���Ԏ��Ƃ�S�C�ƈꏏ�ɍs���܂��B�܂��c���10���Ԃ͌����ʔ��u�t�̐�搶�ɉ�����Ă��������āC�S�C��TT�ʼnp�ꊈ����i�߂Ă����܂��B �@���w�Z�̉p�ꊈ���́u�����𒆐S�ɊO����Ɋ���e���܂��銈����ʂ��āC����╶���ɂ��đ̌��I�ɗ�����[�߂邱�ƁB�ϋɓI�ɃR�~���j�P�[�V������}�낤�Ƃ���ԓx���琬���C�R�~���j�P�[�V�����\�͂̑f�n��{�����ƁB�v��ڕW�ɉ����𒆐S�ɂ����������s���܂��B�P��╶���͎��Ƃň����͂��܂����C��������ǂ�ł���w���͊�{�I�ɍs���܂���B �@�h���i�搶�Ɏ��ȏЉ�������Ă��炢�܂����̂ŁC�Љ�܂��B �@My name is Dorina Araki. I�fm from Romania, but I live in Japan, Suzuka with my husband and my son. I�fm an assistant language teacher in five elementary schools and I like my students very much. I can speak four languages: Japanese, English, Romania and Portuguese. I love Japan very much. Sushi is my favorite food. Me and my family used to go to Onsen almost every end of the week. I�fm interesting in Japan culture and kimono. I play soccer very much. Thank you! �i���̖��O�̓h���i�E�A���L�ł��B���[�}�j�A�o�g�ŁC���͕v�Ƒ��q�ƎO�l�ŗ鎭�ɏZ��ł��܂��B�^���͂T�̏��w�Z�ʼnp��w����������Ă��܂��B��ώq�ǂ��������D���ł��B���͂S�������b���܂��B���{��C�p��C���[�}�j�A��C�|���g�K����ł��B��ϓ��{���D���ł��B�^�����͎��̍D���ł��B���ƉƑ��͖��T���قƂ�lj���ɂ悭�s���܂��B���͓��{�����ƒ����ɋ����������Ă��܂��B���̓T�b�J�[������̂���D���ł��B��낵�����肢���܂��B�j  �@ �@ �@ �@ |
||||||
| 4���P7���i���j �@�@    �s�w�Z����ڕW�t�@�@  �@�u�����l���@�������������q�ǂ��v �@�@�`������Ƃ��ɐ����钆�ōl���C���悭�����悤�Ƃ���q�̈琬�` �@�k�߂����q�ǂ��̎p�l �@�@�@���Ƃ��ɐ����邱�Ƃ��v���q �@�@�@���m�邱�Ɓ@�w�Ԃ��Ɓ@�l���邱�Ƃ��y���ގq �@�@�@�����N���ɂ���q �@�S���W���i���j�Ɏn�Ǝ��C���w�����I���C66���̐V�P�N�����}���܂����B�S��10���i���j�ɂ͋��H���n�܂�C���Ƃ��X�^�[�g���܂����B���N�̂P�N������C�P�N���Ɍ����Ďl���s�s�ł͎s�Ǝ���30�l�w�������{���܂����B���̂��߁C�P�N���͊e�N���X22���Ə��l���Ŋw�K�������߂Ă��܂��B���Ƃ��n�܂�P�T�Ԃ��o���܂������C�Â��Ɏ���グ�C��ϗ����������l�q�Ŏ��Ƃ��i�߂��Ă��܂��B�P���Ԃ��I���Ɓu���C���ꂽ�v�Ɛ����������قǁC�W���ł��Ă���Ɗ������܂����B�Q�N���ȏ�̊w�N�̎q�ǂ��������w�K��|���C�V�тȂǂɑ�ς悢�p�������Ă���Ă��܂��B�܂��C�n�Ǝ��ł������̑厖����`���C�ł���Ύ������炠�������ł���悤�ɂȂ�Ƃ����Ƃ��b���܂����B�q�ǂ������͒��o��ƁC����������Ă��Ă����������Ă����q�����������Ă��܂����B��ς��炵�����Ƃł��B �@���C���̍Z��O�ɗ����Ă���ƍ��Z���̎q�������T�`�U�l���]�ԂŒʂ��Ă����܂��B���Z���̂��Z�����ɂ����u���͂悤�v�Ɛ���������ƁC��߂����āC�u���͂悤�������܂��v�Ɛ��������Ă���܂��B�������͕s�v�c�Ȃ��̂ł����C���݂��̂Ȃ���������܂��B���ꂩ�����������厖�ɂ��āC�Ί炪���ӂ�鉺�쏬�w�Z�ɂ݂�Ȃł��Ă����܂��傤�B �@�@  �@ �@ �@ �@ �@���āC���쏬�w�Z�̊w�Z����ڕW�́u�����l���@�������������q�ǂ��v�ł��B�킽���������E���͂��̊w�Z����ڕW�����ׂĂ̊�{�ɂ��Ċw�K�⋳�犈����n��グ�����ƍl���Ă��܂��B�q�ǂ������͓��X�̐�����̌��C�o�����炽������̂��Ƃ��w��ł����܂��B���܂��������Ƃ����܂������Ȃ����Ƃ������ς�����ł��傤�B��l�ł͂ł��Ȃ��Ă��C�Ȃ��܂ƈꏏ�ɂ���ł��邱�Ƃ������Ă���ł��傤�B���̂悤�ɁC�w�K�⊈����ʂ��āC�w�э����C������荇���C�炿�����W��厖�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�����āC�����̂悳�ɋC�Â��C�����Ɏ��M���萶���C����̖���`���C��̓I�ɐ�����q�ǂ���������悤�ɁC���E����ۂƂȂ��ēw�͂����Ă܂���܂��B��N�Ԃ�낵�����肢���܂��B �@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�{�N�x�̎��g�݂̃L�[���[�h�Ƃ��āC�u�L�����A����v���f���܂����B�{�Z���l����u�L�����A����v�Ƃ́C���ȗL�p�������߁C���Ȃ����߁C����̐l�����ƂƂ��ɎЉ�Ƃ̂������������C�����܂���������͂���ނ��Ƃł��B���́u�L�����A����v�̎��_����w�Z����̊����S�ʂ̌��������s���Ă��������ƍl���Ă��܂��B�u�L�����A����v�ň�݂����͂��u�������́v�u�݂߂�́v�u�������́v�u�߂����́v�ƕ\�����C���̂S�̊ϓ_�����̓I�Ȏq�ǂ��̎p��`���C���ȗL�p���C������͂�L�����Ƃ�ڎw���Ă����܂��B�����āC�����̗͂���ނ��߂ɂ́C�q�ǂ����g����̓I�Ɋw�K�⊈���Ɏ��g�ޏ�̐ݒ����e��������Ɛ��������Ă����܂��B �@          |
||||||
�S���W���i���j    �@�傫����������1�N�����悤�I�@  �@�V�P�N���݂̂Ȃ���C�����w���߂łƂ��������܂� �@�ݍZ���݂̂Ȃ���C�i�����߂łƂ��������܂� �@�݂Ȃ���́C���̈�N�Ԃ��ǂ̂悤��1�N�ɂ������ƍl���Ă��܂����B�ڕW�������Ĉ�N�Ԃ�L�Ӌ`�ɉ߂����Ă��������B�Z���搶����݂Ȃ���ɖ]�ނ��Ƃ́C�u�傫�����������N�ԁv�ɂ��Ăق������Ƃł��B���N�ɉ߂������ƁC�w�K�ɂ���邱�ƂȂǂ��l�����܂����C����Ɏ����̎���̐l�̂��Ƃ�F�����̂��ƂȂǂɋC��z��C����̗���ɗ����čl������悤�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂��B�������g�ȊO�̂��Ƃɂ��ڂ��ނ��C�����ɂł��邱�Ƃ͂Ȃ����Ȃǂ��l���Ȃ��琶�������C�s���Ɉڂ��Ă����C�����Ƃ݂Ȃ���͑傫�Ȑ������}���Ǝv���܂��B�搶�������݂Ȃ���̂�������������Ɖ����������Ǝv���܂��̂ŁC�݂�Ȃœw�͂��C��l�ЂƂ�̂悳���P����������Ȋw�Z�ɂ��Ă����܂��傤�B  �@ �@ �@ �@ �@�N�x���߂ɍ�N�x�̍ݍZ���݂̂Ȃ���̂�������Љ�C�N�x�̎n�܂�̂悫�X�^�[�g���݂�ȂŐ肽���Ǝv���܂��B �� ���̂��C�ق���������������܂����B�O�́C�搶�� �u�悭�킩���ˁB�v �ƌ����āC�ڂ��́u�ǂ�������������ȁ[�B�v�ƍl���āC�u����ł������ȁB�v�Ǝv���āC��������C�搶�� �u�������B�v �Ƃق߂��āC���ꂵ�������ł��B�i�R�N�j �� �P�N�Ԃ�U��Ԃ��ĐS�Ɏc�������Ƃ��Q����܂��B �@�P�ڂ́C�O�����y��ł��B�킽���́C������Ƃ����āC���ɂӂ��܂���ł����B�ł��C�݂�Ȃ͏��ɂł��Ă��܂����B �@�Q�ڂ́C���̂��Ƃł��B��������C�搶�ɂ�����Ă����̂ɁC���͎��������Œ���������Ă���̂ł����Ǝv���܂����B �@�S������͂T�N���ł��B�T�N���ł́C�Y�ꕨ���O�ɂ��āC�e�X�g��100�_���Ƃ��āC���������܂��B�T�N���ɂȂ��Ă��C�S�N���̎v���o���킷��܂���B�i�S�N�j �����i�͂����Ȑl�����ɑ�ɂ���Ă���B���i�ł͔��i�ł��������Ȃ����������������邱�Ƃ��킩�����B���i�͌Â����炠�邩����i�ɂ������Ȃ�������������̂��Ǝv���܂����B�����T�[�����̂��Ƃ����܂�킩��Ȃ��̂Œ��ׂĂ݂����Ǝv���܂����B�i�T�N�j  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@           |
||||||
3��25���i���j    �@�i�����߂łƂ��������܂��@�@  �@�@�|���쏬�w�Z�͈�l�ЂƂ�Ő��藧���Ă���| �@���Ɛ��݂̂�Ȃ͗��h�ɗ������Ă����܂����B���Ǝ��͒g���ȓ��ƂȂ�A�V��ɂ��b�܂�C�����ς��̊���������������Ǝ��ɂȂ�܂����B���Ɛ��́u�ʂ�̂��Ƃv���ϗ͋������C���́u�������̓��Ɂv�������ɉ̂��グ�Ă���܂����B�܂��C�T�N���݂̂Ȃ���̂��Ԃ��̂��ƂƉ̂������Ƃ�Ǝv��������������ς��炵�����̂ł����B���炵���������v���[���g���Ă��ꂽ���Ɛ��ƐV�U�N���Ɋ��ӂ��܂��B �@��N��U��Ԃ�Ɩ{���ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ�����܂����B��l�ЂƂ�̎q�ǂ������̂��̎����̏u�Ԃ̋P���Ă����p���v�������т܂��B�g�C���̃X���b�p����l�ł��ꂢ�ɕ��ׂĂ�����w�N�̒j�̎q�A�n��̋Ǝ҂̕������t��������������w�N�p�T�b�J�[�{�[���ɁA���X�ɏo��������̋C������`���Ă��ꂽ�q�ǂ������A�o�Z�ǂŏW���ꏊ�ɗ��Ȃ��q��S�z���Ă����Ƒ҂��Ă��Ă��ꂽ�ǒ�����ȂǁA�q�ǂ������͒N�Ɍ����邱�Ƃ��Ȃ������̔��f�Ői��ŕ����Ɏ��g�ގp�𐏏��Ō��܂����B�܂��A�^����A�q�ǂ��܂�A�C�w���s�A���R�����A�Z�N���𑗂��Ȃǂ�ʂ��āA�W�c�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�C�ƌ̂������C���K�̐ςݏグ�̐��ʁC�S�ƐS���ʂ��������p�������̊�����^���Ă���܂����B�������C���̏W�c���x���Ă���̂́C��͂��l�ЂƂ�̑��݂Ȃ̂ł��B��l�ЂƂ�̎v���Ƃ�����荇����������^���Ă����W�c�����肾���̂ł��B���̈�N��U��Ԃ�C��l�ЂƂ�g���S���{���ɑ傫�����������Ǝv���܂��B�݂Ȃ���̗��N�x�̔��Ɋ��҂��܂��B  �@ �@ �@ �@  �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ �@ �@ �@ �@ �@  �@�����{��k�ЂɎv�������@�@ �@�����{��k�ЂɎv�������@�@�@�����Q�T�N�R��11���ŁA���̑�k�Ђ���2�N�ڂ��}���܂����B���̓��Ɋe�w���ł́A�u�Ђ܂��̂����v�Ƃ����G�{��ǂ�A���b��������Ɗw�N�ɉ������l���鎞�Ԃ������܂����B �@�T�N�Q�g�̊w���ʐM��ǂ݁A���БS�Z�����݂̂Ȃ���ƂƂ��ɍl���Ă݂����Ǝv���A�����ɂ��鎙���̕��͂��Љ���Ă��������܂��B�i�T�|�Q�w���ʐM���f�ځj ��������Q�N�O�A���k�̑����m���ő�k�Ђ�����܂����B �Q�F�S�U�̂��Ƃł����B���͉��Z���ŁA�L�k����ƂĂ��͂Ȃ�Ă���O�d�ł��A���̂��������܂����B�ӂ��ɂ��Ă��Ă��킩��܂����B�Ԃɏ���Ă���悤�Ȃ��`�Ƃ������ł����B���͂��̂܂܋A��܂����B���ꂳ�e���r�����āA���낤�낵�Ă��܂����B���̎����́u�����������v�Ǝv���܂����B ���̒ʂ�A���k�̕����A�{��A���̒���ԁA�����A�c��ڂ��������̂��������Ă����܂����B���́A�v�킸�ACG�������̉f�悾�Ǝv���܂����B���ꂳ���������܂����B �u�Ôg����B�����݂������ˁB�v �Ƃ����܂����B���̂��ƁA��l�́A�e���r�̑O�Ń{�[�ƍ����Ă��܂����B���̎�����A�V����e���r�Łu�Ôg�v�A�u�Ôg�v�ƕ����悤�ɂȂ�A���̓e���r�̑O�ł����ƍl���܂����B�u�E�\���B�����M���������ǁA����͖{���̂��ƁB�v ���ꂩ�疈���A�e���r�ɂ͖S���Ȃ����l�̐l�����̂�悤�ɂȂ�܂����B�ǂ�ǂ������Ă����܂����B�S���Ȃ����l�̉Ƒ��̘b���e���r�ŕ����܂����B�{���{���ŕς��ʂĂ��Ƒ��̎p�A�����Ȃ��炻�̘b�����Ă��܂����B�u�ڂ̑O�ŗF�����������ꂽ�B�v�u��������Ă��ꂽ���������������ł����̂�ڂ̑O�Ō����B�v�ȂǁA���킢�����Șb����ŁA���������āA�܂��~�܂�܂���ł����B ���̂�������͌x�@���ł��B�Ȃ̂ŁA�V���̏I���ɓ��k�ɍs���܂����B�Z�ɂɃo�X�����������Ă���Ƃ���A��������������čL�X�Ƃ��Ă��܂����y�n�B��������́A����̖{����Ă��܂����B���ɑD���オ���Ă���ʐ^�A�Z�ɂ��{���{���ɂȂ��Ă���ʐ^�A���Z�����Ɠ�l�ł��܂��Ă݂Ă����̂��o���Ă��܂��B ���̂��ƁA����Șb���e���r�ŕ����܂����B�Ō�̍Ō�܂Ŏq�ǂ�������Ă����l�A���������đ����̐l�������悤�ƁA�݂̂��܂��Ō�܂ŕ����𑱂����l�A�����݈��̏�ł���Ɗ݂ɂ����l�A���낢��Ȑl�����܂����B ���͂����l���܂����B�����邱�Ƃ͍K�����Ǝv���܂����B���������Ă��������Ȃ��l�������ς��������Ƃ�Y��Ȃ��ł������Ǝv���܂����B �@�����āA����ɒ����V���̃R�����̐蔲�����͂�A���̒��ɏ�����Ă����{��̏��R�̏��̎q�̃G�s�\�[�h�i���̓��̒��A��e�ƃP���J���Ďӂ�Ȃ��܂܊w�Z�ɏo�������B�A��r���n�k���N����A���̎q�͊w�Z�ɖ߂��Ė������������A��e�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�n�k�̂������̂����j���������̂ŁA���j���̂Q�F�S�U�Ƀx����炵�A��e�Ɂu�S�����l�v�𑗂��Ă���B�j�ɂ��Ă��R�����g�������Ă���Ă��܂��B �u���͍Ō�́u�S�����l�������Ă���B�v�̂Ƃ��낪�ƂĂ����킢�����ɂƎv���܂����B�ӂ�Ȃ������q�͐S�c�肾�Ǝv���܂����B�ƂĂ����킢�������Ǝv���܂����B �S���Ȃ����l�͖߂��Ă��Ȃ�����ǁA���C�͖߂��Ǝv���܂��B�Ȃ̂ŁA���k�̐l�����ɑ������C�ɂȂ��Ă��炢�����Ǝv���܂��B�v �@ |
||||||
| �@ | ||||||
| �l���s�s���@���쏬�w�Z �O�d���l���s�s������475-1 Tel 059-336-2000�@�@�@�@�@Fax 059-336-2001 Copyright Shimono Elementary School |
||||||